将軍の器 ~籤引き将軍 足利義教~
度の歴史の木戸口 史の綴りものは、前回から続きまして、いよいよ室町幕府六代将軍、足利義教の時代へと進みたく存じます。三代将軍足利義満の子にして、兄である四代将軍義持の跡を継ぎ、神籤によって六代将軍となることが決まった足利義教、その将軍としての器はいかに。
後継争いを避けるため、応永十年(西暦1403年)青蓮院に入室し僧籍に身を置くこととなった義教でしたが、程なく青蓮院門跡であった尊道法親王が逝去、義教の長兄にあたる尊満が先に精錬院に入室しており門跡を継ぐはずではあったものの、何らかの理由で青蓮院を追われてしまうのでございます。生母の加賀局の身分が相応でなかったことによるものか、僧籍に入る前からも長男としての扱いは受けられておらず、さりながら青蓮院からこの時期に追われてしまったのが門跡を継ぐことを妨げる意思によるものかどうかは、知り得ぬところでございます。やがて、後の義教は応永十五年(西暦1408年)に得度して門跡となり、義円と名を改めるのでございますが、これは同時に三代将軍義満の後継争いから正式に外れたことを意味するものでございました。
ここで青蓮院について少し触れておきたく存じます。
主には不要な後継争いを避けるべく皇族や摂関家の子弟が入寺し、取分け皇族出身で親王の称号を与えられた僧侶が法親王・入道親王として門主となるのが門跡寺院でございますが、伝教大師最澄による開山の青蓮院は、天台宗三門跡に数えられます。比叡山上に最澄が建立した青蓮坊がその起源であり、平安時代も末の頃、久安六年(西暦1150年)に鳥羽上皇と皇后美福門院が青蓮坊第十二代、行玄大僧正に帰依し青蓮坊を祈願所としました。このことにより寺格が上がり始めまして、さらに鳥羽上皇が第七皇子の覚快法親王を行玄の弟子として入寺させ、以降、青蓮院は皇族や摂家の子弟が門主を務める格式を持つ寺院となっていったのでございます。そしてそれに伴い、青蓮坊は院の御所に準じ都に殿舎を造営し、青蓮院と称されることとなったのでございます。ただ、山上には青蓮坊がそのまま残されており、やがて廃絶する室町時代まで寺籍は保たれていたそうでございます。
青蓮院となって後、第二世門主となっていた覚快法親王の薨去後、養和二年(西暦1182年)になりまして紆余曲折を経ながらもその後を継いだのが、歴史書『愚管抄』を記したと伝えられる慈円でした。天台座主として法会や伽藍の整備、また政においては実兄である九条兼実の孫・九条道家の後見人を務め助言を惜しまず、その道家の子・頼経が公家将軍という形で鎌倉に下向することにも期待を寄せ、公武の協調をこそ理想としたと伝えられております。それだけに、後鳥羽上皇の挙兵の動きに対しては反対を唱えましたものの、ついに聞き入れられず、世に言う承久の乱へと時は進んでしまうのでございました。
『徒然草』によれば、何らか一芸ある者であれば身分に関わりなく召しかかえてかわいがったとあり、その真摯で芯が強く、時の流れの中で生み出されたあるがままを受け入れ融和させていこうという心の広さが伺い知れますが、後に浄土真宗の宗祖となる親鸞も、慈円に教えを授けされたひとりであり、治承五年(西暦1181年)9歳の折、慈円について得度を受けております。
そのように格式ある青蓮院に入室し義円と名を改めた後の六代様足利義教でしたが、応永二十六年(西暦1419年)11月には第百五十三代天台座主ともなり、「天台開闢以来の逸材」とまで呼ばれるほどの才を示したと伝わっておりまする。しかしながらその義円が次の将軍に選ばれたのはその才ゆえではなく、神籤によるものでございました。申すまでもなく人知の及ばぬ存在が義円を選んだ、という考えが成立する傍らで、この時代でさえ、やはり籤による選び方というのは異例であり、人々の心の底には、どこかで『くじ引きで偶然選ばれた』という思いが横たわっていたのもまた否とは言い切れぬものであったのかもしれませぬ。そしてそれは、当の義円、足利義教自身の心の中にもまた同じく横たわっていたものと言い得るものではなかったのでございましょうか。
いずれにいたしましても、兎にも角にも次の将軍が定まったのでございますので幕府重臣たちとしては、将軍不在という権力の空白期間を一日でも短くすべく働きかけを急ぎますものの、元服前に出家していた義円は、俗人としてはいまだ子供という扱いになってしまい、無位無官のままでございました。尚且つ、法体である身の者が還俗し将軍となった先例もなかったことから武家伝奏の万里小路時房は強く反対し、まず義円の髪が伸び、元服できるようになるまで待ち、その上で次第次第に昇任させてゆくべきであるとした。公卿の多くも同意であり、武家の力が強大なものとなってまいりましたこの時代ではありながら、幕府と雖もそれを跳ねのけて無理を通すほどの力はまだなく、二月ほどが過ぎ、漸く義円は還俗、名を義宣と改め従五位下左馬頭に叙任されたのでございまする。そして正長二年(西暦1429年)には、義教と名を改め参議近衛中将に昇った上、ついに征夷大将軍となるのでございました。改名は「義宣」(よしのぶ)が「世忍ぶ」に通じるという俗難を不快に思ったためだそうでございますが、それではと公家が協議の上で新たな名として「義敏」となすことを決めておりましたものの、「敏」よりも「教」の方が優れていてよい、と摂政・二条持基を通じてこれを正させるなど、六代将軍、意思の非常に強いところがすでに垣間見えるのでございます。
こうして六代将軍、足利義教の治世が始まったのでございますが、その目指すところは、未だ盤石とは言い得ぬ幕府権威、そして幕府そのものの力を三代義満の治世を手本としつつ取り戻し、高めていくこと、そしてそれを将軍親政という形で成し遂げていくことにあった様でございます。
かつて天台座主となり「「天台開闢以来の逸材」とまで呼ばれるほどの才を持ち、体に流れる血は足利家と幕府の力を高め南北朝合一を成し遂げた三代将軍義満を父とするもの、そして自らの力で幕府の力を高めていくことを志す者が、名実共に室町殿となったのでございます。将軍親政を目指す政の手始めとして、義教は諸々の決定を将軍主宰で行われる御前沙汰にて行う、また管領を通して行われてきた諸大名への諮問を将軍直接諮問とするなど、幕府管領の権限抑制策を打ち出していきました。また、体制として有力守護に実質依存していた軍事政策を改め、将軍直轄の奉公衆を強化再編し、幕府直轄軍事力の強化を進めていこうといたしました。
寺社勢力に対し積極介入を繰り返したことも知られ、取分け自身が天台座主であったことから、還俗後すぐ弟の義承を天台座主に任じ、天台勢力の取り込みを図るも、延暦寺の弾劾訴訟からはじまる争いはやがて泥沼化の様相を呈し、義教の苛烈な対処は、事態を収束とは逆へと向かわせてしまうことしばしばでございました。また幕府を支える斯波氏、畠山氏、山名氏、京極氏、富樫氏、今川氏など有力守護大名家に対して将軍の支配力を強めるべく家督継承に強く干渉するようになり、意に反した守護大名、一色義貫や土岐持頼は大和出陣中に誅殺されるほどでありました。そして誅殺された彼らの所領は義教の近習に与えられるなど、苛烈で強硬な政策を推し進めることは、結果守護大名たちに大きな不安を与えることにつながったのでございます。また、義教の苛烈さは些細なことにおいてもあらわれ、繰り返される厳しい処断は義教の治世を万人恐怖と言わしめるものとなってしまったのでございます。
そのようなことから畏怖された、と申しますよりは恐れられた六代様と申した方が当を得ていると思われる将軍義教でしたが、幕府最長老格ともなっていた四職の一家である赤松家当主、赤松満祐は将軍親政を進める義教に疎まれる様になっており、永享九年(西暦1437年)頃には播磨、美作の所領を没収されるとの噂が流れておりましたが、永享十二年(西暦1440年)、義教は赤松満祐の弟・赤松義雅の所領を没収の後、その一部を義教自身が重用する赤松氏分家の赤松貞村に与えたのでございます。
嘉吉元年(西暦1441年)六月二十四日、満祐の子の赤松教康は、関東の結城合戦での祝勝の宴として松囃子(赤松囃子・赤松氏伝統の演能)を献上したいと称し西洞院二条にある邸へ将軍義教の「御成」を招請したのでございます。将軍が家臣の館に出向き祝宴を行う御成は重要な政治儀式であり、義教は管領細川持之、畠山持永、山名持豊、一色教親、細川持常、大内持世、京極高数、山名熙貴、細川持春、赤松貞村と、いずれも義教の介入により家督相続を成しえた、いわば義教子飼いの大名衆でございました。
赤松邸にて猿楽を観賞していた折、突如屋敷に馬が放たれ門が一斉に閉じられた音がしたのでございます。異変を感じた義教は「何事であるか」と叫ぶも、傍らに座していた正親町三条実雅が「雷鳴でありましょう」と答えたと伝えられております。したがその直後、周りの障子が一斉に開け放たれ、甲冑姿の武者たちが宴の座敷に乱入、義教は赤松家随一の武勇を誇る安積行秀に討ち取られてしまうのでございました。
不安定であった幕府権力を強め、中央集権化を図ろうとした将軍義教の政そのものは、国としては理に適ったものであったかと思われまする。幕府財政強化のため明との貿易も再開させた義教には、海の向こうすら見据えていたのかもしれず、義教の頭の中には、こうあるべき、という絵が描かれていたのかもしれませぬ。ただ、それでは六代様からそれを伝える声は発せられていたのでしょうか。義教が子飼いとした大名衆は何かそのような声を聞いていたのでしょうか。今となっては知る由もございませんが、少なくともそのような義教の声は、届いていなかったか、もしくは発せられてすらいなかったのかもしれませぬ。苛烈さだけが伝わり、その先に目指すものについて伝える声なくしては、人は怖れ、離れ、やがては己が身を守るため反旗すら翻すもの。
義教亡き後、室町幕府は義教の嫡子千也茶丸(足利義勝)を次期将軍とすることを決するも、幼少の義勝には幕府重臣の支えが欠かせず、且つ義勝が在任わずか八ヶ月、齢十の若さで亡くなると、弟の足利 義政へと将軍の座は継承されていくも、二代続けて幼少の将軍が続いたことにより幕府の政は再び有力守護大名により進められる形へと戻り、これ以降室町幕府において将軍が将軍たる権力を持つことはなく戦国期にその終焉を迎えてしまうのでございました。
聡明であった義教が、もし人との和を重んじ、その声を己の目指すもの、描く国の姿を伝えることができていたとしたら、室町幕府の体制は大きく変わり、歴史に刻まれている戦乱の世を迎えることはなかったのかもしれませぬ。ひとりで成し遂げられることには限りがあります。それを知り、思いを伝える声を持ちえて初めて、成せることがあるのは、今も昔もあまり違いはしないのではないかと、六代様の政を振り返り、感ずるものでございます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

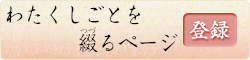
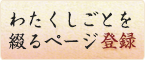



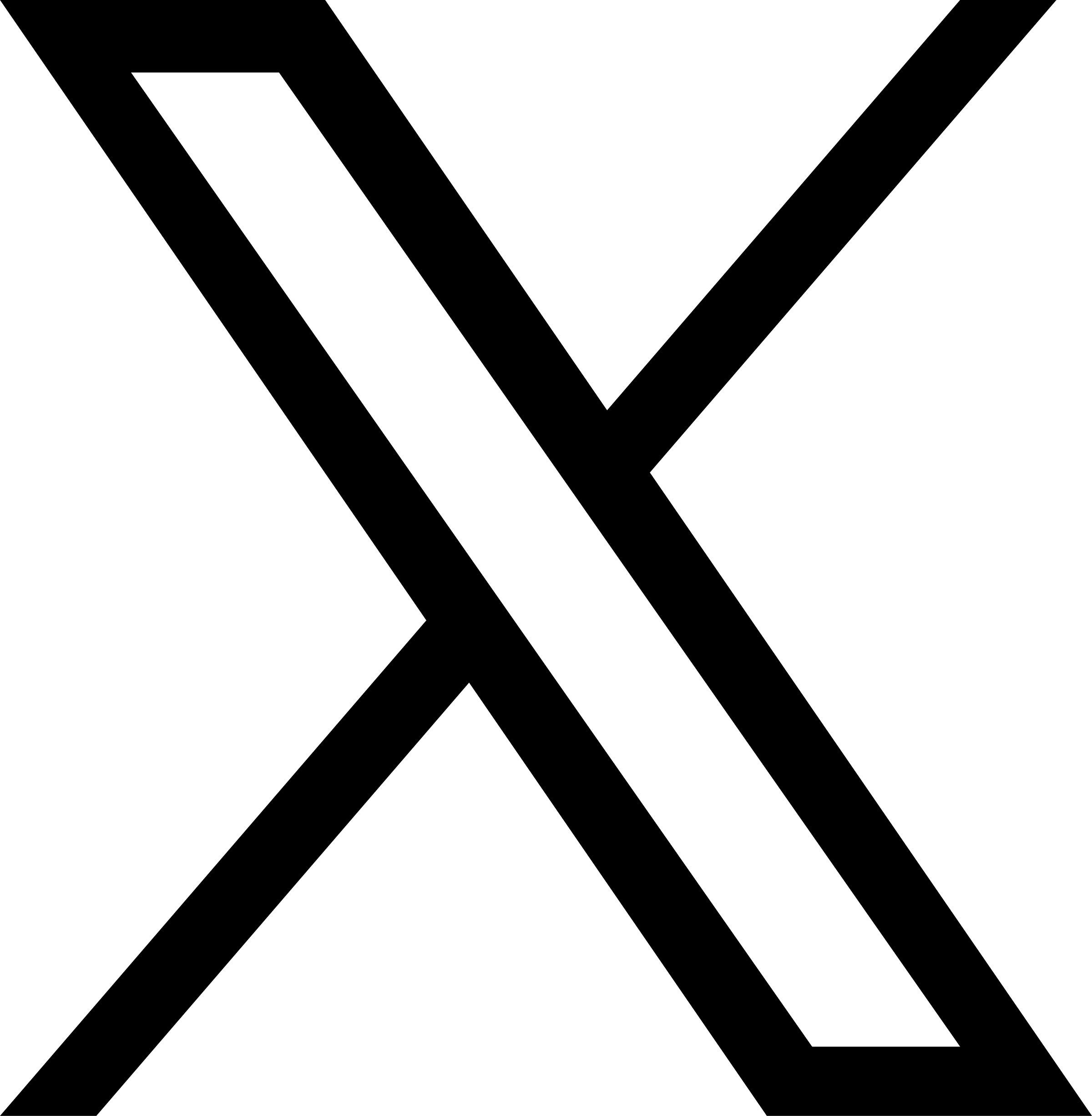
 Facebook
Facebook