将軍の器 ~籤引き将軍 足利義教~
此度の歴史の木戸口 史の綴りものは、室町幕府六代将軍、足利義教公のお話につなげつつ、少し時代を遡りまして、そもそも将軍の器とは何ぞや、ということにふれるお話でございます。
さて、六代様と敬われ、いや寧ろ恐れられたと申しました方がより真に近しいかもしれぬ室町幕府第六代将軍、足利義教。何故籤引き将軍などと呼ばれるのか、と言えば、それは後継を定めぬまま死去した四代将軍、足利義持の意向を受けた幕府重臣が協議を重ねた末、将軍を義持の四人の弟たちの内から籤で選ぶこととしたことによるものでございます。
ところで、何ゆえ四代将軍義持の没後、選ばれたのが六代将軍かと申しますれば、若くして五代将軍の座を義持より引き継ぐこととなりました足利義量が世継ぎをのこさぬまま早世し、義持は義量の他に男子に恵まれなかったため、前将軍である義持がふたたび幕政を執る事態がつづいていたためでございます。
義量に将軍職を譲った後も幕政の実権は義持を中心に、義持と有力守護が握ったままであったこともあり、幸いにも政が大きく滞るようなことはございませんでした。歴史が示すように、後代までふくめて実に二十八年間、室町幕府歴代の中で最も長く将軍であった義持でしたが、その義持にも病に斃れる日が訪れます。応永三十五年(西暦1428年)湯殿で、尻にできた腫れ物を掻き破った義持は発熱し、尻の雑熱(腫れ物)が痛み座ることもできぬほどとなってしまいました。僅か数日の間に尻の雑熱はさらに腫れあがり、やがては傷口が腐りだしたと伝えられております。
そしていよいよ義持が重篤な状態となり、慌てた幕府重臣(管領 畠山満家および、斯波義淳、細川持元、畠山満慶ら)は、醍醐寺の僧 満済の下に集まり、義持の後を誰が継ぐのかについて協議をするのでございました。その上で、満済が義持に後継の意向を問うも、自ら後継者を定めることを否としたのでございます。さりながら天下の重大事、重ねて問うた満済に義持が伝えたことは、重臣たちでこれを決すべしということでございました。それをうけて重臣たちは血筋から義持の後を継ぐことができる人物の名を挙げ、評議を行います。さて、義持の父、三代将軍足利義満と申さば、皆さまご存知のテレビアニメ『一休さん』に登場する将軍さまとしてもお馴染み、治世の後半には鹿苑寺金閣で政を執りおこなった室町幕府将軍でございましたが、室町幕府成立の流れより我が国が抱えた大なる懸念でございました南北朝問題に合一を果たすことで終止符を打ち、そして有力守護の力もおさえることで幕府権力を確立させる偉業を成し遂げた、まさに大器の将軍でございました。そして事ここに及んでは、幸いなことに子宝にも恵まれた義満、この時、義持には僧籍にある四人の弟がおりました。後継を選ぶ方法として義持の承諾も得た上で、神籤により選ばれたのは、青蓮院門跡であった義円、還俗し足利義宣となった、後の足利義教でございました。
ここで少し時を遡りまして、武家政権(武家独自政権)の始まりを思い起こしてみたく存じまする。幕府という形で、京の朝廷にやがて成り代わるほどの支配体制の基を創り出しましたのは、鎌倉幕府初代将軍、源頼朝でございました。その血筋は源氏二十一流の内、清和天皇から分かれた氏族が清和源氏でございますが、中でも第六皇子である貞純親王の子・経基王(臣籍降下し源経基)の子孫が軍事貴族化し、摂関家に仕えて勢力を拡大、その流れを汲み主流となる河内源氏が東国の武士団を支配下におくことで台頭した一族に辿りつきます。平治の乱以前は、まだ幼ささえのこる頃、東国に下向しそこで育った源義朝(頼朝、義経らの父)が、主要武士団をまとめ、時には在地豪族の争いに介入し、また時には在地豪族の娘を娶るなどしながら二十代の早いころには広く東国武士団を支配下におさめることに成功し、その力は中央で凋落の憂き目にあっていた源氏の力を盛り変えず基となり、且つ東国は義朝の存在が重しともなりまして平穏さの中にございました。さりながらやがて西国に基盤の中心を持つ平氏政権の世となり、院政の下で武士集団が、もはや欠くことのできないものとなった軍事警察権を軸として政権に参画していきます中で、これも無視しえない新興の力となっておりました地方武士団を政権の力としては取り込めないまま、東国武士団も複合的支配体制下におかれ、乱れていったのでございました。ただ必死に己の領地を守ることに力を尽くす数多の東国武士団、無論武士団にも領地の大小はございましたし、それはそのまま領主としての力の大小でございましたが、己が目で見ることのできる限り、とでも申しましょうか、あくまで何らそれを超えるまでのものではございませんでした。日々土にまみれ、時に守るべきものを守るために武力を使う、そんな土地に根差すつわものたちを、武家の棟梁という名目をもって、ひとつところに向かわせるだけの何が頼朝にあったのでございましょうか。頼朝が誰よりも豪傑であったのか、否。頼朝の血筋にそこまでの無理を武士たちにさせるまでのものがあったのか、否。頼朝が大規模な私兵や財力を持っていたのか、申すまでもなく否。それでは何か武士たち自身が待ち望んでいたものをもたらしたのか、これもある境を過ぎたところでは否、と言わざるを得ないかと思います。彼らは先祖伝来の土地を守り、そこで己の暮らしを守り続けていけることが望みであり、遙か彼方のその目に見えもしない何かまでを求めていたわけではなかったのであろうと思われるのでございます。
さりながら、日の本をその眼下に捉えるとしたならば、そこに力を及ぼすにはより大きな力が必要となりますし、たとえ目には見えぬところであれども、馬ですぐには行けずのところであっても、そこにも手をさし伸ばせるようでなければなりません。これは決して武家の棟梁に限られたことではありませぬが、広く世を見る目、成し遂げんとする固き決意と強き意思、そして、そのために周りを巻き込む声があって、初めて全国を治めるということが成し得るのでございましょうか。戦においては武に長じた者を、政においては仕組みを作り上げられる者を、そして裏方として仕組みの中で国を支え動かすことに長けた者たちを、上に立つ者として広く見たままに、強く思う意思のままに動かせる声なくしては、成り立たぬものではないかと思われます。頼朝は時にわがままなくらいであったとも伝わりますが、それはおそらく多くの者たちがまだ見ぬものを創らんとする中での強き意思が、時にそのように噴き出ためかもしれません。力でただ押し付けられているだけの者たちは、やがてその力が弱まれば跳ねのけようとするでしょう。過去の恩義を感じることはあっても、それにいつまでも応え続ける者は多くはないかと思われます。利害の合致で合力したものたちは、利害の合致がなくなれば去ってゆくでしょう。ただ、例え強く押し付けられた力であったとしても、その重石となるであろう声に幾許かの得心がゆく何かがあれば、武士たちをして目指す一つところに向かわせることができるのかもしれませぬ。
時は下り室町幕府三代、足利義満は如何な様でございましたでしょうか。非常に刻限に厳しいところのあった義満は、遅れた者を厳しく罰することしばしばであったとか。また、己や周り者たちの装束にも口うるさく、厳格な様子が伺われるところがございます。しかしながら、政においては、同じことでも相手の力の大小で敢えて処罰を分け、強き者に配慮をするといった独特の匙加減を見せるところもあれば、女人に関しては、他者の妻妾と通じることも頻繁であるなど、およそ厳格さとは程遠い側面もまた併せ持っていた様でございます。将軍といえば聖人君子とは言い難いところも元来あるものと思われまするが、引き締めるべきは引き締め、手綱をほどよく緩ませるところもありながら、周りが折り合いをつけていかざるをえないような中に巻き込み、義満が遠く見る大事を進めていくことのできる声を持っていたのではないかと思うのでございます。
次いで二十八年の長きにわたり室町幕府将軍であった義持は、四代将軍として、整いつつある仕組みの中で物事を円滑に進めていくことが求められ、そのためか温厚な将軍であったと思われている節もあるようでございますが、伝わるところによれば、癇癪持ちなところがあり、鎌倉府との対立に連なる諸々の中でも、管領からの報告を聞くやいなや激怒する場面も見せておりまする。最期の後継選定のことを除けば、寧ろ強い意思で事にあたっていたのではないかと覗い知れるところがございますが、文化人であり、また医療への深い関心も持ち、幕政を安定させ、世を豊かにするために強い意思をもって人々を導いていた様子が伺われまする。
示された道があり、やるべきことが定められていれば、人はそれに従う質もたしかにもちあわせているでしょう。それは、ある種楽な生き方でもあるからでございます。されど、唯々諾々とそれに従うだけではない者たちもいれば、歩みが遅れてくる者たちもいることでございましょう。それもまた人の性、そしてそれらを動かし続けることは並大抵の意思で続けられることではなく、そのために届かせる声には、強さや厳しさとともに、何らか得心させるものが重ねられておらねば、示された道の途上で、人は上に立つ者の意には則さない方へと向かい始めてしまうものなのかもしれませぬ。歴史を紐解くに、そのような例えは数知れず、でございます。
義持が亡くなると、籤引き将軍の時代へと突入いたしますが、さて六代様の政とは如何なるものであったのでございましょうか。次の回にてお伝えいたしたくぞんじます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

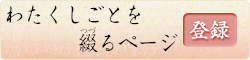

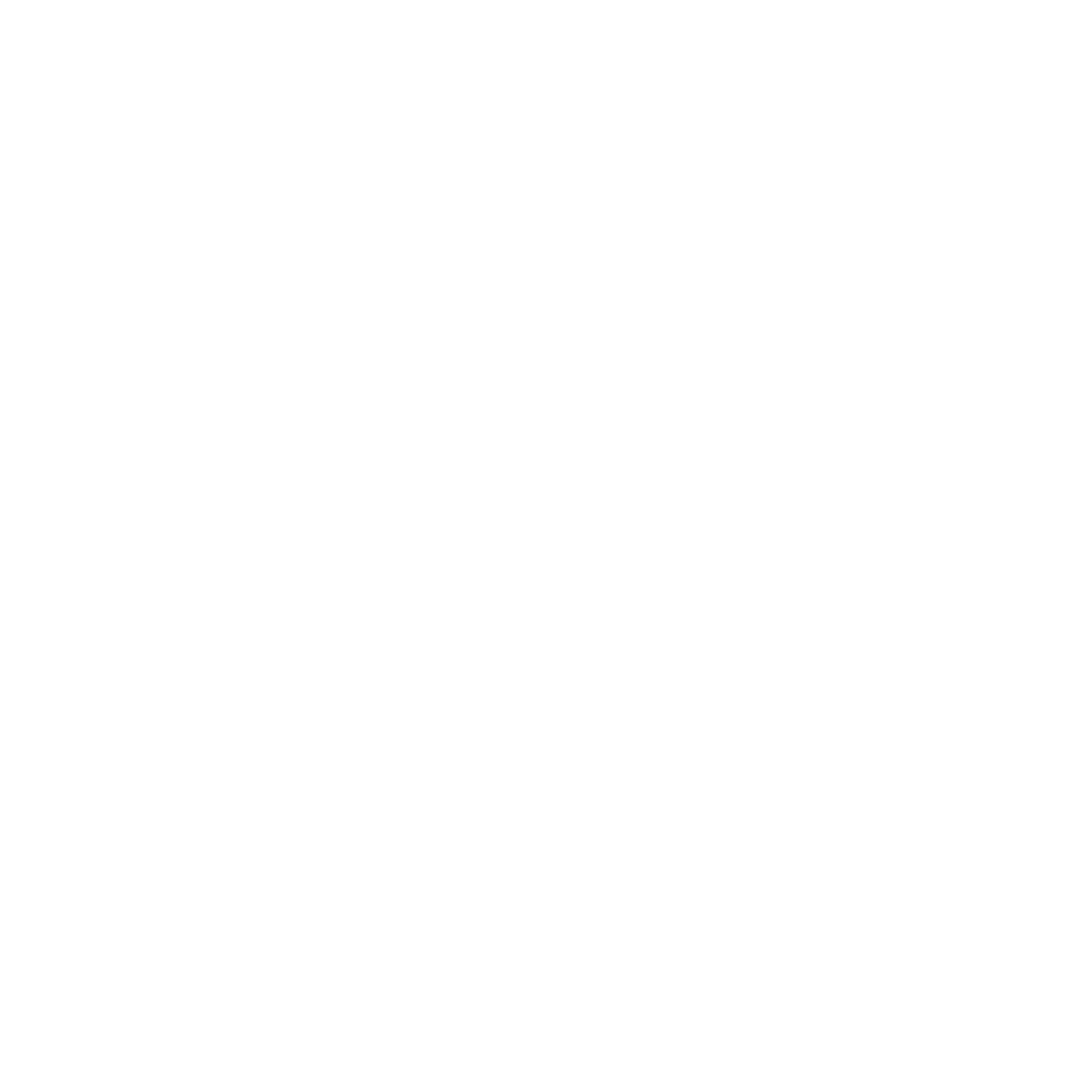 Twitter
Twitter
 Facebook
Facebook