こうして伊勢を固めた親房は、各地に散っている南朝方の有力武将たちとの関係強化に努めていくのでございます。南朝方主力であった新田義貞の一族や楠木正成の遺児・楠木正行、また吉野を本拠とする後村上天皇を奉じる公卿らとの間で書状を交わし、各地に散った南朝方の勢力を結びつけるために奔走したのでございまするが、人の心こそが世を導く柱となることを深く知る親房の思いが歩みを止めさせぬものとなったのでござりましょうか。
縦しんば数で勝ることができたとしても芯に柱なくば烏合の衆と何ら変わらぬもの。心の柱とも成り得るものなくしては、との強き思いから親房は延元四年(西暦1339年)には伊勢・阿坂城に籠り、『神皇正統記』の執筆を進めていくのでございました。守るべきは「帝の正しき統(すめらぎのすじ)」そこに記すところの皇統譜は、天照大神より始まり、代々の天皇がいかに国を守りて今日に至ったか、そして両統迭立の混乱の中にありて何故に大覚寺統、すなわち南朝こそが正統たるかを、魂を込めて説いたものでござりました。
同年、延元四年(西暦1339年)長月(9月)には、後醍醐天皇が吉野の地にて崩御、南朝はその精神的柱を失いながらも、如何にしても思いを伝えんと強く欲する親房の心は、その深い学識に支えられた強き思いの宿った文となり、伊勢に集った武士や社家のみならず、遠く吉野に籠る公卿らの心も励ますものとなり、「南朝の心の一本柱」となっていくのでございました。
後醍醐帝の崩御をうけて南朝を継ぐ形となった若き帝、後村上天皇(後醍醐帝皇子・義良親王)を支え、守り導くことを己が残る生をかけてなすべきことと定めた親房でございましたが、足利方の優勢たること明らかな中で、実に十余年にわたり南朝方が足利方に抗しえたのは心の柱を渡し得たが故であったと申せましょう。後村上天皇を守り支え導き、南朝の柱石となった北畠親房でしたが、正平十三年(西暦1358年)弥生、大和国賀名生行在所にて七十歳の生涯を終えるのでございました。後村上天皇、そして参集した公卿・武士ら皆誰もが深く喪に服し、「南朝の大黒柱、ここに倒る」と嘆いたと伝わっておりまする。
その生き様はまさに心と理の柱。それこそが南朝をまとめ、苦難の時をも乗り越えさせる力を人々に与えてきたのでございまする。魂の書、『神皇正統記』もまたその現れのひとつであり、後々の世にまで伝えられていく形を成したひとつであったのかもしれませぬ。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
南朝の志を武において、皇統を守護する力のあるべき姿というものを体現することは、北畠顕家という存在を中心としてはじめて成し得ていたと申しても過言ではございませぬ。政を司り、力の行使は武士に委ねてきた公卿たちは、武官に任じられてはいても武人には非ず、となり、また臣籍降下により武士となっていった者たちもそれぞれの土地で武士として生きる道は容易いものではなく、その土地にしっかりと根を下ろしていくより外はなかったのでございます。世が乱れる中、皇軍を皇軍たらしめ率いることが求められはしても、成し得るか否かの容易ならざるを誰よりもよく分かっていたのは、顕家の父、北畠親房であったやもしれませぬ。
南朝を遠く陸奥の地より、政を正しツワモノを糾合し支え続けた嫡男・顕家の存在は東西に広がる日ノ本全体の政を見据えた時にも大であり、余人を以て代えがたい鎮守府大将軍落命の報は、幾重にも親房を嘆きの淵へと追いやるものでございました。然れども陸奥から神速の強行軍で武門の集団たる足利方を幾度も蹴散らすほどの武威を見せた顕家率いる軍はもはやなく、南朝方は俄かに力を失い、足利尊氏の勢威は京畿一円を覆い尽くすほどでございました。南朝の諸将も疲弊し、もはや帝を支えるべき人々の心の中にも覆い得ぬ動揺と不安が広がっていくのを止める術すら尽きんとしている様相でございました。然りながら帝を奉じ、正統を繋がんとする南朝の灯を絶やすわけにはまいりませぬ。己までもがただ悲しみの中に身を措き、嫡男顕家がその若き命を賭してまで守り抜かんとしたものを如何で棄て措くことができようや、と伊勢の地に腰を据え南朝再興の基を築く決意を固めたのでございました。
伊勢国は、代々北畠氏の根拠地にして東国と畿内とを結ぶ要衝の地でございました。親房はまず後醍醐帝の勅命を携えて伊勢の豪族・地侍たちのもとを巡り、その心をひとつひとつ結び付けるべく働きかけていきました。北畠氏の家人である大河内氏や度会氏は無論のこと、伊勢国司や神宮の外宮・内宮の社家に至るまで、文字通り一人一人と真摯に向き合い、語り、説いていくことで南朝の足元の力を養っていったのでございます。
就中伊勢神宮の神職層からの支えは重きをなすものでございました。伊勢は「天照大神の御代」から続く皇統の象徴といえる地であり、伊勢神宮との結びつきはその神威を以て「南朝こそ正統である」と云わしめることにも等しき意をもつものであったためでございます。故にこそ親房は神宮の祭祀や年中行事に自ら参列し、朝廷と伊勢神宮の結びつきをここで改めて世に知らしめることで南朝の正統性を訴えたのでございます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
その年の弥生(3月)二日、権中納言へと任官した顕家は、軍勢を率い下旬までには関東から以北にかけての足利方を掃討すべく奥州へと軍を返しておりまする。帰途、相模国片瀬川で足利方の斯波家長が顕家の軍を妨げんとするも卯月(4月)には顕家勢がこれを撃破、次いで皐月(5月)には相馬氏を破り、奥州帰還を果たしてございます。尤も、この頃には九州に落ち延び、勢力を立て直した足利勢が軍を東進。播磨で赤松円心を攻めあぐねている新田義貞と兵庫で合流し足利勢を迎え撃つことを命じられた楠木正成は、既にして劣勢の中善戦するも、水軍を整えられなかった南朝方の不利さもあり、さらには新田勢とも分断され、打ち減らされながらもなお奮戦し足利勢を跳ね除けた後、ここが最期と正成らは自害いたしました。歴戦の武将であり、攪乱戦で相手を翻弄する手段を得意とし、洞察力に長けた、南朝を支えた名将のひとり、楠木正成を失ったことは、武家集団である足利方と違い、真に兵を率いて敵と渡り合えるだけの力量をもった将の少なかった後醍醐陣営にとっては代えようのない大きな損失でございました。顕家らの強行軍を以てして京を奪還、尊氏を九州まで落ち延びさせた折、帝は正成の『状況が宮方に有利な今のうちに足利方と和睦をする』という進言も容れず、また九州で勢力を盛り返した尊氏方の東進に際しての『京中で尊氏を迎え撃つべき』という進言も容れなかったのでございます。もし、帝や周りの公卿に少しでも状況を見極めることのできる誰かがいれば、或いは歴史は変わっていたやもしれませぬ。
京は再び足利方の手に落ち、帝は新田義貞とともに比叡山へと逃れたのでございます。
延元二年/建武四年(西暦1337年)睦月(1月)父・北畠親房より伊勢への来援を求める書状が、また時を同じくして後醍醐帝からは京奪還の綸旨が相次いで顕家の下に。
ただ、新たに移した陸奥国府である霊山城もまた足利方に囲まれており、顕家もおいそれと軍を進発させることができずにおりましたものの、葉月(8月)十一日、義良親王を奉じ霊山城を進発、上洛するために再び南下を開始する顕家の兵は、奥州五十四郡から招集され、その兵数実に十万余騎とも伝わる精鋭揃いでございました。
兵を進めるに際し、やはりどうしても再度陥としておかねばならぬのは鎌倉。先ず葉月(8月)十九日、白河関を越え下野に入る顕家軍は、伊達行朝、中村経長の両軍を中心に、師走(12月)八日には足利方であった小山城を陥落、小山朝郷を捕える。そのまま足利方の大軍を、師走(12月)十三日に利根川で、同十六日には安保原でそれぞれ破り、足利方であり、かつて楠木正成をもって『坂東一の弓取り』とまで言わしめたほどの武勇の持ち主、下野宇都宮家当主の宇都宮公綱を陣中に迎えることにも成功しておりまする。その勢いを駆って、神速で鎌倉に攻めかかった顕家率いる軍勢は師走(12月)二十三日、鎌倉に攻め寄せ、翌日には鎌倉の攻略を全きものとしたのでございました。この折、因縁浅からぬ斯波家長は討ち取られ、足利義詮・上杉憲顕・桃井直常・高重茂らは鎌倉を捨て房総へと逃げ落ちる始末でございました。
破竹の勢いを示す顕家の下には味方する者もまた参ずるもの。僅かの間に兵馬を整え、翌延元二年/建武四年(西暦1337年)睦月(1月)二日には鎌倉を進発、十二日には遠江国橋本、そして二十一日には尾張国に入り、翌日に黒田宿へと至る速さでの西進でございました。
対する足利方も守護らをかき集めた軍勢を組織し抗うも、睦月(1月)二十八日までには顕家率いる軍がこれを美濃国青野原の戦いで徹底的に打ち破り、一時は総大将の土岐頼遠の姿が見えず行方知れずの騒ぎとなるほどの大きな損害を足利方に与えたのでございました。しかしながらさすがに足利方の層も厚く、この戦いによる兵の減少や疲弊度合を鑑みた顕家は、そのまま京へと進むことをあきらめ、如月(2月)には一旦伊勢国に退く形をとっておりまする。
世の動きを見るに敏なのは生き残りをかける武家にとって理の当然でございまする。一族郎党を養うための領地を守る、その領地をまもってくれるのは誰なのか…、理想や官位では食い扶持にはならぬ、と誰もが世の実態を見据える中で、足利方には二の手、三の手を打てるだけの力の層と連携とがそなわり、兵站もまた然り、十重二十重に包み込んでいくような力が備わりつつある一方、如何に戦場での強さで譲らず、信念をつらぬいた戦いを続けていようとも、本拠地を遠く離れての連戦、堪えぬ筈がありませぬ。
その後の畿内における戦いでは、依然精強さを見せる顕家の軍ではございましたが、さすがに連戦連勝とはいかなくなり、援軍のあてもなきまま、苦しい戦いを続けざるを得ない状況となっていくのでございました。この戦いの中にあって、顕家は後醍醐帝に対し、皐月(5月)十日に東国経営の上奏文を草し、さらに同十五日には諫奏文を上奏しておりまする。
伝わるところによれば、
一. 地方分権を推進すること
二. 諸国の租税を免じ、倹約を専らにすること
三. 官爵の登用を慎重にし、能力には官位を、成果には恩賞を以て報いること
四. 月卿雲客僧侶等の朝恩を定め、公卿・殿上人・仏僧への恩恵を公平にすべきこと
五. 奢侈で衰退滅亡することなき様、臨時の行幸及び宴飲を閲かるべきこと
六. 法令を厳にせらるべきこと
七. 政道の益無く寓直の輩を除かるるべき事、即ち、貴賤に関わりなく能有るを用い、血筋だけで高位にあるを退けること
を切々と奏し、真摯に国を憂う心で帝を諫め、跋文も古今の例えを用いながら格調ある漢文にて帝に如何にしても想い届けんと、帝より与えられた大任と大恩を謝し、その上で帝自らが政の非を改め、世を正しく導いていかれることを願い、もしそれが叶わない時には、自らもまた官職を退き隠者となる旨、悲壮なまでの覚悟を以て奏しているものでございました。
和泉の国で戦線を繰り広げていた顕家でしたが、足利方からその討伐に向かうのは高師直。諫奏文の上奏から七日後、堺浦で激突となった両軍。顕家軍は残された力を振り絞り戦うも連戦の疲労に加え、足利方についた瀬戸内水軍の攻めもあり苦境に立たされ、ついには劣勢に回り全軍潰走となってしまうのでございました。
もはや供回り二〇〇騎を数えるほど。顕家は最後まで戦い続け幾多の敵兵を討ち果たしますが、落馬し、ついには討ち取られるのでございました。享年二十一。文に武に秀で、そして何より人を思い、心を掴む将器をもった若武者の、早すぎる、そしてまた清らかとさえいえる最期でございました。南朝の希望を一身に背負った北畠顕家。その生は短くとも、果てしなく高き志を以て世を変えんと奔り続けた生き方は、一筋の馬尾雲のようにはっきりとした軌跡となり、人々の心に刻まれるものでございました。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
帝の熱意、想いだけでは上手く回らぬのが政というもの、混乱を極めた建武新政は人々の反発を招き、やがて信濃国で北条高時が遺児、北条時行を擁した北条氏残党が反旗を翻すことを許してしまうことにもつながるのでございました。世にいう中先代の乱でございます。
勢いに乗った北条方は、足利直義の防ぎを崩し鎌倉入りをはたします。鎌倉を逃れた直義を救うべく鎌倉へと兵を進めようとする尊氏は、この時、後醍醐天皇に征夷大将軍への補任を奏請するも認められず、勅許なきまま葉月(8月)の二日に軍を発し直義の残兵と合流、北条時行の軍を破り、その月の十九日には鎌倉を回復するのでございました。
朝廷の令外官の一つである征夷大将軍はいわば武家にとって至高の栄誉、ただそれにとどまらず、この時すでに鎌倉時代を通して征夷大将軍が武家の棟梁として武家を統合し、幕府政治を行うという先例ができてしまっておりました。天皇親政を政の基軸に考える後醍醐帝としては、後に火種となりかねない征夷大将軍補任をおいそれと行うこともできない理があったのでございましょう。
半ばやむなく、追って尊氏を征東将軍へと補する後醍醐帝でございましたが、中先代の乱の事後もろもろ、また関東の守りを固めておきたいということからも京には戻らぬ尊氏。就中、乱の鎮圧に付き従った武家各々への恩賞分配を自己差配で行い、上洛の命にも従わずとなりましては、尊氏の建武新政離反と見做さざるをえず、建武二年(西暦1335年)霜月(11月)の八日、帝は新田義貞に尊氏追討を命ずるのでございました。ところが、錦の御旗を賜った義貞の旗色芳しくなく、ついには箱根・竹ノ下の戦いで足利方に敗退、師走(12月)十三日には総崩れとなるのでございました。軍団として見た時には如何にしても位や指揮系統で複雑さが目についてしまう南朝方の構成、加えて鎌倉を東西から挟撃せんとするならば、並々ならぬ統率力、政治力もまた求められるところ、荷が勝ちすぎるところがあったのやもしれませぬ。
そのまま尊氏は義貞勢を追撃し、まさに京へと迫らんばかりの勢いでございましたが、一方で、帝の命に応じて奥州から進発、尊氏軍を追って上京せんと騎馬軍を率いるのが鎮守府将軍・北畠顕家でございました。戦の成り行きを後から見据えるにやはり全体の統率をとることができず、ということに端を発すると思われる新田義貞軍総崩れの九日後、師走(12月)二十二日、義良親王を奉じ奥州兵五万は進撃を開始したのでございました。
一度進撃を始めた顕家率いる奥州軍は、すぐさまその凄まじきまでの力を見せることになるのでございます。翌建武三年(西暦1336年)睦月(1月)の二日には鎌倉に到達、足利義詮・桃井直常の軍勢を破り、鎌倉を攻略するという神速、猛襲ぶり。まさに顕家が陸奥下向以来、精強な奥州の兵をさらに鍛え上げ、一つにまとめ上げ、備えてきたことの現れでございました。翌三日には、足利方である常陸の佐竹貞義が顕家追撃に進発したことを受け、顕家は鎌倉を出て進撃を再開。睦月(1月)の六日には遠江に到り、十二日には近江国愛知川にまで到達いたしますが、敵地を一日に凡そ十里(約40km)を進み続け、百五十里(約600km)もの行程を半月ほどで進撃し続けたこととなり、日ノ本の歴史の中でも群を抜いた強行軍でございました。
如何に鍛え上げられ精強を誇る顕家の軍とはいえ、その強行軍は並々ならぬものであり、一重に後醍醐帝の想いに応え、世を導かんとする強い信念によって支えられてきたもの。後、顕家の軍は琵琶湖を一日かけて渡り、翌十三日には近江坂本で新田義貞・楠木正成と合流、顕家は彼らと軍議を開いたのでございます。そして、顕家は坂本の行宮に伺候し、後醍醐帝に謁見したと伝えられておりまする。
睦月(1月)十六日、顕家と義貞の軍勢は近江の園城寺を攻め、足利方の軍勢(細川定禅)を破り、これを敗走せしめ、次いで高師直と関山で合戦に及ぶ。相次ぐ戦いで足利方を打ち破り、睦月(1月)二十七から三十日の戦いにて新田義貞・楠木正成とともに尊氏を破り、京から足利勢を退けたのでござりまする。
休む暇なく、如月(2月)の四日には北畠顕家は新田義貞とともに尊氏・直義を追討すべく京を発ち、如月(2月)十日から十一日にかけ、京に再度攻め入る構えを見せる尊氏を摂津国豊島河原で破り、尊氏は九州へと落ち延びていくのでございました。顕家は義貞とともに足利軍の追撃掃討戦のため転戦し、如月(2月)十四日、京へと凱旋したのでございました。
和漢の学をもって代々仕えた北畠氏にあって、学識は無論のこと、正しき義を重んじ、武を尊ぶ顕家の姿は、真っ直ぐな陸奥のツワモノたちの心を掴みました。そして北畠顕家という若武者の真摯さが、陸奥の地を後醍醐帝が志す天皇親政の世を支える大きな力へとまとめ育むことを助けたのでございましょう。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
さて、早い叙爵など優遇されてきた北畠氏でございますが、文保二年(西暦1318年)弥生(3月)生まれの親房が嫡男顕家もその例にもれず、元応三年(西暦1321年)睦月(1月)、齢三つで叙爵、幼年にて様々な官職につき、それこそ先例のない数え十四(満十二歳歳)にて参議に任じられ公卿に登るほどでございました。(従三位参議・左近衛中将)これには家格もさることながら、少なからず先を嘱望されてのこともまた有り、と推し量られるところでございますが、背中合わせに、政をその軸となりて支え得る人がまだまだ足りぬ、ということもまた然りと申せましょうか。さかのぼること二年、元弘元年(西暦1331年)弥生(3月)には、後醍醐帝の北山第(この時は西園寺公宗の山荘)行幸の際、顕家もこれに供し、御前で、眉目秀麗な北斉の皇族武将高長恭に扮して「陵王」を舞ったと伝わります。この折には帝も笛を吹き、前関白・二条道平が舞い終えた顕家に、自らの紅梅の上着、二藍の衣を褒美として与えたことも伝えられております。折に触れ、後醍醐帝からも信をよせられること重なり、陸奥へ皇子を下向させる際に頼みとするならば、との思いへとつながっていったのでございましょうか。
元弘三年/正慶二年(西暦1333年)皐月(5月)鎌倉幕府を滅ぼし、建武の新政を支える立場となっていた北畠顕家は、同年葉月(8月)従三位陸奥守を任じられます。先例なき若さで公卿に列した翌年のことでございました。そして陸奥守北畠顕家らに奉じられて陸奥国国府兼鎮守府である多賀城へと向かった義良親王(親王となるのは翌年の建武元年)はこの時齢五、奥羽地方の武家を南朝方する大役は、必然顕家の双肩にかかるところ大というものでござりました。
京を遠く離れ、理もまた異にするところ少なからずの中にあって南朝の旗印たる義良親王を導き育て、北条方残党を追い、豪族らが割拠し争いも絶えぬ陸奥の力を南朝方へとまとめ上げることが容易ならざるのは、想像に難くなきこと。幼き頃より先達の薫陶を受け、正しき義を重んじ、家門の誇りを胸に刻みたる顕家の力量が試される時でございました。されど良き馬産地であり、屈強で知られる兵馬を養う彼の地の武士たちを味方につけるということは、即ち政を正しくし、また軍においても認めさせるものなくしては、成し得るものではござりませんでした。代々和漢の学をもって朝廷に仕えてきた北畠氏は、政においてその知見を活かせる場を多く得てまいりましたが、若き顕家は武においても秀でたものを持ち、その一筋なる信念と調和を求める心根、そしてそれに支えられた武人としての姿は、時を経て陸奥の地に生きる多くの武士らの心を得、南朝方の大きな力を築いていったのでございます。
顕家は着任から一年をかぞえない建武元年(西暦1334年)葉月(8月)には津軽における北条氏残党の追討を開始、その年の霜月(11月)半ば過ぎにはこれを滅ぼし、津軽平定を成し遂げており、その戦機の掴み方、拙速で無駄のない戦ぶりは敵味方を畏怖せしめるものであったと語り継がれておりまする。
建武二年(西暦1335年)霜月(11月)には鎮守府将軍に任じられ陸奥将軍府の体制をより強固なものへと作り上げていきました。建武の新政における新たな地方統治機関となる陸奥将軍府が管轄するのは陸奥、出羽、下野、上野、常陸の五カ国であり、顕家には帝から強大な権限を与えられ、統治を進め易い様慮かられておりました。鎮守府将軍となる頃には、奥州の有力地頭であった南部政長や、結城宗広・伊達行朝らの勢力を糾合し、奥羽地方における軍事的な力も大きなものとなっておりました。ただ、鎌倉幕府を滅亡させた際、後醍醐帝から勲功第一とされ先に鎮守府将軍に任じられ、且つ奥州の北条氏旧領地頭職なども与えられ、奥州での勢力拡大をしていた足利尊氏としては、警戒感を拭い去れるものではなく、有力一門である斯波氏の当主斯波高経が嫡男、斯波家長を抑えとして配しておりまする。建武の新政において、陸奥国府を中心に奥羽から北関東の勢力を南朝方へ、という帝の目論見は、北畠顕家という若木の力により形作られてきておりましたものの、時はそのままひとつところへと流れてはくれぬ様相を呈し始めておりました。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
天皇親政を理想とし、実に二百五十年ぶりに政がその形へと回帰を見るに至り、後醍醐帝の思いがその政の持続へと向けられていくのは、元より定められていた流れなのかもしれませぬ。たとえ天皇親政ではないにしても、時は皇位継承者を持明院統と大覚寺統から交互に立てる決まりとなっておりました両統迭立の定めが続く世、後醍醐帝は実子に譲位し、そのまま上皇として院政を敷き治天の君となる、ということすらも立ち行きませぬ。己が理想とする政を、と願う帝の思いは憂いとなり、やがては両統迭立という縛りをもたらしている鎌倉幕府を倒す、ということにつながっていくのでございました。
長きに亘り北条得宗家が執権として権勢をふるう鎌倉幕府では、もはや憚る様すら見せぬ北条一門への偏重に加え、重なる負担や情勢不安は幕府をして多くの御家人からの支えを失わせるに十分なものでございました。
事の流れは様々伝えられておりまするが、倒幕の挙兵は、優勢であった鎌倉幕府側により一時鎮められたかに見えたものの、後醍醐帝の挙兵に呼応した楠木正成が河内国千早城にて幕府の大軍を翻弄し続ける戦ぶりは幕府側に厭戦の気運を生じさせ、倒幕の機運を熟させるものとなったのでございました。そして後醍醐帝の皇子の中でも武の人として知られる護良親王が再び挙兵、流刑地を脱した後醍醐帝の綸旨と、護良親王の令旨とが日の本に広く発せられたことは倒幕の気運を大いに高め、幕府方で北条得宗家と代々縁戚関係を結んできた武家源氏の名門、足利氏の当主・足利高氏(のちの足利尊氏)の幕府離反が転機となり、鎌倉からの討伐軍と京・六波羅探題は壊滅にいたりましてございます。さらに、関東で御家人新田義貞らが倒幕に応じ、北条得宗家を倒し、鎌倉幕府による支配を終わらせた後醍醐帝は、理想とする建武の新政を開くのでございました。時、元弘三年/正慶二年(西暦1333年)文月(7月)のことでございまする。
この時、出家し政の世界から身を引いていた北畠親房は、鎌倉幕府倒幕の動きにも関わっておらず、と伝わっておりまする。後宇多院政より朝廷の中枢に身を置いてきた齢三十八の親房には、この大きな時代の移り変わり、どのように映っていたのでございましょうか。
鎌倉幕府を倒し、理想とした天皇親政に邁進する帝でありましたが、還俗し自ら兵を率い転戦を続け、武の側面で父帝を支え続けた護良親王は、本来あれば勲功第一とされてもよい働き―建武の新政において征夷大将軍に任じられこそしましたものの、やがて自らに権力を集中させようとする父帝後醍醐の思惑、巧みに帝の信頼を得ていく足利尊氏との対立、そして実子に皇位を継がせたい後醍醐帝の寵后、阿野廉子の働きかけなどに翻弄され、父帝後醍醐との溝は深まるばかり、建武二年(西暦1334年)霜月(11月)には、鎌倉に流罪とされてしまうのでございました。
さて、建武の新政が始まり、一たびは隠棲しておりました北畠親房も再び政に参画いたします。ただ、親房はこの時すでに帝との溝が深まる護良親王派であったこともあり、政の中心とは少しばかり遠い立場であったとされておりまする。やがて東国武士の帰属、陸奥の支配を手堅くせんと欲する帝は、親房の嫡男、北畠顕家を従三位陸奥守に任じ、第七皇子義良親王を奉じて陸奥国多賀城へと下向させるのでございますが、この折、親房も共に陸奥へと随行するのでございました。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
親房もまた北畠氏の例にもれず、正応六年(西暦1293年)水無月(6月)の末、まだ生後半年ながら叙爵、従五位下の位に列せられ、長じて朝廷の政を執り行う側のひとりと定められたのでございます。律令制における官職と位階において位に当たる位階は、正一位から少初位下まで三十あり、一位から三位までは正と従が、四位から八位までは正、従に加えて上と下がございましたが、五位より上の位階がいわゆる貴族となり、家格によりてそこが序となるもの、そこまでは進めぬものとが厳然と隔てられておりました。やがて延慶元年(西暦1308年)霜月(11月)、親房は非参議従三位として公卿(太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣・大納言・中納言・参議ら議政官。時代により異なるが、律令制における最高国家機関たる太政官において朝政に参画する高官、およびその任官資格を有するもの)に列せられ、延慶三年(西暦1310年)師走(12月)には参議に任じられたのでございます。時の帝は第九十五代となる花園天皇、伏見上皇を治天の君とする伏見院政の時代でございました。
伏見院政はその後、上皇出家に伴い花園帝の異母兄にあたる後伏見上皇(第九十三代・後伏見天皇)へと引き継がれ、正和二年(西暦1313年)から文保二年(西暦1318年)の間、後伏見院政の時代となっていくのでございます。文保二年(西暦1318年)如月(2月)、譲位により後宇多上皇(第九十一代・後宇多天皇)の第二皇子、尊治親王が践祚、第九十六代天皇に即位したのでございました。後に南北朝時代を迎え、南朝初代天皇としても知られる後醍醐天皇の時のはじまりでごさいます。尤も、これまでのように後宇多院政が敷かれ、即位から三年間、元亨元年(西暦1321年)治天の君たる後宇多上皇が隠居するまでは院政がつづきまするが、後宇多上皇が治天の君の座を退かれた後、後醍醐帝による親政が始まるのでございます。齢三十を過ぎての即位が実に二百五十年ぶりのことではありましたが、それだけではなく他にも様々伝えられてはおりまする諸々、是非は兎も角としても、ここに天皇親政が行われることとなったのでございました。
さて、後宇多上皇に仕え、その信任も厚かった親房は参議に任じられた後も要職に任じられ、益々頭角を現し、後宇多院政から続く後醍醐親政においても、必然重きを成して行ったのでございました。その信任の厚きこと、後醍醐帝の第二皇子にして、その聡明さから父帝後醍醐も行く末を期し、目をかけていた世良親王の乳父をゆだねられたことからもうかがい知ることができましょう。
こうして朝廷において重きをなす親房でしたが、はやり病の多かった元徳二年(西暦1330年)、病の床にあった世良親王は、持ち直すことなく儚くも薨去、病の重さゆえ遺言を書き記す力も残されていなかった親王は、最期に親房に遺命を託したとつたえられております。定かには判りえぬところではございますが、世良親王の宝算、二十くらいではと考えられておりまする。
親王の薨去を嘆き、親房は出家、政の世界からも身を引くのでございました。元徳二年(西暦1330年)、親房、齢三十八のことでございました。
世が大きく乱れ、討幕の動きがやがて鎌倉幕府を倒すほどのものとなりまする、世にいう『元弘の乱』に一連する戦の端緒となる笠置山・下赤坂城の戦いは、翌元徳三年(西暦1331年)長月(9月)のことながら、それを然と描けているものなど、未だ誰もおりませんでした。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
飛鳥時代の終わりごろよりはじまりました中央集権国家の実現への取り組みの中、国を統べるあり方を律令制へとうつしていく朝廷は、やがて諸国をその持てる力毎に、大国、上国、中国、下国の四つの段階に分けることをいたしました。平安時代中期、延喜式が策定されました折には、次に挙げまする十三の国が、最も上位である大国とされておりました。
大和国
河内国
伊勢国
武蔵国
上総国
下総国
常陸国
近江国
上野国
陸奥国
越前国
播磨国
肥後国
その内、上総、常陸、上野の三国は親王任国、すなわち親王が国司に任じられる様定められた国であり、大国の中でも格別のものでございました。尤も、親王が国司として下向して治めることはせぬ遥任でありましたことから、これら親王任国では、次官である介が事実上の長として統治にあたりました。
時が下り、朝廷が任ずる国司の職が有名無実のものとなっても、上総守や上野守に任じられる武士はおらず、上総介や上野介に限られていのはこのためでございます。
その大国のひとつ、伊勢国に南北朝時代より勢力を保ち戦国時代まで主であり続けたのが北畠氏でございます。
村上源氏の流れを汲む北畠氏は、村上源氏宗家である久我家から鎌倉初期に分かれた中院家の家祖、中院通方の次子、雅家が洛北にある北畠(今の京都御苑の北辺り)に移り住み、北畠を称したことにはじまりまする。和漢の学をもって代々仕えた北畠氏は、二歳、三歳、あるいはさらに早く叙爵するなど厚く遇されておりましたが、天皇から見て私的に近しい臣下であったことによると考えられております。
後嵯峨天皇以降、大覚寺統との関係が深かった北畠家でございますが、鎌倉時代終わり頃の当主、
北畠 親房は、文永九年(西暦1272年) 後嵯峨上皇が崩御、後継を定めぬままにただ次代の治天の君は鎌倉幕府の意向に添うように、との遺志だけが示されたことにはじまる両統迭立の混乱を経て、南北朝時代、後醍醐天皇(大覚寺統/第九十六代の治天の君にして、南朝初代の帝)の建武の新政を中心的な立場として支えるひとりとなり、そしてその血筋は伊勢北畠氏の基へと続いていくことになるのでございます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
一条房基が命を絶つ天文十八年から遡ること六年、天文十二年(西暦1543年)、房基の嫡男として、一条兼定は土佐国幡多郡中村に生を受けたのでございます。
室町の幕府は十二代将軍、足利義晴の時代、ただ依然勢力争いが絶えず、もはや幕府権威の象徴として担がれ、時に畿内を転々とせざるをえない存在となってしまいました将軍家にもはや全国を統べる力はなく、戦乱の世の様相は日の本全てにおいてより深まるばかりでございました。折しも、種子島に鉄砲が伝来したのもこの年のことでございます。
そのように乱れた世にあって、土佐一条家の四代目当主となるべくして生まれた兼定。父房基が突如命を絶ち、兼定には土佐中村の地で悠揚と幼年期を過ごしながら当主としての在り方を学ぶこと、時勢が許さぬものでした。
天文十八年(西暦1549年)卯月(4月)、齢七で家督を継ぎました兼定は、大叔父にあたる一条房通(土佐一条家二代当主・房冬の弟)の猶子となり上洛したのでございます。
応仁の乱に際し家領である土佐国幡多荘に下向した一条教房の実弟で、教房の土佐在国に伴い兄、教房の養嗣子となって家督を継いだ一条冬良に子が無かったことから、冬良が兄、教房の孫にあたる房通を婿養子にして家督を継がせており、天文十六年(西暦1547年)には房通は関白となっておりました。土佐一条家の重臣等としても、事ここに至っては京の一条宗家の力を恃みとするよりほかなし、という思いあってのこととは想像に難くないところではございますが、それより遡り、まだ房基存命の折から、土佐一条家の若年当主を支えるべく、房通は天文十二年頃には土佐に下向し、一時当主に代わり政務を執っていたと伝えられており、房通を恃みとするのは当時の関係性からもごく自然なことであった様でござりまする。
京の房通の下で暮らす間に兼定が多くに触れたであろうとは思われながらも、未だ幼年であり、且つまたその身は土佐一条家の家督、おそらくは京での政争の有様などとはやはり縁遠い時の中で、兼定の人となりは形づくられたのかもしれませぬ。弘治二年(西暦1556年)房通薨去の後に元服、房通の跡を継いだ一条兼冬より偏諱を受け、一条兼定と名乗ることとなったのでございます。そして同年、若しくは翌弘治三年にかけて土佐中村に下向、いよいよ土佐一条家当主として政に向き合う時を迎えるのでございました。
長く土佐七雄の盟主という形で土佐中村の地より周辺をまとめてきた土佐一条氏でございましたが、相次ぐ当主の交代、それに続き幼少の当主が京に在ることで当主在国すらあらぬことは、たとえ平時であったとしても土佐一条氏の求心力を下げる基となったことでございましょう。況や世は乱れ、何れもが折あらばと己が勢力を伸ばす機会を虎視眈々と窺う中、勢力図が描きかえられることにさほど長い時を要するものではございませんでした。
かつて土佐七雄の中で没落し、居城の土佐岡豊城をも追われた長宗我部氏。一条房家の保護と扶けを得て長宗我部家の再興を果たした長宗我部国親は勢力を拡張、永禄三年(西暦1560年)に没すも、跡を継いだ元親は父国親の遺志を継ぎ巧みな結びつきと戦とでやがて他の六雄を従えるほどになるのでございます。
一方、土佐中村に在る兼定は、永禄元年(西暦1558年)伊予大洲城を本拠とする宇都宮豊綱の娘を娶るも、永禄七年(西暦1564年)には離別、豊後の大友義鎮の長女を娶り大友氏と結ぶなど外交を展げておりました。なれど兵を出せども捗々しい拡がりがないばかりか敗退を重ね、また京の一条宗家とも疎遠となっていくなど、次第に勢いを削がれていく土佐一条家でございました。
勢いを増す長宗我部家の侵食は止められず、何ら打開策も見いだせずにいる中、兼定は一門でもあり、家中筆頭格として家臣をまとめる知勇兼備の土居宗珊とその一族を断罪してしまうのでございました。したがこれは長宗我部側の策略によるものともされており、あろうことか兼定は無実の罪で家中の大きな力を自ら切り捨ててしまったばかりか、その行いにより家中の信望をも失っていくのでございます。元亀三年(西暦1572年)のことでございました。
翌年、天正元年(西暦1573年)長月(9月)には、残る三家老ら重臣により隠居を強いられ、天正二年(西暦1574年)如月(2月)には中村御所を出て、岳父である豊後の大友宗麟を頼っていったのでございました。尤もこれは、もとより土佐一条家中だけで謀られたことではなく、長宗我部元親と、京から下向していた一条宗家当主、一条内基との間での遣り取りを経て一条内基の諾意があり、進められたことと考えられておりまする。
土佐一条家は、内基が兼定の嫡子元服を執り行い、偏諱を与えた一条内政に継がせておりますものの、既にして実はなく、傀儡となったものでございました。
さて、キリシタン大名としても知られる大友宗麟の下へ身を寄せていた兼定は、豊後の地で洗礼を受け、キリシタンとなったのでございます。洗礼名ドン・パウロ。兼定なりの純真な思いがあってのことでございましょうか、幡多郡の奪回とあわせて、キリスト教宣布をも目指して動き始めた兼定は、幡多郡の宿毛あたりにキリスト教を伝える拠点を築くことも命じていたといわれておりまする。
こうして一度は追われたものの、天正三年(西暦1575年)兼定は再起を計り大友氏の扶けを借りて土佐へと兵を進めるも、四万十川の戦い(渡川の合戦)で大敗、敗走、土佐国は長宗我部家により統一されたのでございました。
その後、兼定は宇和海の戸島に隠棲いたしますが、再起を計りながらも、成し得なかったということが事実と言い得るかと思います。火種を残したくない元親は一計を案じ、かつて兼定の側近であった入江左近を刺客として兼定のもとに差し向けたのでございます。深手を負いながらも何とか一命を保つことができたのは、兼定にとってはむしろ幸いであったのかもしれませぬ。伝わるところによれば、深手を負い、不具の身となってしまった兼定は、豊後から送られて来るキリスト教の書物に親しみ、慰められ、深く信仰に生きる余生を過ごしたそうでございます。天正九年(西暦1581年)に兼定を見舞ったイエズス会司祭アレッサンドロ・ヴァリニャーノも兼定の深い信仰心と信仰生活を感嘆とともに伝えております。
深い傷を負い、身も不自由になりながらも、信仰に満ち溢れた時を過ごした兼定は、天正一三年(西暦1585年)七月一日、齢四三歳で天に召されたのでございます。
家柄や立場に縛られ、好むと好まざるとに関わらず果たすべき役割を決められてしまう時代、社会において一条家に生を受けた兼定には、違う何かを選び取るということは許されぬものでございました。晩年、信仰の中に身を置いた兼定が、最も自身が自身でいられた時であったのかもしれませぬ。戦乱の世であっても、もし文芸や技芸を家技、家職とする家に生まれていたら、嫡流の重責を背負わされることのない立場であったならば、あるいは歴史に刻まれたものとは異なる、兼定らしさが存分に現れる生き方というものに出逢えていたのやもしれませぬ。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら
大永二年(西暦1522年)一条房冬の嫡男として誕生した一条房基。享禄三年(西暦1530年)にわずか齢九つで従五位下に叙爵、そして享禄五年(西暦1532年)には右近衛中将に任官と、まだ幼き頃より官位を進めていったのでございました。中央とのつながりも重んじ、外交に長けた父、房冬の働きかけによるものであったと、想像に難くないことではございますが、その後も位階を進め、天文九年(西暦1540年)には、従三位に叙せられ公卿に列することとなるのでございました。官は既に就いておりました右近衛中将でしたので、一条三位中将となったのでございまする。
翌天文十年(西暦1541年)には阿波権守の官も兼ねることになりますが、その年の霜月(11月)には父、房冬が薨去、房基は若くして土佐一条家の家督を継ぐこととなるのでございました。
土佐一条家は、初代房家亡き後、わずか二年で二代房冬が世を去り、その結果まだ若い房基が三代目を継いだばかりでは、家中も必ずしも静穏ではなかったかもしれず、また乱れ乱される隙もどうしても目につきやすい時期ではなかったかと考えられます。しかしながら、房基はよく家中をまとめ、土佐東部や南伊予へ兵を進めております。尤も、結果的に一条家の勢力圏を拡げることにつながったとは雖も、降りかかる火の粉を払いのけるためであったり、縁戚関係にある豊後大友家の求めに応じての出兵であったりと、此方から仕掛ける類の戦ではなかったのでございまする。当主が相次いで代わることを余儀なくされた土佐一条家でしたが、これまでに打ってきた布石は功を奏し、房基の動きを扶けることにもつながったのでございます。
よく家中をまとめあげ、兵を動かし、土佐一条家の勢力圏拡大に努めるなど武に優れた観のある房基でしたが、摂関一条家当主であり、叔父にあたる一条房通に一条家秘蔵の有職故実書である『桃華蘂葉』の写本手配を願い、また、初代房家が三条西実隆に書写を願い出て土佐一条家に伝わった『伊勢物語天福本』の奥書に房基の花押があり、親しく触れていたことも伺い知られ、文芸にもまた親しむ、文武に秀でた当主であったことが伺い知れまする。
こうして房基の治世が続き、勢いを増すやに思われた土佐一条家。なれどそれが続くことはなく、天文十八年(西暦1549年)房基は突如として自ら命を絶ったと伝えられております。享年二十八、その真偽のほどは杳として知れず。世は戦乱の時、桜の花見頃を過ぎようという頃でございましょうか、土佐一条家を率いる若き当主が世を去り、混乱の足音が聞こえてくることを否とは言い切れぬ、卯月の土佐中村でございました。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

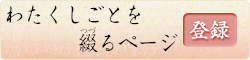
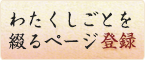



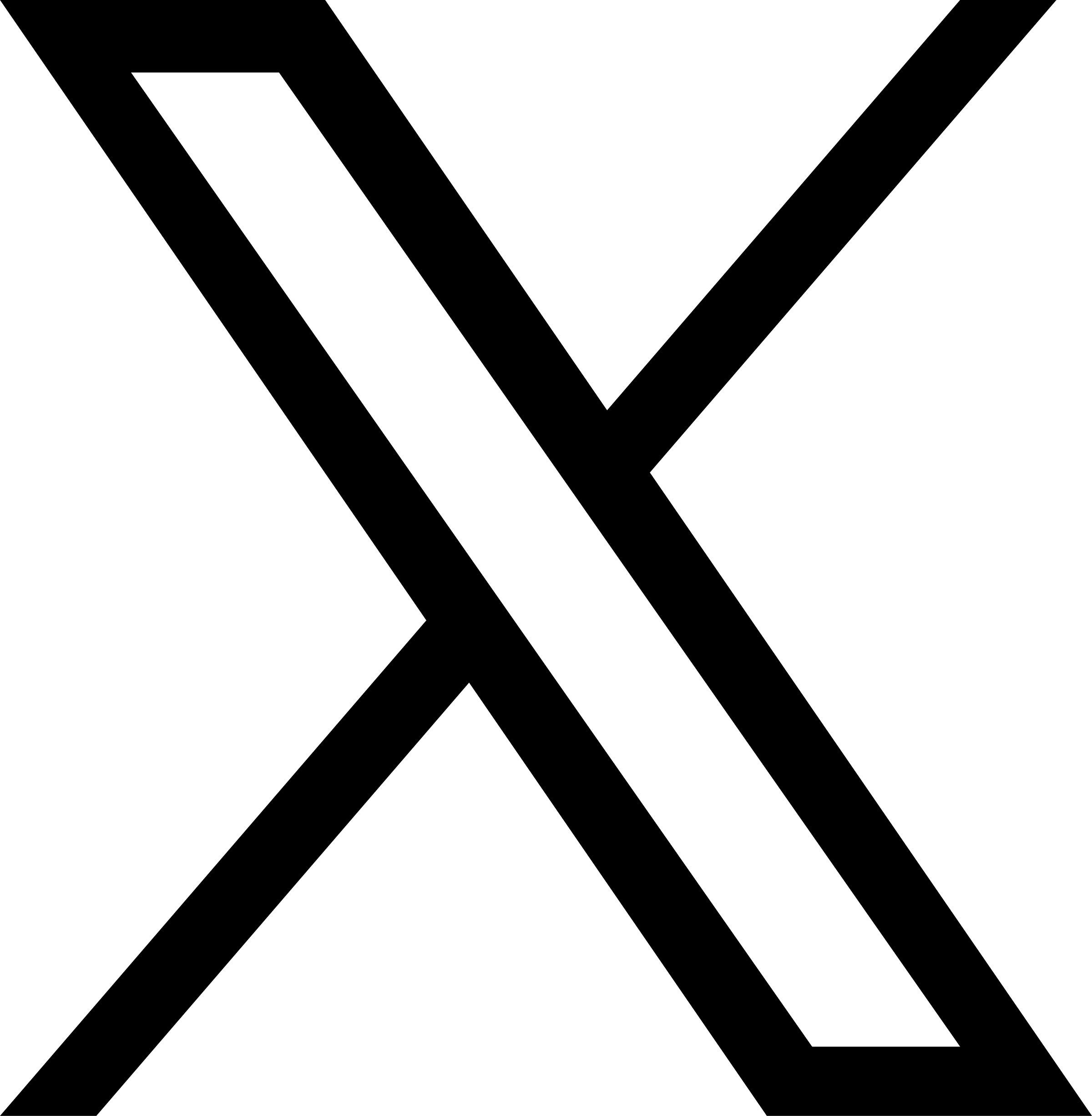
 Facebook
Facebook