日本の伝統宗教と聞いて、どのような風景を思い起こすでしょう。神社や寺院のひとコマでしょうか。神社は日本人としての歩みを神話時代から伝えますし、寺院は日本人の歩み方を教えてくれる存在とも言えます。言うまでもなく神社は神道であり、古代の自然崇拝から連なる神祇信仰(じんぎしんこう)が元になっています。寺院は仏教であり、インドから中国・朝鮮半島を経て六世紀には日本に伝わりました。そして、実はキリスト教も十六世紀には伝わりますので、紆余曲折あったものの、日本では四百年ほどの歴史があります。
とは言いましても、宗教のなかに日本をイメージしやすいのは、やはり神社と寺院になりましょう。神社と寺院というものは、今でこそ別々の宗教団体として法律上は存在していますが、長い歴史のなかでは、ほぼ同体のように併存していた時期が短くありません。神社は神祇信仰から発展し、インドからの仏教のほか、中国の儒教や道教の影響も受けつつ、今のような形態になっています。起源となると太古の昔になるのでしょうが、神社として整ったのは、たとえば伊勢神宮でも五世紀頃ではないかと言われます。
自然崇拝が元になっていますので、当然、日本の自然すべてが神さまです。社殿は寺院建築の影響とも言われますので、むしろ自然のすべてが神社であるとも言えるでしょう。八百万の神々と言われるように、たくさんの神さまがいらっしゃいます。一方、仏教にもたくさんの仏さまがいらっしゃいます。八万四千の法門と言いまして、たくさんの人々がいるから、そのひとりひとりに対してたくさんの教えがあります。たくさんの人々がいるから、それぞれを救うため、それぞれに対してたくさんの仏さまが現れてくださっているのです。
六世紀頃、仏教の受け入れにはひと悶着ありましたが、信仰としてのみならず、その整理された教義が学問としても重用され、次第に定着していきました。既存の神社とはどのように折り合いをつけたかと言えば、そここそ知恵の出しどころであったのです。日本の神さまが仏教を信仰するという設定で、神社と寺院が併存することが可能となりました。そしてさらに一歩進めて、そもそも神さまという存在は、仏さまが日本人のためにその姿を借りて現れ出てくださった存在なのだという、いわゆる本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)により、ほぼ同体となっていきました。
これとは逆に、神さまこそが、仏さまの姿となり仏教を説かれたのだという、見方を逆にした考えも出てきましが、いずれにしても神さまと仏さまは合わさりまして、これを神仏習合(しんぶつしゅうごう)と言います。明治時代になって、明治政府は強制的に神社と寺院を分けましたが、今でも神社と寺院が隣同士にあるところもあります。元来、神社と寺院は別々の宗教ではありますが、こうした知恵によって、宗教同士が衝突することなく、仲良く併存することが可能となっていったのです。とても素晴らしい考え方だと思います。
神道と仏教は、ともに唯一神を信仰する一神教ではないから習合が可能なのだと思われるかもしれませんが、一神教であっても、互いに認め合うことは不可能なことではありません。宗教はあくまでも人の営みです。人が正しく善く生きるためにあるのが宗教です。宗教同士で争いごとなんて、こんな馬鹿げたことはありません。大切なのは衝突を避けるための知恵です。知恵を出さず、暴力によって相手を駆逐するというのは、これはもう人の所業だとは言えないはずです。心地良く生きるためにも、互いを認め合う知恵を出したいものです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
仏教の修行と言いますと、かなり難易度が高いと思われる方も多いでしょう。修行という言葉のイメージが厳しさを伴いますし、実際、難しい修行は現代でも受け継がれています。しかし難しい修行があるならば、易しい修行もあるのが道理です。難易度は自分に合った程度を選べば良いので、それほど恐れることはありません。
私は縁あって浄土真宗の坊さんであるのですが、浄土真宗は他力易行門を旨とすることから、身体的に厳しい修行はありません。江戸時代から学問に力を入れてきた宗派なので、勉学には励まねばなりませんが、皆さんが想像するような難しい修行はないのです。
難行であれ易行であれ、仏教には修行がつきものです。他力易行門においても、自力で行う難しい修行はありませんが、阿弥陀如来から賜る意味での修行はあります。少し奇妙な言い方に聞こえるかもしれませんが、阿弥陀如来が修行時代に完成された「修行の成果」を、そのまま私がいただくというのが他力易行門の修行です。「他力」とは「阿弥陀如来のはたらき」を指す仏教語です。阿弥陀如来から成果をいただき、同じようにさとりへと向かわせていただくというわけです。
難しい修行を私が自力で成すのではないので、その意味において易しい修行、つまり易行です。ただ、そのまま私が疑いなく阿弥陀如来から成果をいただく、受け取るというのは簡単なことではありません。疑いというのは、難行に対する心構えもない私が、阿弥陀如来に頼らずとも自力で成すことが出来ると思う慢心です。
慢心とは驕った心であり、仏教ではご法度です。まずは自分の至らなさ、愚かさを知ること、そのためには仏法を聞くしかありません。人の話を聞かず、自分だけの尺度で物事を計っていますと、どうしても独りよがりになりがちですよね。そこに慢心が生まれます。仏法は阿弥陀如来から賜る尺度です。仏法を聞くことによって、ようやく自分の至らなさ、愚かさに気づかされます。まずは何事も耳を傾け、聞くことが大切です。
仏法を聞いて、自分自身に向き合い思慮深くなることが出来れば、自から疑いも晴れて来ることでしょう。深い思慮は気づきにつながります。偽りのない自分本来のすがたに気づかされ、阿弥陀如来に「私の修行」をおまかせすることが出来れば、それがそのまま他力易行の修行となります。「聞・思・修」は仏教における仏道の歩み方を示します。これは自力難行でも他力易行でも同じです。
まずは聞くこと。普段の生活においても、「聞」こそまず大事だと言えますね。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
運命の分かれ道ってありますよね。あの時、ああしていればよかったなあとか。もっと前向きに言えば、ああしたから今があるんだとか。人によって様々だと思います。自分の判断だけでは避けられないような出来事もありますが、だいたい自分の判断で歩みを進めてきたと思えることでしょう。運命は自分で切り開いていくものなのだと考えている方も多いかもしれません。
人生を振り返るならば、たしかに分かれ道はあると思えますが、歩んできた道は1つです。そして、これから先も歩む道は1つです。おそらく分かれ道はあるでしょう。しかし、歩める道は1つなのです。分かれ道では自分の判断で歩む方向を決めることでしょう。それが人生であるはずなのですが、本当に自分が下す判断に方向を決める力はあるのでしょうか。もしかしたら、はじめからそう判断するよう決められているのかもしれません。
こうした考え方を運命論と言いまして、運命はすべて決まっていると考えます。分かれ道があるように思えても、決まっている道を歩んでいるだけなのです。がっかりする思いではありますが、避けがたい出来事もあることを考えますと、一概に否定することはできないかもしれません。自分の判断だけで切り開けない場合もあるからです。そして、自分の判断であっても、あらかじめ決められた判断であったとも考えられなくはないですよね。
さて、仏教ではどう考えるのでしょう。結論から言いますと、仏教には上記のような運命論はありません。仏や神によって運命が定められているとか、そういうことはないのです。仏教では因果論と言いまして、この宇宙における物事の流れというのは、何らかの原因によって結果がもたらされるという原則です。避けがたい出来事であっても、それが起きる原因は必ずあります。また、自分の判断で道が開かれたならば、当然、自分の判断が原因となっていますし、そう判断したことの原因もまた存在しています。
これはつまり、自分が人生を切り開くという意味において、運命論とは対極的であるとも言えそうです。さらに言うならば、大乗仏教においては唯心思想と言いまして、物事の原因はすべて自分の心によっていると考えます。となりますと、自分に無関係そうな出来事であっても、めぐりめぐってその原因は自分にあるということにもなってきます。ここでは唯心思想について深入りはしませんが、いずれにしましても、仏教ではあらかじめ決められた道を歩むのが人生であるとは考えていません。
なるほど、ならば人生において大事なことは、やはり自分の判断なのだと思えてきそうなところですが、実はそう簡単ではありません。よくよく考えてみるならば、こうした因果論というものは、究極的に言うなばら、すべての出来事は1つの原因に収束されていくということになってしまいます。つまり、その原初的な原因の存在によって、この宇宙の出来事はすべて起きるべくして起きているということです。これは見方を変えただけで、実際には運命論と変わらないとも言えます。
先に述べましたように、自分の判断であっても、そう判断する原因はあるわけで、そうであれば、その原因のそのまた原因もあることにもなります。それを突き詰めれば、原初的な原因にたどり着いてしまいます。なんだ、結局のところ人生は決まっていると言えるではないかと。何のために生きているのかと悲観的になってしまいますよね。しかし大丈夫。ここからが仏教の本領発揮するところであり、こうした因果の束縛から自由になることこそ仏教の目的です。
大乗仏教においては、真如法性(しんにょほっしょう)をさとることにより自由になることができると説きます。言い換えれば、それをさとらないかぎり何をしてもダメなのです。完全にさとることがなくとも、段階的なさとりでも変化は起きてきます。さて、この真如法性とはどうやってさとるのでしょう。そもそも、真如法性って何なんだ。
少し話が変わりますが、仏教では迷いの世界に縛られていることを輪廻転生と言います。命あるものすべて、迷っているかぎり、様々な命のステージをグルグルめぐっているだけだと考えます。前世もあり、前々世もあり、数限りないステージをへて今、私はこうして人としてのステージを生きているわけです。輪廻とはよく表現したもので、もしかしたら私は迷っているかぎり、いくつかのステージにおける同じ人生を、何度も何度も繰り返しているだけかもしれないのです。
では、私は何に迷っているのでしょう。それは物事のとらえ方です。宇宙の物事はすべて諸行無常であり、これは移り変わっているという意味です。因果は絶え間なく発動しているので、変化は絶え間なく起きています。停滞することはありません。自分自身の存在もそうです。先ほどの自分と、今の自分は同一ではありません。だって心は絶え間なく動いてしまうでしょう。それを無理矢理、固定的にとらえようとするから間違えるのです。物事を正しくとらえることができていない、変化に対応できていない、だから迷う。真如法性とは、物事の正しいあり方です。
真如法性をさとることができれば、今まで持ち合わせていなかった原因を自分に植えつけることができます。そうでないかぎり、結局のところ同じ過ちを繰り返すため、判断はいつも間違えることになります。避けがたい難局に遭遇したとしても、正しい物事のとらえ方ができていれば、人生の歩みは変わっていくことでしょう。因果論は原則として存在しますが、人生を変えることはできるのです。ちなみに真如法性をさとるためには、正しい生活をして正しく思考することが前提です。倫理的な善悪もしっかりわきまえないとならぬわけで、まずは自分自身の行いを振り返ることがスタートとなりそうです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
今まで極楽浄土の話をしてきましたが、こうしたいわゆる「あの世」という概念を、日々の生活において捉えるならば、どういう意味が出て来るのでしょう。そもそも、なぜ極楽浄土が仏教で説かれるかと言えば、より充実した「今」を生きるためです。極楽浄土が善い国土だから早く行ったほうがいい、つまり早く死ねと言っているわけではありません。むしろ、行く準備をしとけということで、それが「今」の充実につながるということになります。
極楽浄土のような「あの世」がないとしたら、どう思われます?元気で健康のときは死なんてほぼ考えませんので、もとより「あの世」なんてないと一蹴される方も多いでしょう。しかしどうでしょう、自分は元気であっても、自分にとって大切な方が先に亡くなったとしたら、同じように考えられるでしょうか。「あの世」がないということは、亡くなれば無に帰すということです。何もかも無くなる。まさに無です。
もちろん、それでも問題ないと答える方はいらっしゃると思います。それはそれで大いに結構なことです。ただ、少なくとも私にはそう思えません。大切な方であれば再会したいですし、見守っていてもらいたい。そして、いざ自分が死ぬとなれば、やはり無に帰すということを想像するだけで怖い。無というのは文字通り何も無しです。空間すら無い。当然意識は無いですし、存在しません。無を感じることもない。
宇宙の果てがどうなっているのか想像するより恐怖感があり、寝る前に布団で考えてはいけません。翌日、目が覚めればすっかり忘れているものですが、忘れているだけで解決にはなっていません。生きているということが、実は常に無と隣り合わせなのだとしたら、私はとても不安です。仏教の説かんとするところは、「今」をより良く生きましょうということなのですが、死の問題はそこに首をもたげてくるものです。ああ、恐ろしい。
死がどのようなものであれ、死を受け入れることは難しいことです。生命なのでいずれ死ぬとは理解していても、心情としてはなかなかついていけません。だからこそ「あの世」が必要なのです。死は無ではなく、生活の続きなんだと思えることは安堵になります。たとえそれが証明できないものであったとしても、「あの世」があって続いていくと思えることこそ重要です。極楽浄土は「今」を生きるため、死の恐怖を少しでも軽くし、しっかりとした死への準備を促してくれます。
はっきり言いますと、極楽浄土があるのかないのかなんて分かりません。おそらく、経典に説かれているような具体的な環境ではないでしょう。高度な瞑想によって極楽浄土の知見を得た高僧方は、当時の表現法にしたがって経典に様子をまとめたのです。死んで見て来たわけではないので、客観的に証明できるものがあるわけではありませんが、私も何かはあると思います。私たちはこの宇宙の一員です。1つの命として、宇宙の何かに帰っていくということが極楽浄土へ往くこと、すなわち浄土往生なのだと考えています。
浄土往生は「この世」と「あの世」の橋渡しです。ここからは本当に宗教的な言い方になりますが、橋があると信じていれば、必ずあります。私はそう思って臨終を迎えたい。その時はもう分からなくなっているかもしれませんが、普段からそう思っていれば大丈夫でしょう。亡くなった両親にも再会したいのですし、何も無いよりよほど嬉しい死後の世界かな。いつ死ぬか知りませんが、浄土往生という橋渡しによって死の準備をしつつ、安堵した生活を送っていきたいものです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
浄土系の寺院で読誦することの多い『阿弥陀経』という経典に、「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」(しょうしきしょうこう おうしきおうこう しゃくしきしゃっこう びゃくしきびゃっこう)という一節がございます。これは阿弥陀如来の国土である極楽浄土においては、それぞれの色がそれぞれ自分自身の色をしっかりと映し出している、という様子を説いています。単純に4色しかないということではなく、無数の色があっても、互いに妨害しして個性を打ち消し合うことがないことを示唆しています。
これは人の個性です。人は千差万別、同じ思考の人はいません。一卵性の双子であっても、毎日同じ服を選ぶということはないでしょう。身体的に同じ存在とはいえ、別人格だからです。もし同じであるならば、何か外的な強制的要因が働いているはずです。別々で良いのです。経験も異なりますし、そもそも心はそれぞれ異なります。
しかし、個性と個性がぶつかり合いますと、時には問題も発生します。色合いで言うならば、ぶつかり合ってゴチャゴチャになれば、美しいとは言い難い風合いになってしまいます。
『阿弥陀経』では上記の経文の直後に、「微妙香潔」(みみょうこうけつ)と説かれます。これは、それぞれの色が「きわめて見事であり清らかな香りがする」という意味です。もう少し具体的に尋ねてみますと、『阿弥陀経』のサンスクリット語原典(『阿弥陀経』は漢訳であり、元々はインドのサンスクリット語で書かれていました)の同じ箇所では、「さまざまな色の蓮花はさまざまな色でさまざまな輝きがあり、さまざまな色に見えている。」(岩波文庫『浄土三部経(下)』、紀野一義訳)と説かれています。4つの色があっても、それぞれがぶつからず、それぞれが個性を発揮しているということでしょう。だからこそ、「きわめて見事」なのです。
昨今、多様性ということが声高に叫ばれていますが、互いに尊重しなければ成り立たない概念でもあります。自分が輝くためには、他者も輝いていなければなりません。私がいて、あなたがいる。あなたがいて、私がいるのですから。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
極楽浄土、仏教で説くところのいわゆる「あの世(あちらの世間)」ですが、より清浄さが強調される場合は「出世間(しゅっせけん)」とされ、穢れである世迷い事のある世俗を出たより高次な国土とされます。「世間」というのは、まだ迷いの世界にあるという意味で使われる場合が多いようです。イメージとしては、私たちが生きている「この世」です。いずれにしましても、極楽浄土は阿弥陀仏という仏のいる国土にはなります。
う~む、何のことやら、と思われことでしょう。しかし、浄土と名のつく仏国土は他にもあり、どの浄土へ行くことが最善なのかと議論されたこともあったのです。極楽浄土は他浄土の信奉者から低次に見られることもあったのですが、そもそも、極楽浄土を説く経典はたくさん存在し、それぞれ説いている内容に矛盾があったりしました。どの程度清浄なのか何とも言えず、どんな仏国土なのかなかなか定まらなかったのです。今でこそメジャーな極楽浄土ですが、この立場を得るためには紆余曲折あったわけです。
ところで、極楽浄土はどのような過程をへて人の知るところなったのでしょう。文章化という視点から言えば、1世紀頃に編纂されたとされる『阿弥陀経』など、阿弥陀仏が登場する浄土経典(たくさん種類があります)に説かれていることが分かっています。と言うことは、それ以前にどこかの誰かさんが発見したことになります。え?それってお釈迦さまなのでは?と思われるかもしれませんが、たしかに仏教の開祖はお釈迦さまなのですが、歴史的に見ますとお釈迦さまが極楽浄土を説いた形跡は今のところありません。お釈迦さまは仏教の基本的な教えと瞑想法を説かれましたが、お釈迦さま以降も仏教は発展し、高僧方が様々な教えと瞑想法を提示されたのでした。極楽浄土はこうしたなかで歴史上に登場します。
浄土経典に説かれていることを見ますと(『阿弥陀経』など、本屋さんで売っています)、極楽浄土は当時の僧侶にとっての理想国土のようにも思えます。当時というのは前述の紀元前後のことなので、お釈迦さまがお亡くなりになって5~600年前後は経過していると思われます。お釈迦さまはこの世に出られた仏(←釈迦牟尼仏とも言います)であり、仏の教えを直接受けることは僧侶の宗教的理想です。しかし、そのお釈迦様はすでにおられないとなりますと、この世からどこか別の仏のいる国土へ移動するしかないわけです。
高僧方が瞑想をされるなか、おそらく、こうした願いも相俟って、この世とは別の仏国土である極楽浄土の存在を知り、そこに阿弥陀仏を見たのではないかと思います。瞑想においては、阿弥陀仏が眼前に立たれ教えを説かれることもあったかもしれません。瞑想によって観察した阿弥陀仏の姿と極楽浄土の風景を改めて言語化し、それをもとに神話的脚色、つまり、阿弥陀仏がどのような修行をへて仏となったのか、仏になる前は何をしていたのかといった話を加え、浄土経典が誕生したのかと思います。その阿弥陀仏は歴史上のお釈迦様をなぞるように語られ、阿弥陀仏から直接教えを聞く願いが達せられる国土として、理想的に極楽浄土は描かれています。理想国土という意味で言えば、たとえば沐浴場の水温調節が完璧だとか、洗濯物がよく乾くとか、そういう生活空間の願いも込められているところは興味深いです。阿弥陀仏がおられて、そのご指導のもと、心地よく仏教の教えを実践することができるような国土なのです。
語弊を恐れず言い方を変えれば、会いたい人に会える国土、それが極楽浄土です。誰しも再会したい方はいることでしょう。家族であったり、友人であったり、はたまたその道の先達であったりと、人によって様々だと思います。浄土経典には「倶会一処」という言葉がございます。極楽浄土においては、「ひとところ(一処)でとも(倶)に再会できる」という教えです。古の僧侶たちは仏に会いたいと願ったことでしょう。
死すれば何もなし、と考える方もおられるでしょう。もちろん、どうなるかは死なないと分かりません。しかし、私は何もないのでは寂しい。会いたい人、たくさんいます。もう会うことができないなんて、せっかく出会ったのに悲しいことです。仏教での極楽浄土のみならず、諸々の宗教では何らかの「あの世」が説かれます。宗教とは自分の「生き死に」を課題としているものですが、それは宗教でしか解決できないからです。科学的に解決するということではなく、宗教として、宗教的な解決を図っているのです。死は誰にとっても恐ろしい事です。できれば死にたくないし、大事な方にも死んで欲しくない。そう思うのが人情ですが、そうはいきません。会いたい方に会えるところ、それが極楽浄土であり、いわゆる「あの世」です。願うならば、行くことができるはずです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
仏教に限らず、どのような宗教でも信心は不可欠です。仏さまも神さまも、普通に生活していれば頻繁に出遇えるという存在ではありません。宗教において、私たちが直接触れているのはまずは教えであり、教えを通じて宗教体験をすることが可能となります。つまりその教えを聴いてみないと、そもそも始まらないのが宗教なのです。そこが衣食住と異なるところであり、宗教は人生を豊かにしてくれるものですが、必須ということでもありません。
たいていの宗教には尊格がありまして、仏教では仏さまが筆頭の尊格です。尊格がたくさん存在する宗教もあれば、ひとつだけの宗教、また、抽象的な宗教もあります。仏教は対機説法と言いまして、説法を聴く人に合わせて様々な教えが説かれます。必然的に仏さまも色々な性格が出て来まして、たくさんの仏さまが存在することとなりました。別人格というわけではなく、仏さまの多様な側面という意味になります。一方、キリスト教やイスラム教など、神は唯一としてその多様性を説かない宗教もあります。
いずれにしましても、教えには仏さまや神さまを信じることの意義深さが説かれており、そこから信心が始まっていきます。仏教のなか、とりわけ信心を重んじているのは浄土教であり、阿弥陀如来の教えを説くものです。阿弥陀如来は命あるものすべてを救い取ってくださるはたらきであり、阿弥陀如来に帰順することが浄土教の信心となります。
しかし、一度教えを聴いただけで簡単に信じられるのかと言えば、そんなことは稀でしょう。教えを通じて、自分自身にとって何らかの実感があるからこそ、信じる気持ちにもなるものです。
浄土教において、信心というものは2つの側面があると言われます。まず、人は教えに触れることによって、はじめて明確に自分の過ち、自分の至らなさに気づかされることがあります。愚かな自分に気づかされるのです。そして、愚かであるからこそ、だからこそ救いの手を差し伸べてくださる阿弥陀如来。こんな自分を無条件で受け入れてくださる阿弥陀如来の慈悲に触れたとき、信心は自から実感できるものとなります。信心はまさに阿弥陀如来からいただくとも言えましょう。これを二種深信(にしゅじんしん)と言います。
自らの愚かさに気づかされること、場合によっては、懺悔(さんげ、ざんげ)という言い方もいたします。仏教のみならず、キリスト教などにも見られる宗教行為です。自分を悔い改めるということです。仏さまや神さまの前だからこそ、嘘偽りのない自分に正直に向き合うことが出来るのでしょう。信心というものは、ただ信じ込むというものではなく、内省による自分自身の気づきがあって初めて成り立つものなのです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
前回、自業自得のお話をさせていただきました。私たちは自分の意志に関わらず、思いがけず善い方向にも悪い方向にも行ってしまい、困惑することもしばしばです。だからこそ、時には肩の力を抜いて、流れにまかせるような生き方も必要ではあるのですが、状況を変化させる自分の意志もまた業とは無関係ではありません。変化させたいと思う意志も業のうちであり、変化を望むということは、そうした業によってもたらされた結果でもあるのです。
分かってはいても、なかなか状況を変化させられない。そういう時は、いまだ変化するという結果がもたらされていないか、変化の最中にあっても、正しい行動を取れていないということになります。時が満ちていない場合は待つしかありませんが、思うように上手く変化出来ない場合は、正しくない行動によって、さらに悪業を積んでしまっている可能性もあるでしょう。では、悪業を積まないようにするためには、どのような心掛けが有益なのでしょうか。
仏教においては、私たちの行動指針として、無所得ということが頻繁に説かれます。これはもちろん報酬を得ないというボランティア精神のことではなく、得るところがない、すなわち、物事に余計な執着をしないという意味になります。私たちが物事をとらえて、実体があると思ってしまうことであっても、仏教ではそのように見ることはありません。私たちの身体を例に取ってみますと、身体はたしかに実体があり、だからこそ私たちは生きていて、時には爽快感を、また、ときには苦痛を感じることもあります。しかし、よくよく考えてみるならば、身体は刻一刻と変化しているのであり、私たちが思い込んでいるような固定的な実体があるわけではありません。その証拠に、私たちの身体はいつか使用不能になる、つまり、私たちはその時が来れば死ぬわけです。
他にも名誉ですとか、お金というものであっても、実際には実体なんてありません。実体がないにも関わらず、私たちはそれを得るために一所懸命であったりします。出来れば限度までそれらが欲しい。ただし、思いよりも満足に得ることが出来なければ、逆に苦しみや辛さが増すばかりです。思うように人から評価されない、思うようにお金がない、そして、健康だったのに病気になってしまった…、となれば、誰でも良い方向に人生が向いているとは思わないでしょう。
名誉だって、お金だって、そして健康だって、出来ればある程度得ることが出来たほうが良いでしょう。問題は、どの程度に思うかということなのです。本来は実体のないものなのですが、私たちはそれらを追い求めて幸せを感じるところがあります。これはもう仕方のないことです。執着している以上、完全に正しいといは言えないあり方ですが、これを修正するためには厳しい修行をせねばなりません。より自分にとって充実した人生を歩むためには、以前もこのコラムで取り上げましたが、少欲知足、欲少なく足るを知る心掛けが大切であり、そのためには、そもそも自分が一所懸命に得ようとしている物事なんて実体がなく、すべては無所得なのだという理解が一助となるはずです。何事もほどほどに、欲張れば欲張るほど悪い方向に行ってしまうからです。
執着は悪業となって、自分自身に苦しみや辛さといった悪い結果をもたらします。正しい行動とは執着を出来るだけ少なくしていくことであり、それは善業となって善い結果を生み出すことでしょう。状況が改善されていくということは、こうした正しい行動があってのことだと言うこと、肝に銘じておきたいものです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
今回、タイトルだけを見ますと、あまり良い印象を持たれないかもしれません。「自業自得」という言葉は、一般的には悪い意味で用いられることが多いでしょう。「悲惨な結果になったのは自業自得」など、悪いことは自分の責任なのだという意味です。しかし、これはもともと仏教の言葉であり、「自分自身の行為(身体、言葉、心)の結果やその影響(→自業)は自分自身で得ることになる(→自得)」という意味なので、善いことも悪いこともすべて含まれています。善い行いをしたら善い結果が得られるという意味でもあります。
ただ、善悪という概念は判定が難しいので、今回は善悪には触れず、自分自身の行為の結果やその影響は自分自身で得ることになる、という点に絞ってみたいと思います。
今、自分はなんでこんな状況に置かれているのだろう、自分はなんでこんな境遇にあるのだろう、そもそも、なんで人として生まれてきのか、なんで自分という人格を得ているのか。たいてい人には不満があるものなので、なんでかなとその責任の所在を突き止めたくもなります。しかし、いずれも自業自得です。仏教の考えで捉えれば、生まれてこの方、してきたことはすべて自分自身の業によります。さらに言えば、どう生まれたのかも、どのような境遇で生まれたのかも、実は両親や先祖の責任ではなく自分自身の業によっているのです。もちろん、これは「前世」という生まれる前の自分のあり方、宗教的な考えに基づいてはいますが、自分が生まれてきたのは両親や先祖の責任にはならないのです。
生きていますと、自分の意志とは反対の方向に事が流れていってしまうこと、よくよく遭遇いたします。おかしい、こんなはずじゃなかったのに、という具合です。人生の歩みは何でも意志通りになるわけではないこと、私たちは経験的に理解しています。ただ、自分の意志、つまり意識レベルにおいて、今まで自分の行ってきたことや自分で考えていたこと、すべてを管理して記録してあるかと言えば、そんなことはないでしょう。この世のことでもこんな程度なのですから、前世のことなんてまったく分かりません(もとより前世の記憶は、現世であるこの世には持ち越されません)。
意識というものは、私たちのほんの一部に過ぎません。今現在の自分を構築するものという視点において、業こそが私の本質とも言えます。意識はあくまでも舵取りの役目であり、本質とまでは言い得ません。善いことをしようとしても、思わず悪い方向に行ったりすることもあるでしょう。そんなつもりはなくとも、そうなってしまうのは、自分の業によって物事が引き起こされているからです。舵が効かないこともあるわけですね。自分のあずかり知らぬことに思えても、自分に起きている事態はすべて自業自得によっているのです。思い通りにならないわけです。極端な言い方になりますが、人は死にたい時には死ねず、死にたくない時には思いがけず命を落としたりするものです。
私たちは、こうした一見すると不条理かと思えるようななか、生きてゆかねばなりません。もしかしたら、不条理であることの説明のため、業という考えが生まれたとも言えるかもしれません。業のはたらきは科学的に解明できるような性質ではないので、存在の証明は出来ません。しかし、何事もまず自分自身の行為を顧みる必要性を説いています。何かと責任転嫁しやすい私たちですが、今ある状況で生きていかねばならぬこと、状況を改善させる可能性は自分以外にはいないこと、そして、だからこそ自分は大切な存在であり、かけがえのない尊厳を持っているのだということを、業という考えは私たちに伝えようとしているのだと思います。
厳しい世の中ですが、自分に可能なことは前向きに取り組んでいきたいものです。出来ないことは出来ないで良いのです。それが自分の業なのですから。無理をするようなことではありません。これは「投げ出し」ではありません。諦めです。「諦める」ということは、実は自分の状況を「あきらかにする」という意味です。諦めることこそ肝腎です。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら
前回からの続きとなります。
幽霊登場のお話や、幽霊画や幽霊像を見るならば、恨めしい思いを持って亡くなった人もいるだろう、怒りのなかで亡くなった人もいるだろう、大きな悲しみをこの世で懐いて亡くなった人もいるだろう、そういう「まだ生きている人の感情」の投影が幽霊という存在を形作ってきたことは想像に難くないことです。しかし、そうは言いましても、実際に幽霊を見たという話は、昔も今も尽きることがありません。幽霊が見える、という認識は精神医学や心理学の側面から解明できる場合も多いようですが、仏教においても、認識の対象(いわゆる五感や意識で認識可能なところ)を3種類に分けて解説していますので、そこに幽霊の正体を見出せるかもしれません。
大乗仏教の唯識思想では、三類境(さんるいきょう)と言いまして、私たちが日常世界で認識している対象(=境)を、以下、3種類に分析します。
①まずは「性境(しょうきょう)」と言いまして、言うなれば「実在」しているものです。主観に左右されずに客観的に存在しています。それ自身の本性を守って存在している、という意味です。日常世界における物理的存在です。
②つぎは「独影境(どくようきょう)」で、これは逆に主観によって描き出された存在で、本性や本質というものがまるでありません。影像だけが独りで起きているので、幻覚とか幻聴といったものに該当します。物理的に存在していないのです。
③最後に「帯質境(たいぜつきょう)」です。独影境は本性や本質がありませんでしたが、こちらは本性があり本質を帯びています。しかし性境のように、主観がその本性をしっかり認識できているかと言えば、ありのままに認識されているわけではありません。簡単に言えば見間違い、聞き間違いです。
以上です。意外とシンプルに思われるかもしれませんが、この3種類を導き出す過程は複雑なものの、たしかにこれで十分だと言えそうです。では、幽霊はどこに当てはまるのかと言えば、①性境ではないのは確実なので、可能性としては②独影境か③帯質境になります。しかし、②独影境には本性がなく、そこには幽霊を幽霊たらしめるこの世への怨念や悲哀といった心の一部すら存在していないことになります。主観が勝手に作り出した幻であるため、これは精神医学や心理学で分析される事象に近いでしょう。だとするならば、巷で騒がれることの多くは③帯質境になります。
夜中に境内にいれば、木々が幽霊に見えることは経験上よくあることですし、何となく薄気味悪い雰囲気を感じれば、何でも幽霊に見えてくるものです。心霊スポットもそうです。心霊スポットという触れ込みがあるからこそ、そこに行けば主観はそう物事を認識してしまう方向に誘導されるもので、幽霊はたくさん出現しそうです。主観は雰囲気に左右されるものなので、複数人であっても共通の雰囲気のなかにいれば、同じように見間違いや聞き間違いをする可能性もあるでしょう。仮に心霊スポットという看板がなくとも、今までの経験や知識の上から、何となく幽霊が出そうだなと感じてしまえば、幽霊の出現率は高くなると思います。幽霊が何故かだいたい似たような姿で伝わるのは、あらかじめ幽霊の姿が私たちにインプットされているからです。モデルはもちろん、ご遺体です。
このように、大乗仏教の理論の上からするならば、幽霊存在の可能性はどんどん狭くなってきてしまいます。ただし、何事も完全に「ない」を証明することは困難と言われますし、上記の三類境であっても、もとより、幽霊の存在を分析するための教義ではありません。私が勝手にここで使用しただけなので、分析として不十分ではあります。では、もし三類境以外に幽霊が見えるという現象を尋ねるならば、それはもう真如、つまり仏さまからのはたらきかけに他ならないでしょう。たとえば亡父の幽霊かと思ったが、実はそうした姿で語りかけてくださる仏さま、幽霊だって仏さまとして、私を導いてくださる存在として捉えることも可能だと思います。私は、こうした幽霊は大いに信じています。父はちゃんと成仏して、敢えて幽霊になって戻ってきたとも言えるでしょう。有難いことです。
幽霊とは、亡き方を思う気持ちにより成り立っている、亡き方を思わなければ、幽霊という存在はあり得ません。言い換えれば、幽霊は供養なのです。日本人は古来、それだけ人の死を悼んできたということでしょう。生死こそ、私たちの一大事だからです。
幽霊に出遇ったならば、有難い気持ちで接したいものです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦
善福寺の公式サイトはこちら
『宗の教え~生き抜くために~』アーカイブはこちら

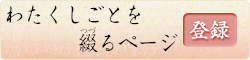
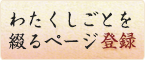



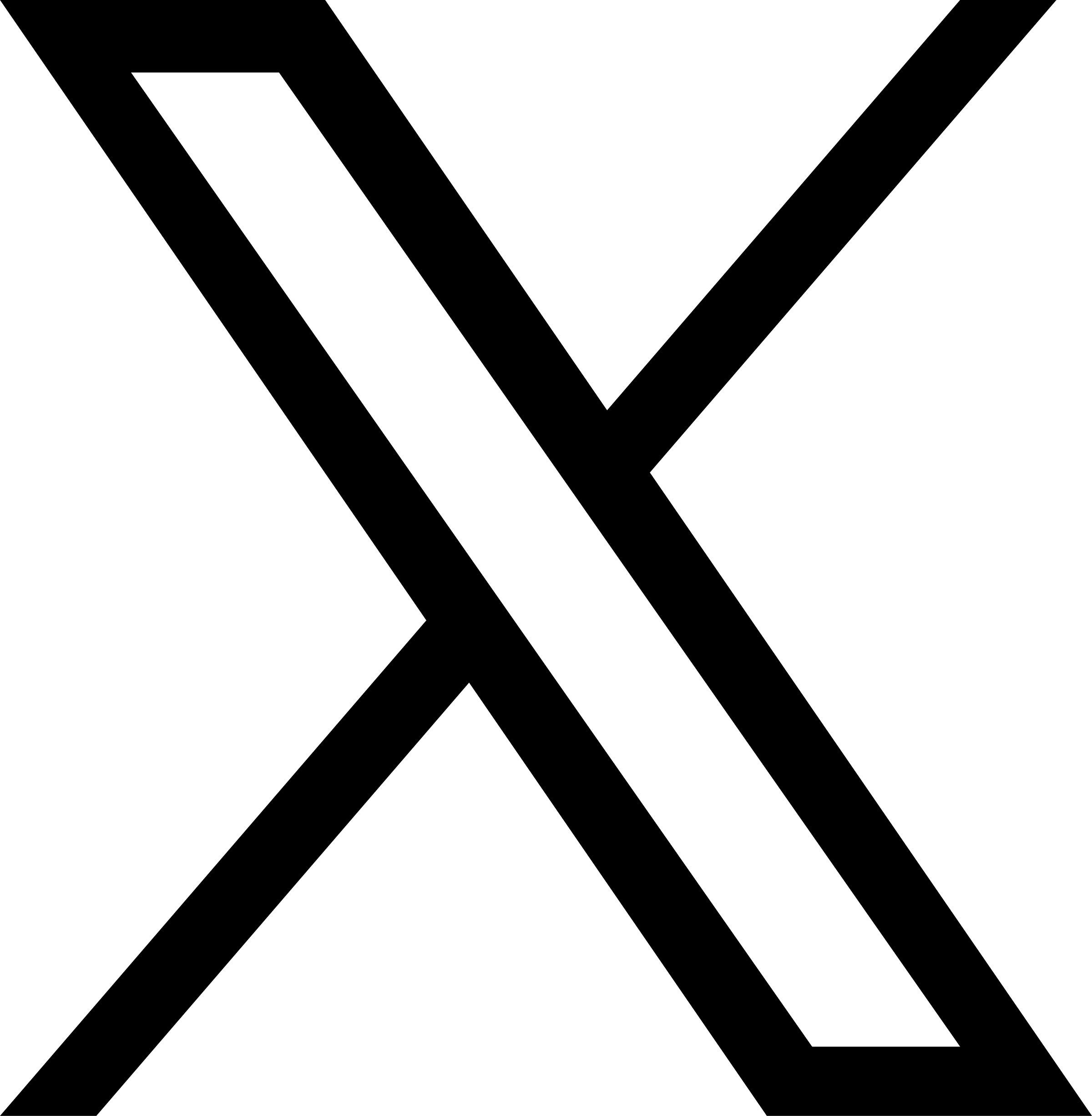
 Facebook
Facebook