出雲の戦国大名尼子氏 其の一
歴史の木戸口 史の綴りもの、今回は、戦国時代半ばに一時は山陰山陽十一か国の内、八か国の守護となり、中国地方に並びなき勢力を誇るまでに至った尼子(あまご)氏に連なるお話でございます。
尼子氏といえば、長禄二年(西暦1458年)に生まれ、主家である京極氏の出雲守護代としての立場から、着々と在地で独自の権力基盤を築き、尼子氏を戦国大名へと伸し上がらせしめました尼子経久がまず思い浮かぶところでございましょうか。権謀術数に長け、同時代中国地方で同じく謀将としても名高い毛利元就、宇喜多直家と並び中国地方の三大謀将とも称されております。ただ、弱体化しつつあったとは言え未だ中央から全国の政を執りおこなっていた室町幕府や主家の命をはねのけつつ、取分け主家の京極氏が守護代を派しながらその下部組織たる小守護代や郡奉行といったものたちが存在せず、他国とは少し異なる、守護代による独自の統治支配が長らく行われてきた出雲国では、言わずもがな国人衆(南北朝から室町期、その土地に実行支配力を持っていた地方豪族)はじめ寺社勢力、たたら製鉄場といった在地勢力の力も強く、これら勢力との結びつきを強めていきながら自身の権力基盤を確立させていくことは並大抵のことではござりませんでした。尼子氏の戦国大名としての基礎固めは経久の力量を以てしてはじめて成しえた一大下克上事業とでも申すべきものでございましょうか。中でも、時代が進みやがて各地で守護大名、戦国大名の被官として家臣団に組み込まれていく国人衆ですが、この時期にはまだ大小様々な在地独立勢力としての毛色が強く、それをどう味方とし、味方とし続けられるかは常に勝敗を大きく左右するものでございました。よく言えば気を見るに敏、悪く言えば日和見主義的なところもある彼ら国人衆もまた、その判断は生存に関わる重大事、致し方のないことでもございまして、結果として、旗色次第でまとめて寝返ってしまうということしばしばでございました。経久の勢力拡大策は、その拡大の途上で当然の如く、時に国人衆や他の支配勢力との対立を生むことにもなり、中でも西出雲の塩冶氏と対立は、後に尼子宗家による支配体制を見直さざるを得ない結果を見せつけるものとなったのでございます。塩冶氏と言えば、元をたどれば尼子氏とは同族、出雲国西部で大きな勢力を誇る一族で、鎌倉期には出雲守護を務めていた名族でもございました。
さて、周りをすこし広く見まわしますれば、西に西国一の勢力を誇る大大名、大内氏有り。周防国山口を本拠に東は石見、安芸、西は北九州の筑前、豊前にまでその支配力を及ぼした西国の大大名家にして、その影響力を度々中央にまで及ぼすほどの力を持っておりました。永正八年(西暦1511年)大内義興上洛の折には尼子経久もその軍勢に従ったと伝えられておりますが、後の尼子氏の勢力拡大はやがて利害の不一致による争いへとつながり、時に争い、また時には敢えて触れず、の関係がつづくのでございました。
勢力拡大のため、縁戚関係による結びつき、養子縁組による他家の取り込みも巧みに行い、旗色を見て靡いてしまう程度の国人衆とのゆるい結びつきを、尼子宗家の意向で動かせる勢力へと変えていくことにも経久は力を尽くしたのでございます。そして先の塩谷氏に対しては自身の子、三男の興久を養子にいれることで取り込むことを図りましてございます。こうして塩谷氏を継いだ塩谷興久は、父、尼子経久の意思を汲み、幕府御料を直轄地化したり、古志氏など在地氏族を尼子勢力配下に組み入れたりするなど力を尽くしましたが、同時に塩谷氏独自の権益もまた守らなければならない立場でもあり、その故に反尼子勢力との結びつきもまた深めていくこととなり、興久率いる塩谷氏の同盟勢力範囲は出雲西部・出雲南部、そして備後北部にまで至るほどとなっていったのでございます。やがて立場の違いは、互いの中に異なる事情を生み、享禄三年(西暦1530年)塩谷興久は、反尼子の旗手を鮮明にしたのでございました。父、尼子経久との争いに際し、出雲大社、鰐淵寺、三沢氏、多賀氏、それに備後の山内氏等の諸勢力を味方とし、規模の大きなものであったことが窺えると共に、尼子宗家の影響力が出雲西部に浸透していなかったことを如実に物語ることでもあったのでございます。また、両者とも大内氏に援軍を求めておりますが、大内氏側では、両者共倒れを狙ったこともあってか、最終的にはやや消極的ながら経久側に立つということを決しております。激しい戦いの後、乱は鎮められ、興久の領地の多くは、次兄である尼子国久へと引き継がれていきました。
政戦両略を駆使し、時に後退することはありつつも、尼子氏の勢力基盤を着実に強化させた尼子経久、外からは謀将としての顔で知られますが、それが内に対しては細やかな気遣いとなって表れる人物であったとも伝えられております。家臣が経久の持ち物を褒めようものなら、たいそう喜ぶだけではなく、どんなものでもすぐにその者に与えてしまうため、家臣たちも却って気を遣い経久の持ち物を褒めずにただ眺めているだけにしたと言われております。ある時、家臣のひとりが、さすがに庭の松の木なら大丈夫であろうとその松の枝ぶりを称賛したところ、経久はすぐにその松を掘り起こして与えようとしたため、周囲の者が慌てて止めたものの経久は諦めず、とうとう切って薪にして与えてしまったそうでございます。また冬には着ている着物を脱いでは家臣に与えてしまい、ついには自身は薄綿の小袖一枚で過ごしていたとも言われ、欲なく家中を思い遣る主としての姿が伝えられております。
さて、このように守護代から戦国大名へと、まさに下克上の典型とも言える変化を遂げてきた尼子氏ですが、世はこれからさらに乱れ、混沌の中で力が新たな秩序をつくり、戦乱の中で変革を重ねていく時へと向かっていきます。歴代国の力を積み重ねてきた大国でさえただ一度の戦に敗れ滅び去ってしまう時代、尼子氏はどのように舵を取りすすみゆくのでございましょうか。次回、其の二にてお話できればと存じます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

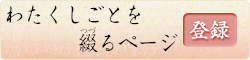
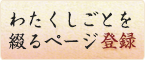



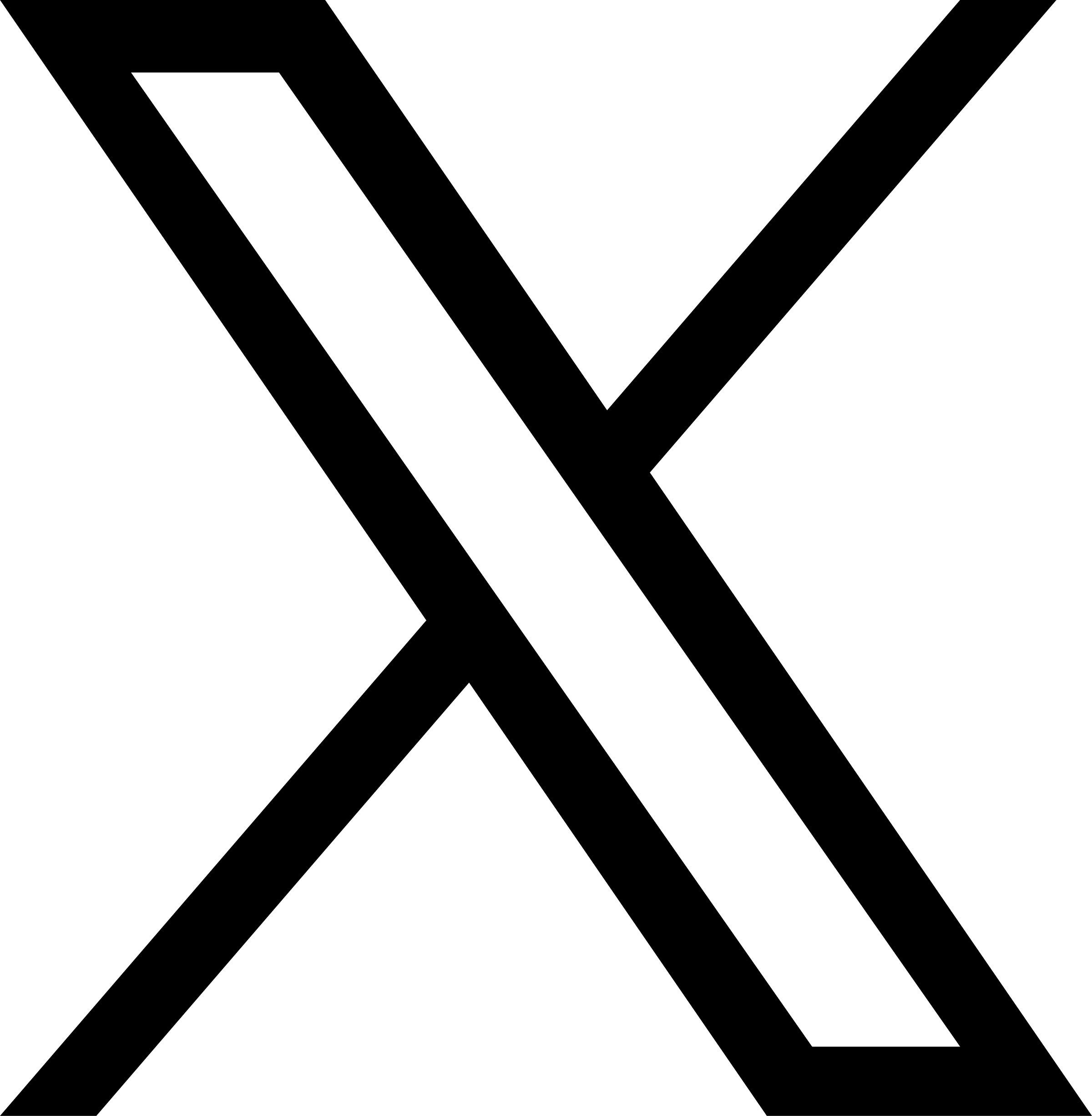
 Facebook
Facebook