一条房基が命を絶つ天文十八年から遡ること六年、天文十二年(西暦1543年)、房基の嫡男として、一条兼定は土佐国幡多郡中村に生を受けたのでございます。
室町の幕府は十二代将軍、足利義晴の時代、ただ依然勢力争いが絶えず、もはや幕府権威の象徴として担がれ、時に畿内を転々とせざるをえない存在となってしまいました将軍家にもはや全国を統べる力はなく、戦乱の世の様相は日の本全てにおいてより深まるばかりでございました。折しも、種子島に鉄砲が伝来したのもこの年のことでございます。
そのように乱れた世にあって、土佐一条家の四代目当主となるべくして生まれた兼定。父房基が突如命を絶ち、兼定には土佐中村の地で悠揚と幼年期を過ごしながら当主としての在り方を学ぶこと、時勢が許さぬものでした。
天文十八年(西暦1549年)卯月(4月)、齢七で家督を継ぎました兼定は、大叔父にあたる一条房通(土佐一条家二代当主・房冬の弟)の猶子となり上洛したのでございます。
応仁の乱に際し家領である土佐国幡多荘に下向した一条教房の実弟で、教房の土佐在国に伴い兄、教房の養嗣子となって家督を継いだ一条冬良に子が無かったことから、冬良が兄、教房の孫にあたる房通を婿養子にして家督を継がせており、天文十六年(西暦1547年)には房通は関白となっておりました。土佐一条家の重臣等としても、事ここに至っては京の一条宗家の力を恃みとするよりほかなし、という思いあってのこととは想像に難くないところではございますが、それより遡り、まだ房基存命の折から、土佐一条家の若年当主を支えるべく、房通は天文十二年頃には土佐に下向し、一時当主に代わり政務を執っていたと伝えられており、房通を恃みとするのは当時の関係性からもごく自然なことであった様でござりまする。
京の房通の下で暮らす間に兼定が多くに触れたであろうとは思われながらも、未だ幼年であり、且つまたその身は土佐一条家の家督、おそらくは京での政争の有様などとはやはり縁遠い時の中で、兼定の人となりは形づくられたのかもしれませぬ。弘治二年(西暦1556年)房通薨去の後に元服、房通の跡を継いだ一条兼冬より偏諱を受け、一条兼定と名乗ることとなったのでございます。そして同年、若しくは翌弘治三年にかけて土佐中村に下向、いよいよ土佐一条家当主として政に向き合う時を迎えるのでございました。
長く土佐七雄の盟主という形で土佐中村の地より周辺をまとめてきた土佐一条氏でございましたが、相次ぐ当主の交代、それに続き幼少の当主が京に在ることで当主在国すらあらぬことは、たとえ平時であったとしても土佐一条氏の求心力を下げる基となったことでございましょう。況や世は乱れ、何れもが折あらばと己が勢力を伸ばす機会を虎視眈々と窺う中、勢力図が描きかえられることにさほど長い時を要するものではございませんでした。
かつて土佐七雄の中で没落し、居城の土佐岡豊城をも追われた長宗我部氏。一条房家の保護と扶けを得て長宗我部家の再興を果たした長宗我部国親は勢力を拡張、永禄三年(西暦1560年)に没すも、跡を継いだ元親は父国親の遺志を継ぎ巧みな結びつきと戦とでやがて他の六雄を従えるほどになるのでございます。
一方、土佐中村に在る兼定は、永禄元年(西暦1558年)伊予大洲城を本拠とする宇都宮豊綱の娘を娶るも、永禄七年(西暦1564年)には離別、豊後の大友義鎮の長女を娶り大友氏と結ぶなど外交を展げておりました。なれど兵を出せども捗々しい拡がりがないばかりか敗退を重ね、また京の一条宗家とも疎遠となっていくなど、次第に勢いを削がれていく土佐一条家でございました。
勢いを増す長宗我部家の侵食は止められず、何ら打開策も見いだせずにいる中、兼定は一門でもあり、家中筆頭格として家臣をまとめる知勇兼備の土居宗珊とその一族を断罪してしまうのでございました。したがこれは長宗我部側の策略によるものともされており、あろうことか兼定は無実の罪で家中の大きな力を自ら切り捨ててしまったばかりか、その行いにより家中の信望をも失っていくのでございます。元亀三年(西暦1572年)のことでございました。
翌年、天正元年(西暦1573年)長月(9月)には、残る三家老ら重臣により隠居を強いられ、天正二年(西暦1574年)如月(2月)には中村御所を出て、岳父である豊後の大友宗麟を頼っていったのでございました。尤もこれは、もとより土佐一条家中だけで謀られたことではなく、長宗我部元親と、京から下向していた一条宗家当主、一条内基との間での遣り取りを経て一条内基の諾意があり、進められたことと考えられておりまする。
土佐一条家は、内基が兼定の嫡子元服を執り行い、偏諱を与えた一条内政に継がせておりますものの、既にして実はなく、傀儡となったものでございました。
さて、キリシタン大名としても知られる大友宗麟の下へ身を寄せていた兼定は、豊後の地で洗礼を受け、キリシタンとなったのでございます。洗礼名ドン・パウロ。兼定なりの純真な思いがあってのことでございましょうか、幡多郡の奪回とあわせて、キリスト教宣布をも目指して動き始めた兼定は、幡多郡の宿毛あたりにキリスト教を伝える拠点を築くことも命じていたといわれておりまする。
こうして一度は追われたものの、天正三年(西暦1575年)兼定は再起を計り大友氏の扶けを借りて土佐へと兵を進めるも、四万十川の戦い(渡川の合戦)で大敗、敗走、土佐国は長宗我部家により統一されたのでございました。
その後、兼定は宇和海の戸島に隠棲いたしますが、再起を計りながらも、成し得なかったということが事実と言い得るかと思います。火種を残したくない元親は一計を案じ、かつて兼定の側近であった入江左近を刺客として兼定のもとに差し向けたのでございます。深手を負いながらも何とか一命を保つことができたのは、兼定にとってはむしろ幸いであったのかもしれませぬ。伝わるところによれば、深手を負い、不具の身となってしまった兼定は、豊後から送られて来るキリスト教の書物に親しみ、慰められ、深く信仰に生きる余生を過ごしたそうでございます。天正九年(西暦1581年)に兼定を見舞ったイエズス会司祭アレッサンドロ・ヴァリニャーノも兼定の深い信仰心と信仰生活を感嘆とともに伝えております。
深い傷を負い、身も不自由になりながらも、信仰に満ち溢れた時を過ごした兼定は、天正一三年(西暦1585年)七月一日、齢四三歳で天に召されたのでございます。
家柄や立場に縛られ、好むと好まざるとに関わらず果たすべき役割を決められてしまう時代、社会において一条家に生を受けた兼定には、違う何かを選び取るということは許されぬものでございました。晩年、信仰の中に身を置いた兼定が、最も自身が自身でいられた時であったのかもしれませぬ。戦乱の世であっても、もし文芸や技芸を家技、家職とする家に生まれていたら、嫡流の重責を背負わされることのない立場であったならば、あるいは歴史に刻まれたものとは異なる、兼定らしさが存分に現れる生き方というものに出逢えていたのやもしれませぬ。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

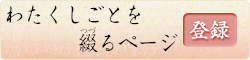
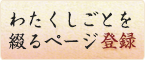



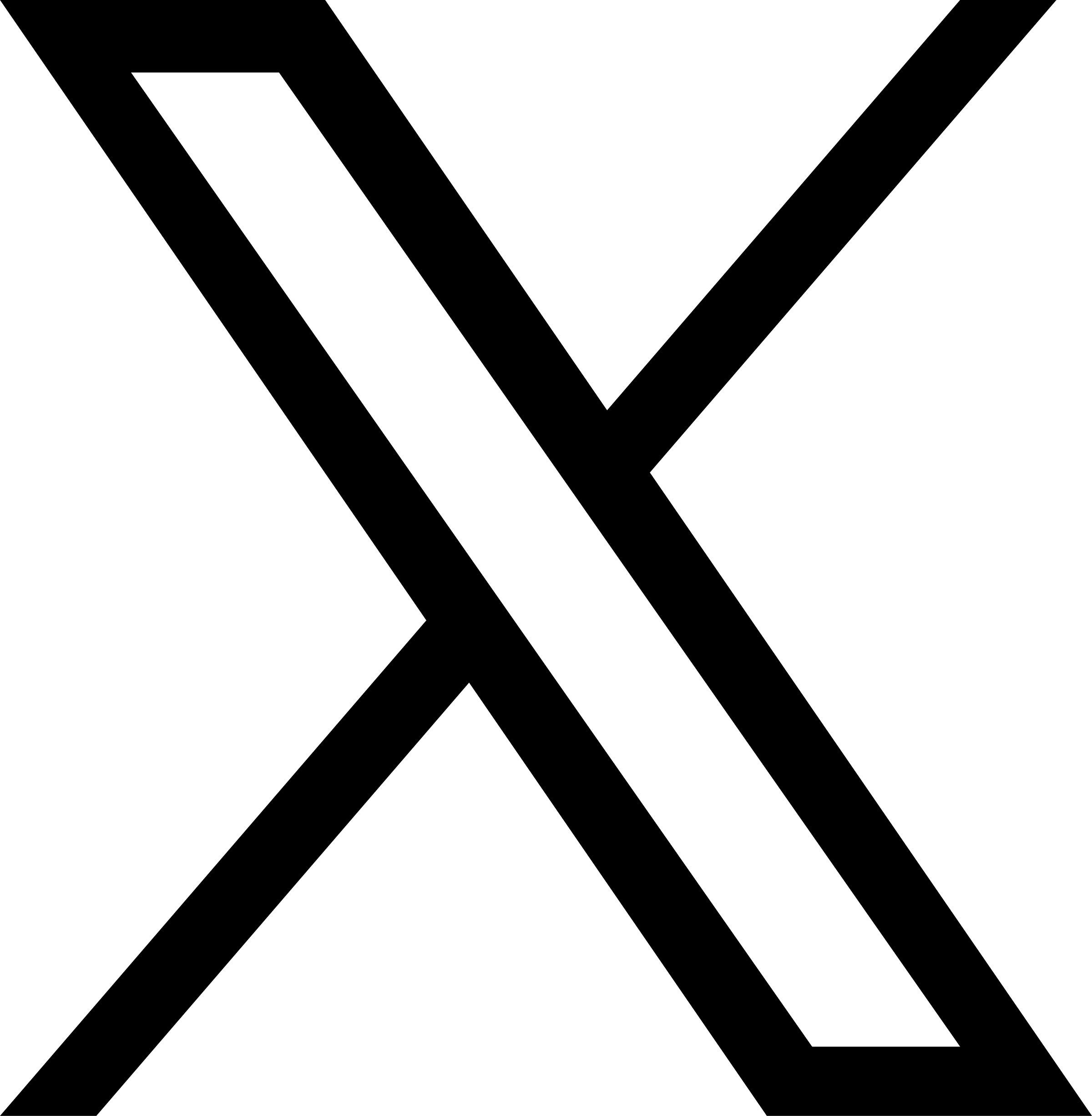
 Facebook
Facebook