此度は、土佐一条家のお話の続きでござりまする。
明応七年(西暦1498年)一条房家の嫡男として誕生した房冬は、永正七年(西暦1510年)に元服いたしますと、従五位上・侍従に叙任、その後も官位を進め、大永元年(西暦1521年)には従三位に叙せられて公卿に列したのでございまする。
土佐に在国したままの土佐一条家、代が変われば次第に一条宗家との関係もやはり少しずつ遠いものにはなってしまうもの。一条家が土佐にあって有力であり得たのは、決して単独で大きな武力をもっていたからではなく、京から離れてもなおその家格に見合う高い位を維持し、巧みな政の才をもって国人領主たちの盟主たる立場を築けていたことに起因するところが多くございます。そしてその有力な立場を以て、近隣の大勢力とも結んでいくという、外交政略に依るところ大でございました。
機を見るに敏で、政の才に長けていた房冬は、前関白一条教房の子でありながら、京におらず土佐在国ということ故に官位を進めることに時を要した父、房家の例を慮り、その溝を少しでも埋めるべく、自らは一条宗家、摂関一条家の当主であった一条冬良の猶子となったのでございまする。そしてさらに京とのつながりを深めることとして、房冬が公卿に列せられた大永元年(西暦1521年)には、房冬の正室にと内々定められておりました伏見宮邦高親王の王女・玉姫宮が降嫁のため土佐国に下向するのでございました。これには先代房家の頃からの働きかけが功を奏したであろうことは想像に難くないが、房冬が一条宗家当主たる一条冬良の猶子であったことも事が運ぶ大きな助けとなったのではないかと思われまする。尤も、如何に摂関家猶子とはいえ、名門皇族の姫宮が、京にはおらず、在国の公家へと降嫁するのはさすがに前例のないことと、眉を顰める者も少なからずであった様でございまする。
こうして、土佐一条家は『皇族の姻戚』という地位も手に入れ、ますます強まった中央とのつながりは、周辺大名家をして土佐一条家の存在を再認識させるものともなるのでございました。世は乱世に向かって実なる力が問われる様に移り変わりつつある時、権威だけでは覚束ないところも鑑みねばなりませぬ。大国の後ろ盾を得るべく、房冬は周防の大内義興の娘を側室に迎えるのでございますが、大内家にとっても、摂関家猶子たる房冬との縁組は、中央へのつながりを太くすることにつながり、相互の利害が一致するものでございました。
祖父教房の頃よりつながりのあった堺商人や山科本願寺との関係をより強固なものとすることにも心を砕いた房冬。明国との貿易を通じて利を上げ、堺商人や山科本願寺とのつながりも深かった大内氏とも姻戚関係となり、経済的恩恵も受けられる枠組みの中に土佐一条家を導いていったのでございます。
天文四年(西暦1535年)には、左近衛大将に任じられる房冬。しかしながら、左近衛大将と申さば京の帝が住まう御所の警護を司る近衛府の長、時の後奈良天皇もさすがに土佐在国の房冬を左近衛大将へということは当初肯んじられませんでした。しかし房冬は任官を諦めるどころか、人脈を使い、銭も惜しまず手を尽くして徐々に外堀を埋めていき、任官へといたるのでございました。
世の動きを見定め、つながりを広げる労を惜しまず、決して容易くはない舵取りが求められる時代に土佐一条家の主であった房冬。惜しむらくは父、房家亡き後、わずか二年で病没したと伝えられておりまする。享年四十四歳。天文十年(西暦1541年)霜月のことでございました。
房冬が病に斃れることなくば、歴史は大きく変わっていたのかもしれませぬ。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

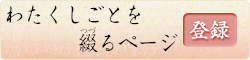
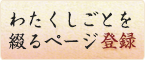



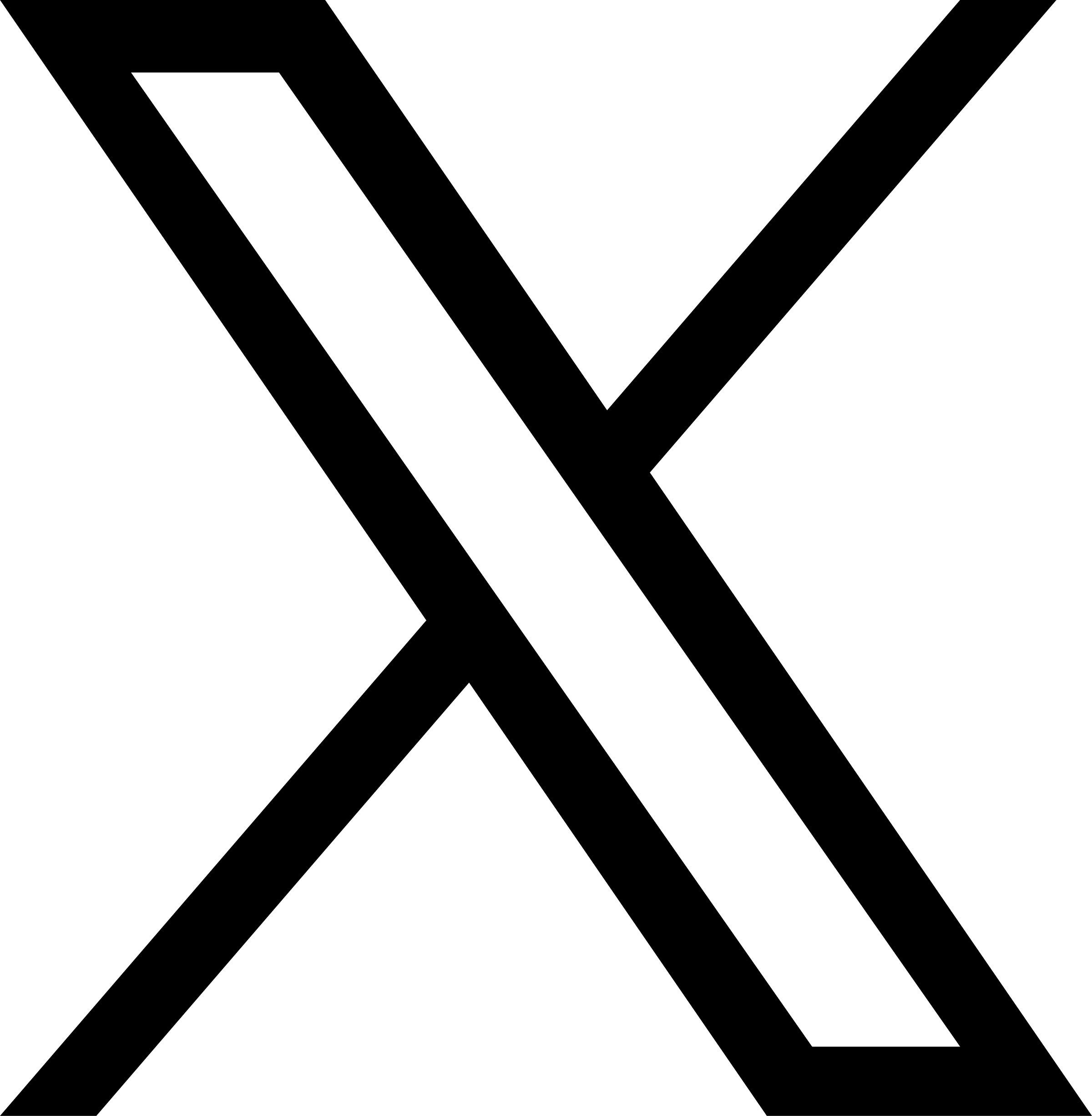
 Facebook
Facebook