前編では、藤原氏のルーツについてお話してまいりました。後編では、まさに時代の大きな流れの狭間に生き、語り継がれるべき藤原頼長卿のお話となりまする。
さて、このように興り朝廷の政を長きにわたり主導してきた藤原北家でございますが、悪左府と呼ばれた藤原頼長もまたこの藤原北家に生を受けた公卿のひとりでございました。保安元年(西暦1120年)、時の摂政関白太政大臣、藤原忠実の三男として生まれた頼長は、幼名を菖蒲若(あやわか)といい、『台記』(藤原頼長の日記)によれば、少年時代には父・忠実の命にも従わずよく馬にまたがって山野を駆け巡ったものの、落馬して一命を失いかねないほどの目に遭い、その後は心を入れ替えて学問に励むようになったと伝えられております。そして膨大な和漢の書を読み、やがては誰もが認める博識となったと言われております。元服し、着実な昇進を遂げ、保延二年(西暦1136年)には内大臣、右近衛大将を兼ねるまでになっておりました。
一方、氏長者として一族を束ねる立場にあった兄・忠通は後を継ぐ子宝に恵まれなかったため、天治二年(西暦1125年)にはまだ幼い弟である頼長を養子に迎えていたのでございました。しかし康治二年(西暦1143年)に実子・基実が生まれると、摂関の地位を自らの子孫に継承させようと望むようになった忠通は、父・忠実、また頼長と対立していくようになるのでございました。そのような中、久安三年(西暦1147年)、朝廷に左大臣、右大臣が空席である中、内大臣であった頼長が一ノ上卿(最上位公卿)として朝廷政務を掌握、摂政たる忠通を事実上凌ぐ勢いとなるのでございました。そして久安五年(西暦1149年)、頼長は名実共に最高位である左大臣へと進むのでございます。
時を少し遡りまして、世は白河上皇の院政時代、親政を目指す院の思惑により摂関家の力が弱められていく中で逼塞を余儀なくされてていた摂関家は、やがて鳥羽院政時代になり、頼長の異母姉・泰子が鳥羽上皇の皇后(異例中の異例として皇后宮に冊立された)となることで息を吹き返してくることとなるのでございました。
生後程なく祖父である白河法皇の下に引き取られて養育され、生後七ヵ月で立太子、後、父である堀河天皇の死後、わずか五歳で即位することとなりました鳥羽天皇、その治世は、幼帝の後見という形で、太上天皇たる白河上皇の院政が布かれた中での始まりでございました。
尤も、白河上皇が院政を布くに至った契機は、摂関家当主の師実、その嫡男・師通が相次いで亡くなったことで、まだ若年の忠実(頼長の父)が跡を継がざるを得なかったこと、さらには堀河天皇の早世により摂関家が天皇の外戚の座を失ってしまったことが重なり、権力が半ば然るべく集まってきたことによるとの見方が正鵠を射たものと言い得るかもしれませぬ。
永久五年年(西暦1117年)には、鳥羽帝のもとに白河法皇の養女である藤原璋子(待賢門院)が入内、鳥羽天皇の中宮とし、保安四年(西暦1123年)には、第一皇子に譲位させ崇徳天皇として即位させておりまする。これにより鳥羽天皇も鳥羽上皇となられたことになりますが、院政の実権は依然白河法皇(嘉保三年(西暦1096年)に出家のため)が握っており、実に四十三年間の長きにわたり院政を布き、政治的実権を掌握しつづけたのでございました。
白河法皇崩御の後、大治四年(西暦1129年)より、鳥羽上皇による院政が布かれることとなります。幼少の頃より白河院政の駒のようにされ、長きに亘り耐えてきた重石のようでもあった白河法皇の崩御後は、あたかも白河院政時代になされた決定をまるで巻き戻すかのようなことが行われているように見えるところがあるかと存じます。それは否定ゆえか、または策有りてのことか、はかり知り得るものではござりませぬが、少なからず否と言い、巻き戻せることを巻き戻すことで、その思いを現実のものとしたかったというところは無きにしも非ず、と申せますでしょうか。そのひとつが、白河法皇の勅勘を受け宇治に蟄居の身となっておりました前関白・藤原忠実(頼長の父)を呼び戻したことであり、その娘、すなわち上述の頼長の異母姉・泰子を入内させたことでございました。また、白河法皇の側近を遠ざけ、院の要には自己の側近を据えるなどは、いつの世も行われることではございますが、伊勢平氏の平忠盛(平清盛の父)に内昇殿までをゆるし、政権に近づけることも行われたそうでございます。かつて地下人(じげびと)と呼ばれ、公卿の命で戦いをする役割であった武士が、その看過しえぬ実力をもって朝政にも影響を及ぼし始める大きな区切りのひとつでございました。尤も、その素地となる北面の武士(院御所の北側の部屋に詰め、上皇の身辺警護や供奉を司った武士)は、白河法皇が創り調えたもので、既に時代の変化により必要とされるものとなっていたのかもしれませぬ。また寵愛は、白河法皇の後ろ盾を失った藤原璋子(待賢門院)から、藤原得子(美福門院)へと移っていきました。尤も、中宮・藤原璋子(待賢門院)は、幼き頃より白河院の養女となって溺愛されておりまして『古事談』によれば、鳥羽院は、第一皇子である崇徳天皇のことを「叔父子」(祖父・すなわち自身の子ではなく白河院の子)と呼んでいたとされておりますこともあり、白河法皇という重石がなくなった時に、寵がうつるのもまた致し方ないところであったのかとも思われまする。
何はともあれ、鳥羽院政下において、摂関家も、内にまとまりを欠いたままではあったにせよ総じて力を盛り返してくることができたのでございまする。しかしながら崇徳天皇に譲位させ、齢三で即位した近衛天皇の元服(久安六年(西暦1150年))に合わせ頼長の養女・多子が入内すると、兄・忠通は藤原伊通の娘・呈子を養女に迎え、鳥羽法皇に摂関家の娘でなくば立后できない旨を奏上、もはや忠実・頼長と忠通との亀裂は如何にしても繕い得るものではなくなってしまったのでございました。事実、これに立腹した忠実は、摂関家の財を忠通より接収し、また氏長者の地位をも剥奪しこれを頼長に与え、忠通を義絶してしまうのでございました。
鳥羽法皇はこれら一連に敢えてあまり深く関与はせず、曖昧とも言える立場でしたが、何にせよ左大臣であり、氏長者ともなった頼長は、政に意欲高く取り組み、取分け学術の再興と綱紀粛正を目指したと伝えられております。後に悪左府と呼ばれることになるのは、その苛烈で妥協を許さない性格からのものであり、『悪』という語が、元は剽悍さ力強さをも表す言葉として使われてきたことに由来するものと考えられております。しかしながら、実際の慣例や個々の事情などよりも、律令や儒教の論理をはるかに重視し、苛烈に事にあたっていく頼長の政は周りに理解者を減らし、院近臣である中・下級貴族からの反発を招き孤立を深めていくこととなってしまうのでございました。そしてその苛烈さゆえに周囲との衝突を繰り返す頼長は、綱紀粛正の動きの中で結果的に寺社勢力との対立も深めてしまい、政の有り方を正そうとする思惑に基づく行動は、却って頼長の対立者を生み出してしまうことの方に、よりつながってしまうのでございました。
久寿二年(西暦1155年)近衛天皇の崩御に伴い、皇位継承者を決める王者議定が開かれることになりましたが、この時期、頼長は妻の服喪のため出仕できておらず、また王者議定とは申しましても、その実は権大納言 三条公教が主導し、鳥羽法皇、関白 藤原忠通、久我雅定ら少数と密かにはかり、後継を定めてしまうというものでございました。当初、崇徳上皇の第一皇子である重仁親王が後継と見られ、父である上皇もそれを望んでおりましたが、崇徳上皇が藤原頼長と結んで先の近衛天皇を呪殺せしめたとの噂がまことしやかに宮廷内でささやかれ、それが鳥羽法皇の逆鱗に触れ、重仁親王は皇位継承の道から遠く退けられてしまうのでございました。代わって、生母が出産の後に急死したことで、祖父にあたる鳥羽法皇が引き取り、その后たる美福門院に養育され、僧侶となるため九歳で覚性法親王のいる仁和寺に入っていた孫王に目が向けられることとなりました。これがやがて皇位を継ぐことになる守仁親王(後の二条天皇)でございますが、如何にしても幼少であったこともあり、且つ実父も存命であるものを、それを飛び越えての即位はさすがに如何なものかとの声も無視できず、守人親王即位までの中継ぎという形で、その父、雅仁親王が立太子もせぬまま即位することとなったのでございます。それこそが第七十七代天皇、後白河天皇でございました。尤も、この突如として雅仁親王を擁立する運びとなった裏には、雅仁親王の乳母の夫であった信西の策動があったと言われておりますが、定かなところは知る由もなきことにございまする。しかしながら、ここに権力をめぐり激しき政略戦が繰り広げられ、その中で内覧としての立場も奪われた頼長は失脚に等しい状態とされていたのでございます。
その翌年、保元元年(西暦1156年)二十八年の長きにわたり院政を布いた鳥羽法皇の崩御を機に、それまで薄氷の下を流れていた水が亀裂からほとばしるかの如く事態は動き始めるのでございました。世に言う保元の乱でございます。保元の乱につきましては、他に事細かく述べられているものも多く存じますので、ここではそのあらましに触れるのみといたしまするが、「(崇徳)上皇と左府(藤原頼長)同心して軍を発し、国家を傾け奉らんと欲す」という風聞により謀反人の烙印を押され、嵌められた形ではあれど対せねばならぬ状況へと頼長は追い込まれていくのでございました。平氏源氏の武士を動員し、武力の上で優位にたつ後白河天皇陣営は、形の上でも官軍であり、それに対して事ここに至りては挙兵するより外ない頼長は、挙兵の大義として崇徳上皇をいただいて臨むこととせざるをえなかったとも言えましょうか。摂関家の私兵がほとんどを占める中、武士で上皇方に参じていた源為朝が夜襲を献策するも、頼長はそれを退けたと伝えられております。興福寺の悪僧集団など大和からの援軍を待ち、夜が明けてから相対するということに軍議は決した様でございますが、悲しいかな頼長は政の知見は豊かでも、軍の駆け引きに通じた人ではなかった様でございます。このような常ならざる時、人は平時の儀礼や日頃のあるべき姿といったものを敢えて忘れ、敵を退けることをこそ考えねばならぬものかと存じますが、頼長にはそこまで割り切ってしまうことはできなかった様でございます。時を同じくして、後白河天皇陣営でも夜襲が献策され、逡巡する藤原忠通(頼長の兄)を信西、源義朝(源頼朝の父)らに押し切られ、夜のうちに攻めかかることで決したのでございます。平清盛率いる三百余騎、源義朝率いる二百余騎、そして源義康(足利氏の祖)率いる百余騎が京の大路をそれぞれ進み寅の刻(午前四時)に上皇方との戦が始まったと伝えられております。一進一退の攻防が続くも、やがて放たれた火が白河北殿にも燃え移り、上皇方は総崩れとなってしまうのでございました。
落ち延びる際、源重貞の放った矢を頸部に受けた頼長は、出血による衰弱に苦しみながらも逃亡を続け、末期の望みとして奈良に逃れていた父、忠実に今際の対面を望むも拒まれ、失意のなかで絶命したと言われております。
時代の流れではございましょうが、朝廷での権力争いが、武士の力をも巻き込んでこのような形でひとつの結末を迎えました保元の乱、やがて世は着実に武士が力を持つ時代へと移り変わっていくのでございました。
頼長の死後、長男の師長、次男兼長、三男隆長、四男範長は、乱を起こした父頼長と連座させられる形で、いずれもが官位剥奪の上配流とされてしまいました。長子の師長は、後に許されて京に戻り、内大臣にまでのぼり、やがては従一位・太政大臣にまで昇っておりますが、他の三人は、そこから戻り返り咲くことはできませんでした。頼長は、生前、彼らに、学問を決して疎かにせざることを諭してきたと言われております。家風として、学問を重んじ、それによって得た知見を政の中で活かし、国を支えることの意を教え伝えていたのではないでしょうか。
世が移り、再び藤原摂関家が日の本の政全てを動かす時が再び来ることはなくなれども、続いて到来する長きにわたる武家支配の世にあっても、藤原北家流に連なる摂関家は、五つの家(近衛家・鷹司家・九条家・二条家・一条家)即ち五摂家に分かれて、脈々と続いていくのでございます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

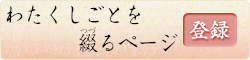
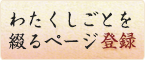



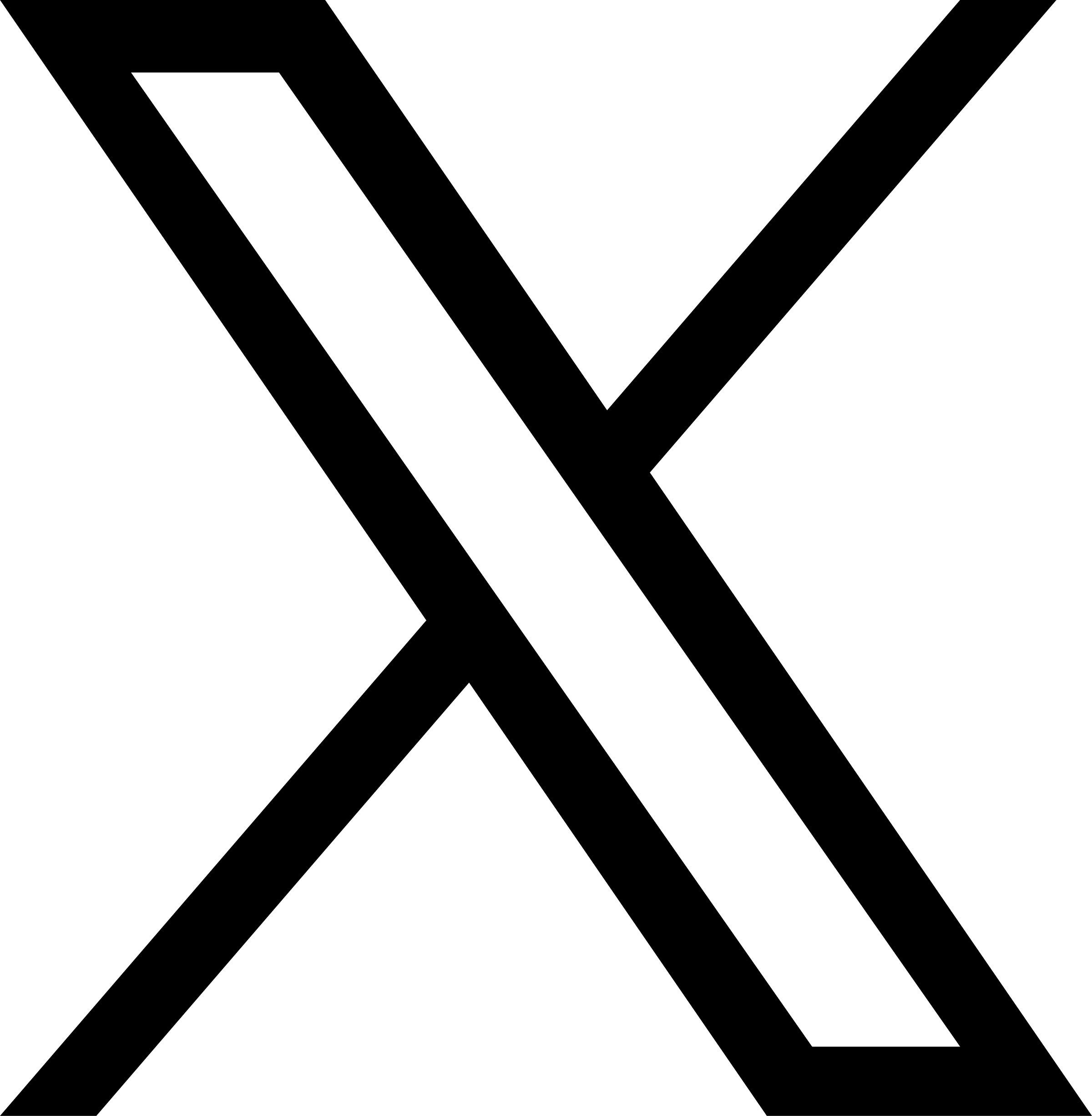
 Facebook
Facebook