悪左府 藤原頼長 保元の乱と武家政権の基
さて、前回、左大臣の登場により血筋によってのみ与えられた権威を振りかざす一条三位も、ぐうの音もでなくなってしまった場面をお話いたしましたが、律令制下の朝廷において最高行政機関たる太政官の最高位が左大臣でありましたことはお伝えしたとおりでございます。今回は、そんな左大臣を任じられた方々の中でも、悪左府と呼ばれた平安末期の左大臣・藤原頼長卿について少しお話できればと存じます。
因みに『左府』とは、左大臣の唐名のことでございますが、府にはもともと古代中国において官物や財貨を収蔵した蔵という意味がありました様で、やがてその蔵が立ち並んだ場所が重要拠点として政を執り行う場となり、延いてはその長を言い表す言葉となっていったためではないかと考えられます。
左大臣 藤原頼長についてお話する前に、皆さまご存知の藤原氏について、時代を遡ってみたいと思います。
藤原一族の中でもよく知られた方と言えば、平安中期に、その権勢並びなきと言われた藤原道長が挙げられますでしょうか。天皇外戚となり、摂政として政の実権を掌握、祝宴の席での即興の歌『この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 虧(かけ)たることも なしと思へば』はその権勢並びなきことを後世につたえるものとしてよく知られたものでございます。
悪左府、藤原頼長も大きな流れとしては、その道長と同じ藤原北家の流れを汲む貴族でございました。
ではそんな藤原一族はそもそもどこからやってきたのか、と申しますれば、さらに時を遡りまして飛鳥時代、大化の改新にて中大兄皇子(後の天智天皇)を支え、政権の中心的立場として、それまでの豪族中心の政から、唐の律令制に倣い、天皇中心の中央集権国家体制をつくり上げる基を築いた、藤原鎌足まで行きつくことになります。その始まりは、皇極天皇四年(西暦645年)のことでございました。大化の改新以降、天皇という呼称が正式なものとなったと伝えられておりますが、各地に豪族が濫立し、広大な私有地に対して公に支配力を持つ中では大王(おおきみ)を中心としつつも、実質的なところはおろか、形式的にもまだまだ諸勢力の集合体であるところに留まったままであり、統一国家としてより大きな力を示すことは事実難しいことでございました。申すまでもなく、それまでの伝統に基づく氏族制をいきなり廃してしまうことによる混乱は避けなければならず、ゆえに少しずつ、我が国の在り様を鑑みながらも律令制を採り入れていき、真に天皇を中心とした中央集権国家へと制度を整え始めたというところでは、国が国として成るための大きな変革のはじまりであったと申せますでしょうか。
早くから中国の史書に高い関心を持ち、遣唐使として留学していた南淵請安に学び、国家の有り方というものを改革の旗手として進めていきました鎌足ですが、最初から藤原であったわけではなく、神事を司る中臣氏でありました。中臣鎌足として改革を進め、天智天皇の信任も厚かった鎌足は、落馬して療養する中、天智天皇が見舞い、その際に大織冠の位と、藤原の氏を賜り、その翌日に身罷ったと伝えられております。鎌足五十六年の生涯でございました。大織冠の位は大化三年(西暦647年)に制定された七色十三階冠の制における最高位であり、史上、大織冠となったのは藤原鎌足の他にはおりませんでした。また、この時賜った藤原の氏は、鎌足が大和国高市郡藤原(現在の奈良県橿原市)の生まれであることによるとも言われております。家々が氏を単位として結合し、氏族として朝廷を支える支配階級の構成単位でもございました。そのことからも新たに氏が作られるということは、どれだけ大きな意味を持つものであったかを伺い知ることができるかと存じます。
こうして天智天皇の治世、国家の功臣として大きな力を持つにいたった鎌足の一族ですが、鎌足亡き後は、一転不遇の時期を迎えることになります。鎌足の子、不比等(史)は、幼くして父を亡くし、鎌足の死後中臣氏の中心的存在であった右大臣 中臣 金が、天智天皇の後継争いである壬申の乱において、天智天皇の子、大友皇子方として敗れ処刑されるに至り、勝者たる天智帝の弟、大海人皇子、すなわち天武天皇の治世には、乱とは無関係であった鎌足流も不遇の時代を迎えることとなったのでございます。金をはじめとする中臣氏の有力者が近江朝(大友皇子)方として処断され、朝廷の中枢から一掃されてしまった天武天皇の御代、天皇親政の下、時代は大きく変化を続け、官制もまた大きく改革されます。広く優秀な人材に官途をひらくべく、宮廷に仕える者をまず大舎人とし、その後才能を見極め官職につける制度となりました。世を鑑み、一から始めることも厭わぬ史(不比等)は官途に就くべくこの新制度下で歩み始めるも、後ろ盾を持たない不比等にはいつまでたっても道が拓かれないどころか、ただ鎌足の子として視られ退けられたまま時が過ぎていくのでした。しかしながら、不比等はこの時を無為には過ごさず、勉学に勤しみ、来るべき律令制国家時代において必要とされる知識を誰よりも多く身につけていくのでございました。また、ただ待つだけではなく、伝手と人脈づくりにも腐心した不比等は、天武帝の治世後期には、従兄弟の中臣大嶋と共に草壁皇子(天武天皇と皇后・鸕野讃良皇女(後の持統天皇)の皇子)に仕えていたと伝えられております。
忍耐強く、慎重に着実に動いた不比等に、やがて次の持統天皇(天武天皇皇后)の時代、転機が訪れるのでございます。天武天皇薨去に際し、後事を託された皇子と皇后でしたが、皇子の年なども鑑み、皇后自らが天皇の位につくこととなるのでした。草壁皇子に仕えながら、その立場に加え、政をはじめとする幅広い知見を以て持統帝の信頼を得ていく不比等でしたが、生まれつき病弱でもあったと伝わる草壁皇子は、その後皇位につくことなく持統天皇三年(西暦689年)二十七歳の若さで薨御されてしまうのでございました。当時、皇位継承に関して直系継承などの定まり事は未だなく、皇族の中からその出自、地位や力により次の天皇が選出されておりました。おそらくは母の身分の高さをはじめ幾つかの条件が揃ったことですでに立太子されていた草壁皇子でしたが、それが即ち、皇太孫にあたる皇子の子、軽皇子の皇位継承を何ら確かなものとすることにはつながらなかったのでございます。しかしながら我が子であり、やがて皇位を継がせるべく慈しみ、時と場を整えてきた草壁皇子を亡くした持統天皇の想いは、草壁皇子の子、己が孫にあたる軽皇子へと自然注がれることになり、何とか軽皇子に皇位を継承させたいと願うようになっていったのは、何ら不思議なことではなかったかと思われます。ここで持ち前の優れた観察眼と智慧を活かし、軽皇子(後の文武天皇)の擁立に尽力した功績は大きく、また卓越した政の知識を以て大宝律令編纂においても中心的な役割を担うこととなった不比等は、その影響力を政治の表舞台へと及ぼしていくのでございました。さらに、軽皇子の母たる阿閉皇女(後の元明天皇)に仕えその信任厚く、細やかな心配りだけではなく、政治的な視点においても優れたものを持っていた女官と伝わる県犬養三千代(あがたいぬかいのみちよ)との関係と力添えは、不比等が皇室との関係を深めていく上で大きなものとなるのでございました。尤も、力をつけてきたことで皇族たちの目もまた彼らから見て危ういものとして不比等に向けられることになります。一つ段を踏み誤ればすべてが崩れてしまうような中、慎重さを重ねても重ねすぎることはないくらいに、地歩を固めていったのではないかと思われるのでございます。さて次に不比等は、やがて皇位を継承する軽皇子と自身の娘との距離を近づけていくことに心を砕くのでございますが、後に、天皇の外戚となることで実権を握る摂関政治の基は、不比等がこのような思いの中で築き始めたものでございました。しかしながら、この時代には、皇后、妃となることができるのは皇族出でなければならず、たとえ如何に信頼を得、位を得たとしてもなお、不比等にできるとすれば、己が娘を皇后、妃より位の劣る天皇の夫人とさせることまででした。即ち、側室にはなれても正室にはなれない、ということとなりますが、では天皇の位についた文武天皇(軽皇子)が、皇族の中から妃を迎えず、夫人しか迎えなかったとしたらどうなりますでしょうか。その時には、夫人が皇子を生めば、その皇子が皇位を継ぐことになります。皇位を他の皇族ではなく天皇の子が継承していくものという流れを形づくってきたことがここで意味をもつのでありますが、いにしえのことにて、定かなことは推しはかるより外はございませぬものの、時の流れが味方をしたものか、不比等が遠大な思いの中でこのような流れをつくり上げていったものなのか、誰にとって最も益のあることであったのか、ということから伺い知るばかりとなりますでしょうか。
果たして不比等の娘、藤原宮子は即位した文武天皇(軽皇子)の夫人となり、文武天皇には他にそれより位の劣る嬪はいても、皇后、妃を迎えたという記録はなく、文武天皇と宮子の間に生まれた首皇子が、やがて聖武天皇として即位することとなるのでございました。
さらに不比等は橘三千代(県犬養三千代)との間にもうけた娘、安宿媛(光明子)を首皇子に嫁がせます。養老四年(西暦720年)不比等は六十二年の生涯を閉じることとなりますが、光明子は不比等の死後、力を合わせた不比等の息子たち藤原四兄弟により光明皇后となり、皇族ではない立場からの立后の先例を開いたとされております。
藤原氏を新しい律令制国家の政の中枢へと導き、神事を司る中臣氏とは一線を画す立場に位置付けんとした不比等の意思により、藤原氏は不比等とその子孫にのみ許され、他の一族は再び中臣氏たることとされたのでございますが、政を律令制という、制度として動くものへと進めていくこと、それは、政を前時代的な神権政治から脱却させ、次の形へと変えていくことの必然性と、それに欠くべからざる学問を重んじた不比等の姿勢なくしては得られぬものであったかと思われるものでございます。
不比等亡き後、武智麻呂(むちまろ・藤原南家開祖)、房前(ふささき・藤原北家開祖)、宇合(うまかい・藤原式家開祖)、麻呂(まろ・藤原京家開祖)の四兄弟がその遺志を継いていくのでございますが、その道のりは決して平坦なものではなく、幾多の政敵との争い、また時には一族内での争いの歴史でございます。時は流れ、嵯峨天皇の時代に、帝の信を得た当主冬嗣が朝廷内での力を伸ばし、冬嗣より三代続けて北家嫡流が外戚の地位を保ち続けることができたことにより確固たる地位を築きあげ、先述の藤原道長、そして頼道の時代の全盛期へとつながっていったのでござりまする。
次回後編では、悪左府 藤原頼長の時代のお話へとつづきまする。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

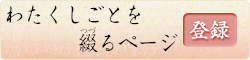
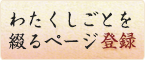



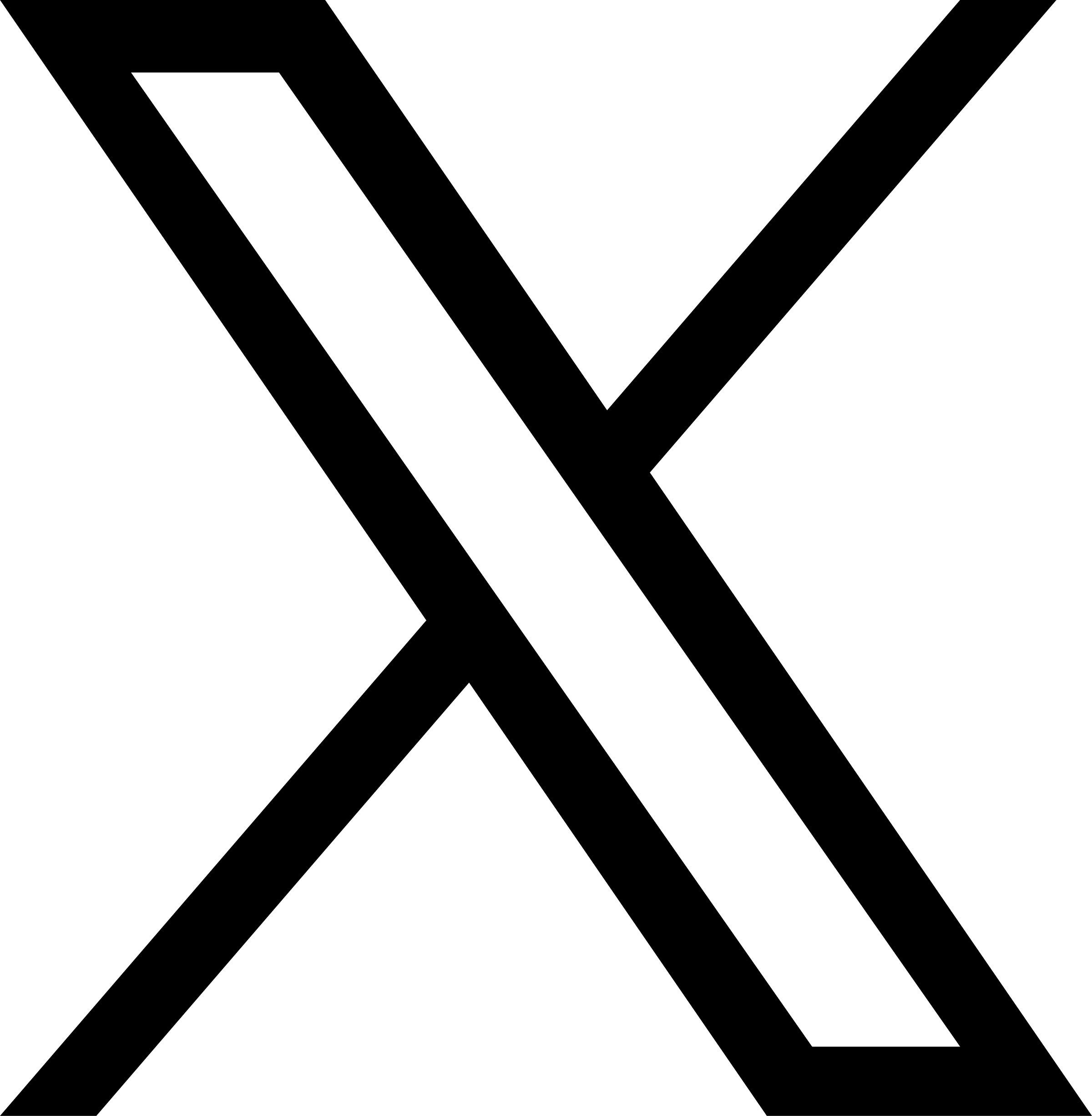
 Facebook
Facebook