こうして伊勢を固めた親房は、各地に散っている南朝方の有力武将たちとの関係強化に努めていくのでございます。南朝方主力であった新田義貞の一族や楠木正成の遺児・楠木正行、また吉野を本拠とする後村上天皇を奉じる公卿らとの間で書状を交わし、各地に散った南朝方の勢力を結びつけるために奔走したのでございまするが、人の心こそが世を導く柱となることを深く知る親房の思いが歩みを止めさせぬものとなったのでござりましょうか。
縦しんば数で勝ることができたとしても芯に柱なくば烏合の衆と何ら変わらぬもの。心の柱とも成り得るものなくしては、との強き思いから親房は延元四年(西暦1339年)には伊勢・阿坂城に籠り、『神皇正統記』の執筆を進めていくのでございました。守るべきは「帝の正しき統(すめらぎのすじ)」そこに記すところの皇統譜は、天照大神より始まり、代々の天皇がいかに国を守りて今日に至ったか、そして両統迭立の混乱の中にありて何故に大覚寺統、すなわち南朝こそが正統たるかを、魂を込めて説いたものでござりました。
同年、延元四年(西暦1339年)長月(9月)には、後醍醐天皇が吉野の地にて崩御、南朝はその精神的柱を失いながらも、如何にしても思いを伝えんと強く欲する親房の心は、その深い学識に支えられた強き思いの宿った文となり、伊勢に集った武士や社家のみならず、遠く吉野に籠る公卿らの心も励ますものとなり、「南朝の心の一本柱」となっていくのでございました。
後醍醐帝の崩御をうけて南朝を継ぐ形となった若き帝、後村上天皇(後醍醐帝皇子・義良親王)を支え、守り導くことを己が残る生をかけてなすべきことと定めた親房でございましたが、足利方の優勢たること明らかな中で、実に十余年にわたり南朝方が足利方に抗しえたのは心の柱を渡し得たが故であったと申せましょう。後村上天皇を守り支え導き、南朝の柱石となった北畠親房でしたが、正平十三年(西暦1358年)弥生、大和国賀名生行在所にて七十歳の生涯を終えるのでございました。後村上天皇、そして参集した公卿・武士ら皆誰もが深く喪に服し、「南朝の大黒柱、ここに倒る」と嘆いたと伝わっておりまする。
その生き様はまさに心と理の柱。それこそが南朝をまとめ、苦難の時をも乗り越えさせる力を人々に与えてきたのでございまする。魂の書、『神皇正統記』もまたその現れのひとつであり、後々の世にまで伝えられていく形を成したひとつであったのかもしれませぬ。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

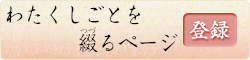
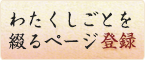



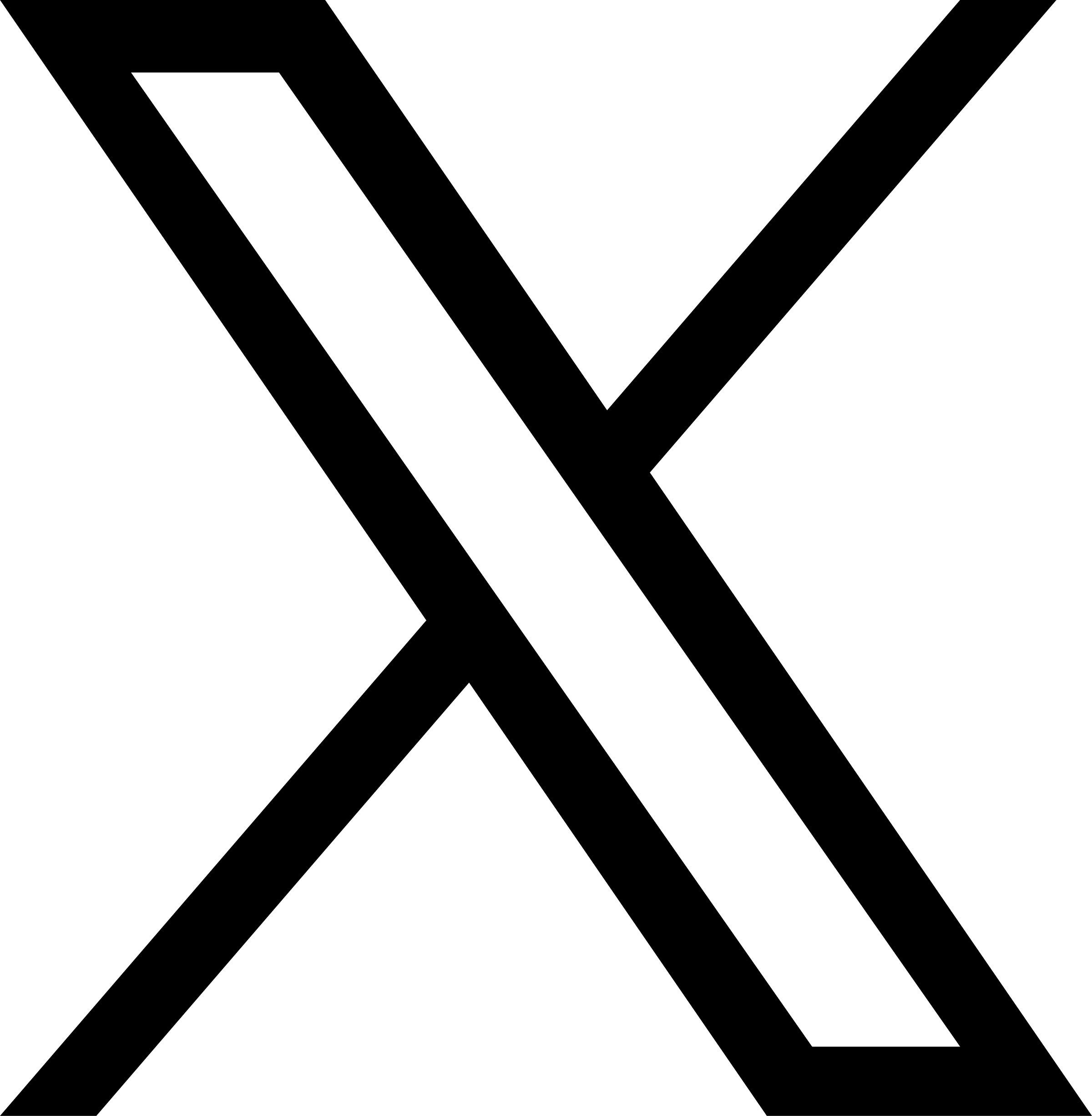
 Facebook
Facebook