南朝の志を武において、皇統を守護する力のあるべき姿というものを体現することは、北畠顕家という存在を中心としてはじめて成し得ていたと申しても過言ではございませぬ。政を司り、力の行使は武士に委ねてきた公卿たちは、武官に任じられてはいても武人には非ず、となり、また臣籍降下により武士となっていった者たちもそれぞれの土地で武士として生きる道は容易いものではなく、その土地にしっかりと根を下ろしていくより外はなかったのでございます。世が乱れる中、皇軍を皇軍たらしめ率いることが求められはしても、成し得るか否かの容易ならざるを誰よりもよく分かっていたのは、顕家の父、北畠親房であったやもしれませぬ。
南朝を遠く陸奥の地より、政を正しツワモノを糾合し支え続けた嫡男・顕家の存在は東西に広がる日ノ本全体の政を見据えた時にも大であり、余人を以て代えがたい鎮守府大将軍落命の報は、幾重にも親房を嘆きの淵へと追いやるものでございました。然れども陸奥から神速の強行軍で武門の集団たる足利方を幾度も蹴散らすほどの武威を見せた顕家率いる軍はもはやなく、南朝方は俄かに力を失い、足利尊氏の勢威は京畿一円を覆い尽くすほどでございました。南朝の諸将も疲弊し、もはや帝を支えるべき人々の心の中にも覆い得ぬ動揺と不安が広がっていくのを止める術すら尽きんとしている様相でございました。然りながら帝を奉じ、正統を繋がんとする南朝の灯を絶やすわけにはまいりませぬ。己までもがただ悲しみの中に身を措き、嫡男顕家がその若き命を賭してまで守り抜かんとしたものを如何で棄て措くことができようや、と伊勢の地に腰を据え南朝再興の基を築く決意を固めたのでございました。
伊勢国は、代々北畠氏の根拠地にして東国と畿内とを結ぶ要衝の地でございました。親房はまず後醍醐帝の勅命を携えて伊勢の豪族・地侍たちのもとを巡り、その心をひとつひとつ結び付けるべく働きかけていきました。北畠氏の家人である大河内氏や度会氏は無論のこと、伊勢国司や神宮の外宮・内宮の社家に至るまで、文字通り一人一人と真摯に向き合い、語り、説いていくことで南朝の足元の力を養っていったのでございます。
就中伊勢神宮の神職層からの支えは重きをなすものでございました。伊勢は「天照大神の御代」から続く皇統の象徴といえる地であり、伊勢神宮との結びつきはその神威を以て「南朝こそ正統である」と云わしめることにも等しき意をもつものであったためでございます。故にこそ親房は神宮の祭祀や年中行事に自ら参列し、朝廷と伊勢神宮の結びつきをここで改めて世に知らしめることで南朝の正統性を訴えたのでございます。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

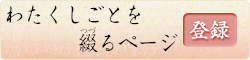
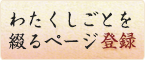



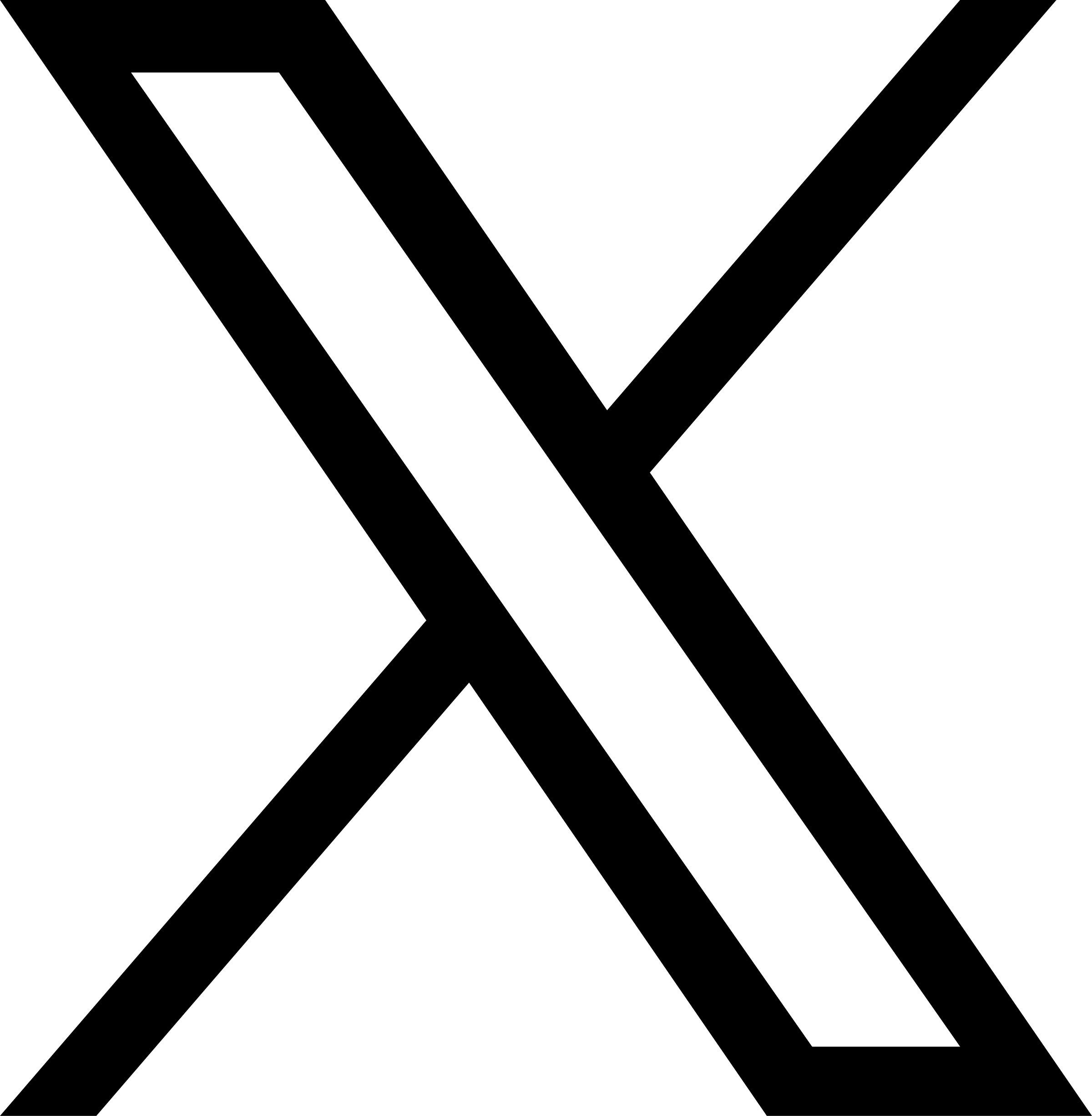
 Facebook
Facebook