その年の弥生(3月)二日、権中納言へと任官した顕家は、軍勢を率い下旬までには関東から以北にかけての足利方を掃討すべく奥州へと軍を返しておりまする。帰途、相模国片瀬川で足利方の斯波家長が顕家の軍を妨げんとするも卯月(4月)には顕家勢がこれを撃破、次いで皐月(5月)には相馬氏を破り、奥州帰還を果たしてございます。尤も、この頃には九州に落ち延び、勢力を立て直した足利勢が軍を東進。播磨で赤松円心を攻めあぐねている新田義貞と兵庫で合流し足利勢を迎え撃つことを命じられた楠木正成は、既にして劣勢の中善戦するも、水軍を整えられなかった南朝方の不利さもあり、さらには新田勢とも分断され、打ち減らされながらもなお奮戦し足利勢を跳ね除けた後、ここが最期と正成らは自害いたしました。歴戦の武将であり、攪乱戦で相手を翻弄する手段を得意とし、洞察力に長けた、南朝を支えた名将のひとり、楠木正成を失ったことは、武家集団である足利方と違い、真に兵を率いて敵と渡り合えるだけの力量をもった将の少なかった後醍醐陣営にとっては代えようのない大きな損失でございました。顕家らの強行軍を以てして京を奪還、尊氏を九州まで落ち延びさせた折、帝は正成の『状況が宮方に有利な今のうちに足利方と和睦をする』という進言も容れず、また九州で勢力を盛り返した尊氏方の東進に際しての『京中で尊氏を迎え撃つべき』という進言も容れなかったのでございます。もし、帝や周りの公卿に少しでも状況を見極めることのできる誰かがいれば、或いは歴史は変わっていたやもしれませぬ。
京は再び足利方の手に落ち、帝は新田義貞とともに比叡山へと逃れたのでございます。
延元二年/建武四年(西暦1337年)睦月(1月)父・北畠親房より伊勢への来援を求める書状が、また時を同じくして後醍醐帝からは京奪還の綸旨が相次いで顕家の下に。
ただ、新たに移した陸奥国府である霊山城もまた足利方に囲まれており、顕家もおいそれと軍を進発させることができずにおりましたものの、葉月(8月)十一日、義良親王を奉じ霊山城を進発、上洛するために再び南下を開始する顕家の兵は、奥州五十四郡から招集され、その兵数実に十万余騎とも伝わる精鋭揃いでございました。
兵を進めるに際し、やはりどうしても再度陥としておかねばならぬのは鎌倉。先ず葉月(8月)十九日、白河関を越え下野に入る顕家軍は、伊達行朝、中村経長の両軍を中心に、師走(12月)八日には足利方であった小山城を陥落、小山朝郷を捕える。そのまま足利方の大軍を、師走(12月)十三日に利根川で、同十六日には安保原でそれぞれ破り、足利方であり、かつて楠木正成をもって『坂東一の弓取り』とまで言わしめたほどの武勇の持ち主、下野宇都宮家当主の宇都宮公綱を陣中に迎えることにも成功しておりまする。その勢いを駆って、神速で鎌倉に攻めかかった顕家率いる軍勢は師走(12月)二十三日、鎌倉に攻め寄せ、翌日には鎌倉の攻略を全きものとしたのでございました。この折、因縁浅からぬ斯波家長は討ち取られ、足利義詮・上杉憲顕・桃井直常・高重茂らは鎌倉を捨て房総へと逃げ落ちる始末でございました。
破竹の勢いを示す顕家の下には味方する者もまた参ずるもの。僅かの間に兵馬を整え、翌延元二年/建武四年(西暦1337年)睦月(1月)二日には鎌倉を進発、十二日には遠江国橋本、そして二十一日には尾張国に入り、翌日に黒田宿へと至る速さでの西進でございました。
対する足利方も守護らをかき集めた軍勢を組織し抗うも、睦月(1月)二十八日までには顕家率いる軍がこれを美濃国青野原の戦いで徹底的に打ち破り、一時は総大将の土岐頼遠の姿が見えず行方知れずの騒ぎとなるほどの大きな損害を足利方に与えたのでございました。しかしながらさすがに足利方の層も厚く、この戦いによる兵の減少や疲弊度合を鑑みた顕家は、そのまま京へと進むことをあきらめ、如月(2月)には一旦伊勢国に退く形をとっておりまする。
世の動きを見るに敏なのは生き残りをかける武家にとって理の当然でございまする。一族郎党を養うための領地を守る、その領地をまもってくれるのは誰なのか…、理想や官位では食い扶持にはならぬ、と誰もが世の実態を見据える中で、足利方には二の手、三の手を打てるだけの力の層と連携とがそなわり、兵站もまた然り、十重二十重に包み込んでいくような力が備わりつつある一方、如何に戦場での強さで譲らず、信念をつらぬいた戦いを続けていようとも、本拠地を遠く離れての連戦、堪えぬ筈がありませぬ。
その後の畿内における戦いでは、依然精強さを見せる顕家の軍ではございましたが、さすがに連戦連勝とはいかなくなり、援軍のあてもなきまま、苦しい戦いを続けざるを得ない状況となっていくのでございました。この戦いの中にあって、顕家は後醍醐帝に対し、皐月(5月)十日に東国経営の上奏文を草し、さらに同十五日には諫奏文を上奏しておりまする。
伝わるところによれば、
一. 地方分権を推進すること
二. 諸国の租税を免じ、倹約を専らにすること
三. 官爵の登用を慎重にし、能力には官位を、成果には恩賞を以て報いること
四. 月卿雲客僧侶等の朝恩を定め、公卿・殿上人・仏僧への恩恵を公平にすべきこと
五. 奢侈で衰退滅亡することなき様、臨時の行幸及び宴飲を閲かるべきこと
六. 法令を厳にせらるべきこと
七. 政道の益無く寓直の輩を除かるるべき事、即ち、貴賤に関わりなく能有るを用い、血筋だけで高位にあるを退けること
を切々と奏し、真摯に国を憂う心で帝を諫め、跋文も古今の例えを用いながら格調ある漢文にて帝に如何にしても想い届けんと、帝より与えられた大任と大恩を謝し、その上で帝自らが政の非を改め、世を正しく導いていかれることを願い、もしそれが叶わない時には、自らもまた官職を退き隠者となる旨、悲壮なまでの覚悟を以て奏しているものでございました。
和泉の国で戦線を繰り広げていた顕家でしたが、足利方からその討伐に向かうのは高師直。諫奏文の上奏から七日後、堺浦で激突となった両軍。顕家軍は残された力を振り絞り戦うも連戦の疲労に加え、足利方についた瀬戸内水軍の攻めもあり苦境に立たされ、ついには劣勢に回り全軍潰走となってしまうのでございました。
もはや供回り二〇〇騎を数えるほど。顕家は最後まで戦い続け幾多の敵兵を討ち果たしますが、落馬し、ついには討ち取られるのでございました。享年二十一。文に武に秀で、そして何より人を思い、心を掴む将器をもった若武者の、早すぎる、そしてまた清らかとさえいえる最期でございました。南朝の希望を一身に背負った北畠顕家。その生は短くとも、果てしなく高き志を以て世を変えんと奔り続けた生き方は、一筋の馬尾雲のようにはっきりとした軌跡となり、人々の心に刻まれるものでございました。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

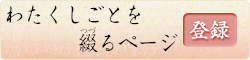
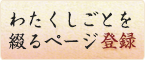



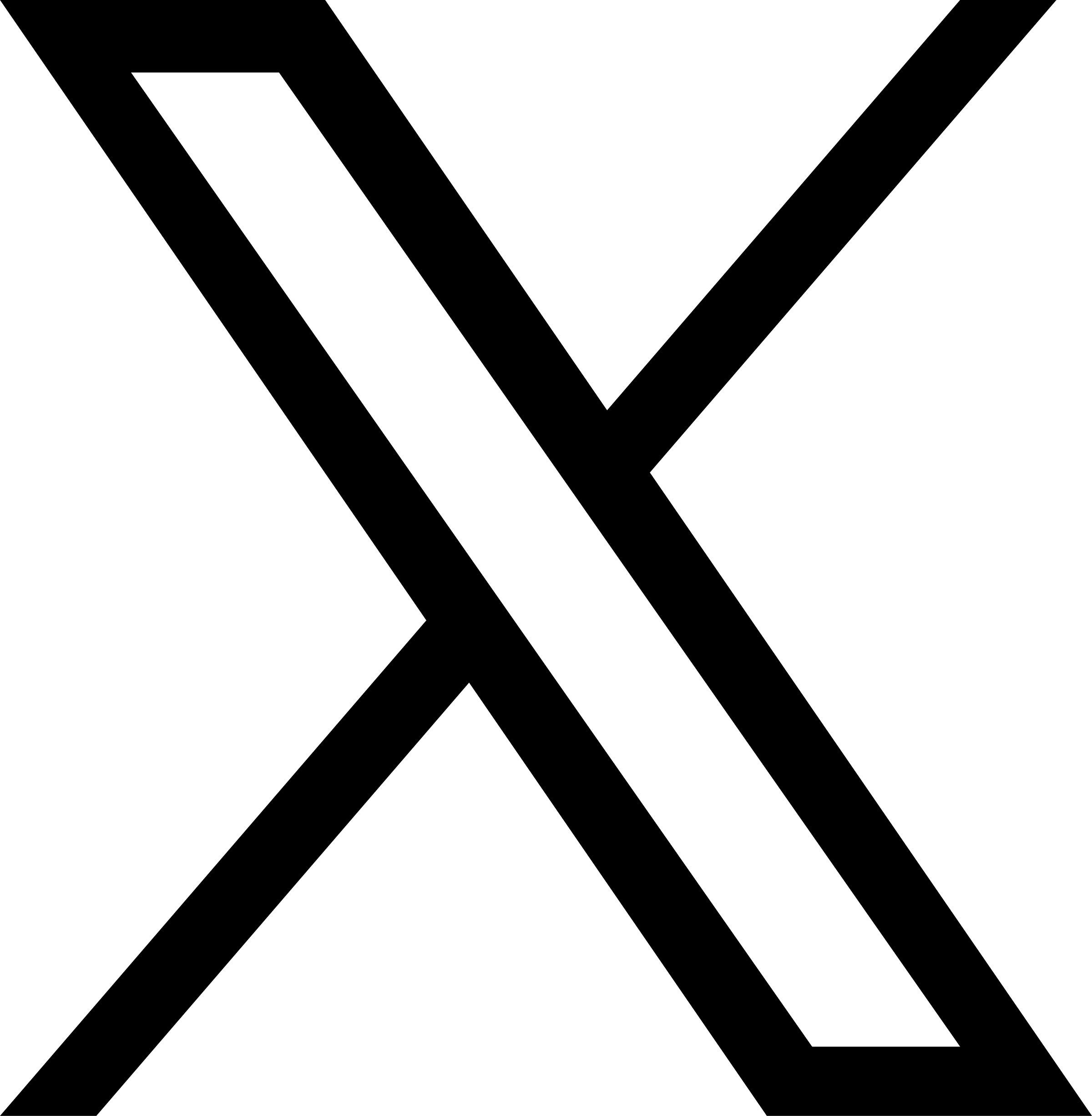
 Facebook
Facebook