帝の熱意、想いだけでは上手く回らぬのが政というもの、混乱を極めた建武新政は人々の反発を招き、やがて信濃国で北条高時が遺児、北条時行を擁した北条氏残党が反旗を翻すことを許してしまうことにもつながるのでございました。世にいう中先代の乱でございます。
勢いに乗った北条方は、足利直義の防ぎを崩し鎌倉入りをはたします。鎌倉を逃れた直義を救うべく鎌倉へと兵を進めようとする尊氏は、この時、後醍醐天皇に征夷大将軍への補任を奏請するも認められず、勅許なきまま葉月(8月)の二日に軍を発し直義の残兵と合流、北条時行の軍を破り、その月の十九日には鎌倉を回復するのでございました。
朝廷の令外官の一つである征夷大将軍はいわば武家にとって至高の栄誉、ただそれにとどまらず、この時すでに鎌倉時代を通して征夷大将軍が武家の棟梁として武家を統合し、幕府政治を行うという先例ができてしまっておりました。天皇親政を政の基軸に考える後醍醐帝としては、後に火種となりかねない征夷大将軍補任をおいそれと行うこともできない理があったのでございましょう。
半ばやむなく、追って尊氏を征東将軍へと補する後醍醐帝でございましたが、中先代の乱の事後もろもろ、また関東の守りを固めておきたいということからも京には戻らぬ尊氏。就中、乱の鎮圧に付き従った武家各々への恩賞分配を自己差配で行い、上洛の命にも従わずとなりましては、尊氏の建武新政離反と見做さざるをえず、建武二年(西暦1335年)霜月(11月)の八日、帝は新田義貞に尊氏追討を命ずるのでございました。ところが、錦の御旗を賜った義貞の旗色芳しくなく、ついには箱根・竹ノ下の戦いで足利方に敗退、師走(12月)十三日には総崩れとなるのでございました。軍団として見た時には如何にしても位や指揮系統で複雑さが目についてしまう南朝方の構成、加えて鎌倉を東西から挟撃せんとするならば、並々ならぬ統率力、政治力もまた求められるところ、荷が勝ちすぎるところがあったのやもしれませぬ。
そのまま尊氏は義貞勢を追撃し、まさに京へと迫らんばかりの勢いでございましたが、一方で、帝の命に応じて奥州から進発、尊氏軍を追って上京せんと騎馬軍を率いるのが鎮守府将軍・北畠顕家でございました。戦の成り行きを後から見据えるにやはり全体の統率をとることができず、ということに端を発すると思われる新田義貞軍総崩れの九日後、師走(12月)二十二日、義良親王を奉じ奥州兵五万は進撃を開始したのでございました。
一度進撃を始めた顕家率いる奥州軍は、すぐさまその凄まじきまでの力を見せることになるのでございます。翌建武三年(西暦1336年)睦月(1月)の二日には鎌倉に到達、足利義詮・桃井直常の軍勢を破り、鎌倉を攻略するという神速、猛襲ぶり。まさに顕家が陸奥下向以来、精強な奥州の兵をさらに鍛え上げ、一つにまとめ上げ、備えてきたことの現れでございました。翌三日には、足利方である常陸の佐竹貞義が顕家追撃に進発したことを受け、顕家は鎌倉を出て進撃を再開。睦月(1月)の六日には遠江に到り、十二日には近江国愛知川にまで到達いたしますが、敵地を一日に凡そ十里(約40km)を進み続け、百五十里(約600km)もの行程を半月ほどで進撃し続けたこととなり、日ノ本の歴史の中でも群を抜いた強行軍でございました。
如何に鍛え上げられ精強を誇る顕家の軍とはいえ、その強行軍は並々ならぬものであり、一重に後醍醐帝の想いに応え、世を導かんとする強い信念によって支えられてきたもの。後、顕家の軍は琵琶湖を一日かけて渡り、翌十三日には近江坂本で新田義貞・楠木正成と合流、顕家は彼らと軍議を開いたのでございます。そして、顕家は坂本の行宮に伺候し、後醍醐帝に謁見したと伝えられておりまする。
睦月(1月)十六日、顕家と義貞の軍勢は近江の園城寺を攻め、足利方の軍勢(細川定禅)を破り、これを敗走せしめ、次いで高師直と関山で合戦に及ぶ。相次ぐ戦いで足利方を打ち破り、睦月(1月)二十七から三十日の戦いにて新田義貞・楠木正成とともに尊氏を破り、京から足利勢を退けたのでござりまする。
休む暇なく、如月(2月)の四日には北畠顕家は新田義貞とともに尊氏・直義を追討すべく京を発ち、如月(2月)十日から十一日にかけ、京に再度攻め入る構えを見せる尊氏を摂津国豊島河原で破り、尊氏は九州へと落ち延びていくのでございました。顕家は義貞とともに足利軍の追撃掃討戦のため転戦し、如月(2月)十四日、京へと凱旋したのでございました。
和漢の学をもって代々仕えた北畠氏にあって、学識は無論のこと、正しき義を重んじ、武を尊ぶ顕家の姿は、真っ直ぐな陸奥のツワモノたちの心を掴みました。そして北畠顕家という若武者の真摯さが、陸奥の地を後醍醐帝が志す天皇親政の世を支える大きな力へとまとめ育むことを助けたのでございましょう。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

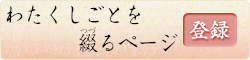
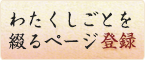



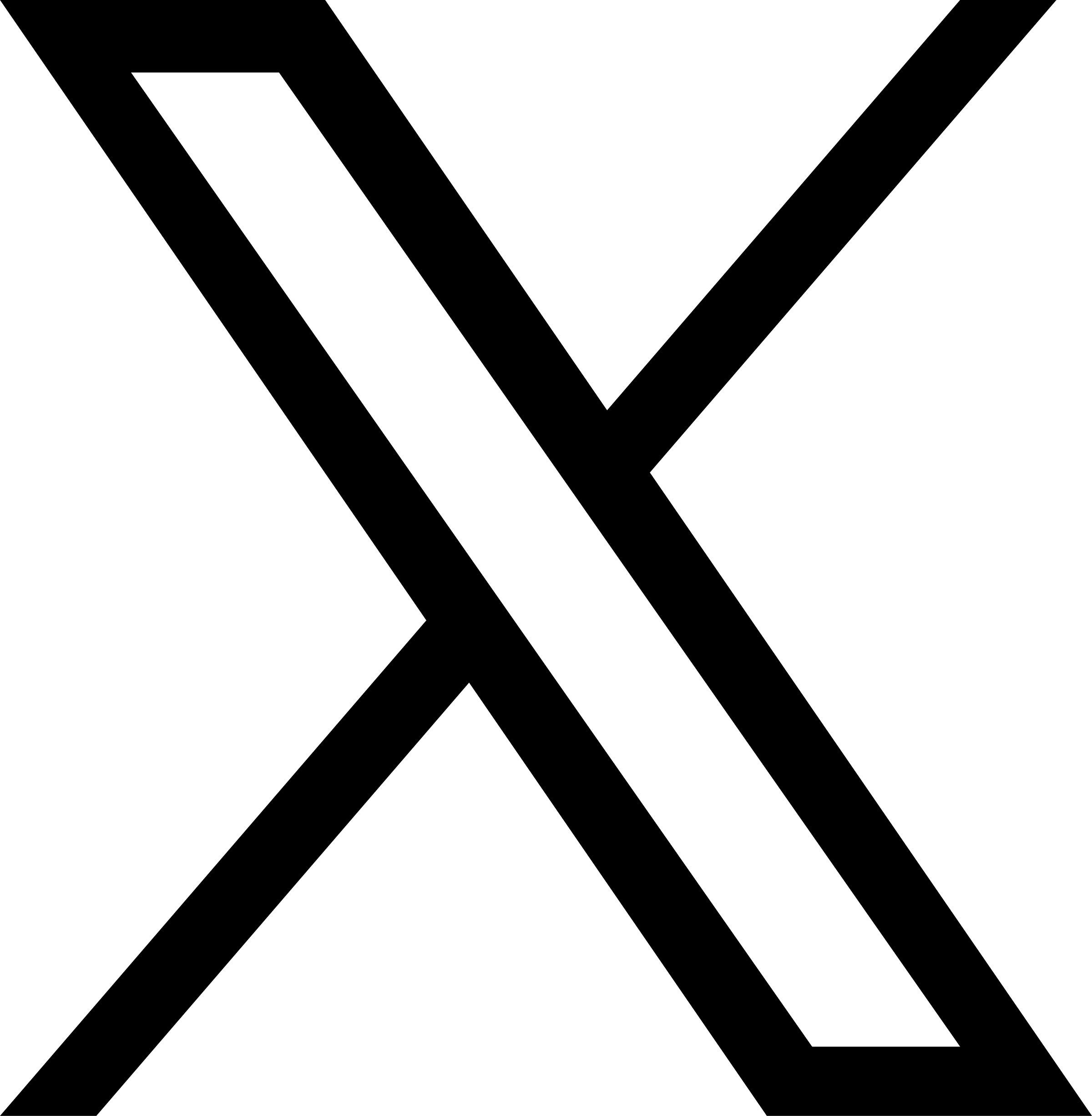
 Facebook
Facebook