さて、早い叙爵など優遇されてきた北畠氏でございますが、文保二年(西暦1318年)弥生(3月)生まれの親房が嫡男顕家もその例にもれず、元応三年(西暦1321年)睦月(1月)、齢三つで叙爵、幼年にて様々な官職につき、それこそ先例のない数え十四(満十二歳歳)にて参議に任じられ公卿に登るほどでございました。(従三位参議・左近衛中将)これには家格もさることながら、少なからず先を嘱望されてのこともまた有り、と推し量られるところでございますが、背中合わせに、政をその軸となりて支え得る人がまだまだ足りぬ、ということもまた然りと申せましょうか。さかのぼること二年、元弘元年(西暦1331年)弥生(3月)には、後醍醐帝の北山第(この時は西園寺公宗の山荘)行幸の際、顕家もこれに供し、御前で、眉目秀麗な北斉の皇族武将高長恭に扮して「陵王」を舞ったと伝わります。この折には帝も笛を吹き、前関白・二条道平が舞い終えた顕家に、自らの紅梅の上着、二藍の衣を褒美として与えたことも伝えられております。折に触れ、後醍醐帝からも信をよせられること重なり、陸奥へ皇子を下向させる際に頼みとするならば、との思いへとつながっていったのでございましょうか。
元弘三年/正慶二年(西暦1333年)皐月(5月)鎌倉幕府を滅ぼし、建武の新政を支える立場となっていた北畠顕家は、同年葉月(8月)従三位陸奥守を任じられます。先例なき若さで公卿に列した翌年のことでございました。そして陸奥守北畠顕家らに奉じられて陸奥国国府兼鎮守府である多賀城へと向かった義良親王(親王となるのは翌年の建武元年)はこの時齢五、奥羽地方の武家を南朝方する大役は、必然顕家の双肩にかかるところ大というものでござりました。
京を遠く離れ、理もまた異にするところ少なからずの中にあって南朝の旗印たる義良親王を導き育て、北条方残党を追い、豪族らが割拠し争いも絶えぬ陸奥の力を南朝方へとまとめ上げることが容易ならざるのは、想像に難くなきこと。幼き頃より先達の薫陶を受け、正しき義を重んじ、家門の誇りを胸に刻みたる顕家の力量が試される時でございました。されど良き馬産地であり、屈強で知られる兵馬を養う彼の地の武士たちを味方につけるということは、即ち政を正しくし、また軍においても認めさせるものなくしては、成し得るものではござりませんでした。代々和漢の学をもって朝廷に仕えてきた北畠氏は、政においてその知見を活かせる場を多く得てまいりましたが、若き顕家は武においても秀でたものを持ち、その一筋なる信念と調和を求める心根、そしてそれに支えられた武人としての姿は、時を経て陸奥の地に生きる多くの武士らの心を得、南朝方の大きな力を築いていったのでございます。
顕家は着任から一年をかぞえない建武元年(西暦1334年)葉月(8月)には津軽における北条氏残党の追討を開始、その年の霜月(11月)半ば過ぎにはこれを滅ぼし、津軽平定を成し遂げており、その戦機の掴み方、拙速で無駄のない戦ぶりは敵味方を畏怖せしめるものであったと語り継がれておりまする。
建武二年(西暦1335年)霜月(11月)には鎮守府将軍に任じられ陸奥将軍府の体制をより強固なものへと作り上げていきました。建武の新政における新たな地方統治機関となる陸奥将軍府が管轄するのは陸奥、出羽、下野、上野、常陸の五カ国であり、顕家には帝から強大な権限を与えられ、統治を進め易い様慮かられておりました。鎮守府将軍となる頃には、奥州の有力地頭であった南部政長や、結城宗広・伊達行朝らの勢力を糾合し、奥羽地方における軍事的な力も大きなものとなっておりました。ただ、鎌倉幕府を滅亡させた際、後醍醐帝から勲功第一とされ先に鎮守府将軍に任じられ、且つ奥州の北条氏旧領地頭職なども与えられ、奥州での勢力拡大をしていた足利尊氏としては、警戒感を拭い去れるものではなく、有力一門である斯波氏の当主斯波高経が嫡男、斯波家長を抑えとして配しておりまする。建武の新政において、陸奥国府を中心に奥羽から北関東の勢力を南朝方へ、という帝の目論見は、北畠顕家という若木の力により形作られてきておりましたものの、時はそのままひとつところへと流れてはくれぬ様相を呈し始めておりました。
『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』について
人の行いというものは、長きに亘る時を経てもなお、どこか繰り返されていると思われることが多くござりまする。ゆえに歴史を知ることは、人のこれまでの歩みと共に、これからの歩みをも窺うこととなりましょうか。
かつては『史』一文字が歴史を表す言葉でござりました。『史(ふひと)』とは我が国の古墳時代、とりわけ、武力による大王の専制支配を確立、中央集権化が進んだとされる五世紀後半、雄略天皇の頃より、ヤマト王権から『出来事を記す者』に与えられた官職のことの様で、いわば史官とでも呼ぶものでございましたでしょうか。様々な知識技能を持つ渡来系氏族の人々が主に任じられていた様でござります。やがて時は流れ、『史』に、整っているさま、明白に並び整えられているさまを表す『歴』という字が加えられ、出来事を整然と記し整えたものとして『歴史』という言葉が生まれた様でございます。『歴』の字は、収穫した稲穂を屋内に整え並べた姿形をかたどった象形と、立ち止まる脚の姿形をかたどった象形とが重ね合わさり成り立っているもので、並べ整えられた稲穂を立ち止まりながら数えていく様子を表している文字でござります。そこから『歴』は経過すること、時を経ていくことを意味する文字となりました。
尤も、中国で三国志注釈に表れる『歴史』という言葉が定着するのは、はるか後の明の時代の様で、そこからやがて日本の江戸時代にも『歴史』という言葉が使われるようになったといわれております。
歴史への入口は人それぞれかと存じます。この『のこす記憶.com 史(ふひと)の綴りもの』は、様々な時代の出来事を五月雨にご紹介できればと考えてのものでござりまする。読み手の方々に長い歴史への入口となる何かを見つけていただければ、筆者の喜びといたすところでございます。
<筆者紹介>
伊藤 章彦。昭和の出生率が高い年、東京生まれ東京育ち。法を学び、海を越えて文化を学び、画像著作権、ライセンスに関わる事業に日本と世界とをつなぐ立場で長年携わっている。写真に対する審美眼でこだわりぬいたファッション愛の深さは、国境をこえてよく知られるところ。
どういうわけだか自然と目が向いてしまうのは、何かしら表には出ずに覆われているものや、万人受けはしなさそうなもの。それらは大抵一癖あり、扱いにくさありなどの面があるものの、見方を変えれば奇なる魅力にあふれている。歴史の木戸口『史の綴りもの』は、歴史のそんな頁を開いていく場。
『歴史コラム 史(ふひと)の綴りもの』アーカイブはこちら

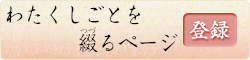
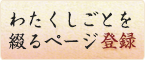



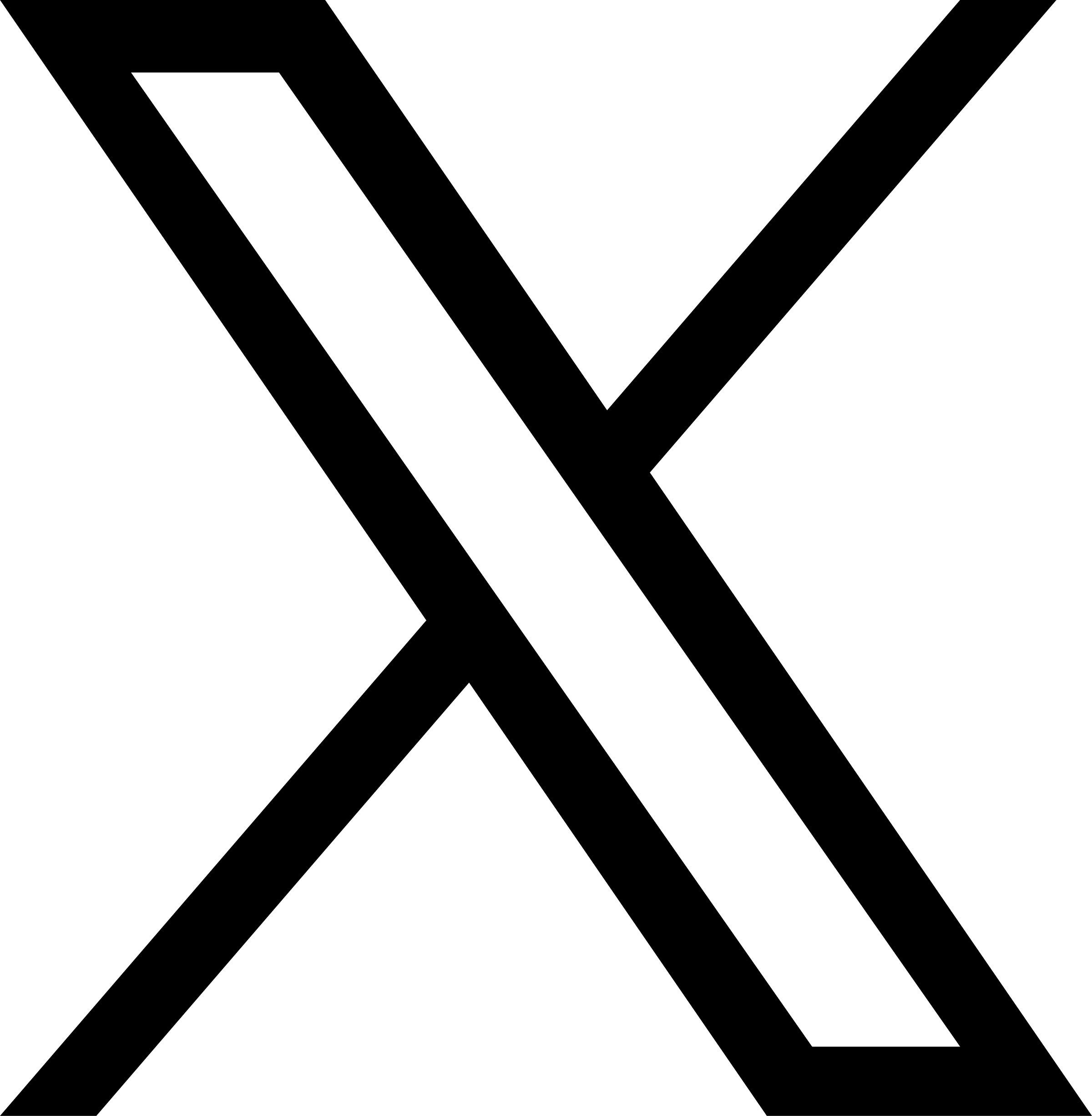
 Facebook
Facebook