十念の念仏もて、すなわち往生を得。往生を得るが故に、すなわち三界輪転の事を免る。
社会人になりますと、出世ということが否応なしに頭をよぎることも多くなるでしょう。学生の頃はそんなの興味ないよと思っていても、まったく関与せずに仕事を続けることは難しいかもしれません。周囲を見れば出世のために頑張っている人もいるわけですし、見比べてしまう機会も増えることでしょう。他者と自分を比べることはそれほど意味のあることではありませんが、人よりも少しでも勝っていたいという煩悩があるかぎり、簡単にスルー出来そうにはありません。なにかと胸がざわついてしまう。私もこうした経験があり、とくに今でも治っていません。
しかし大丈夫です。出世という言葉は、そもそも社会的な地位が上がることをまったく意味していません。率直に言いますと、これは仏教用語の誤用なのです。本来、世に出るのは私たち凡夫ではなく、仏が私たちを教化するため、この世にお出でになったということを意味します。仮に「社会人として立派に世に出て行く」の意味に転用することも不可でないとしても、他者を妬んでいたりしては、むしろ仏とは逆方面に行っていることになります。私たち凡夫にとっては、まずは「出世間」ということが大事であり、これは妬みや僻みの多い世間から脱出していくことを意味します。つまり、凡夫が仏の境地に至ることを意味しているわけで、おそらく通俗的な「出世」という言葉は、こちらとの関連ではないかと思われます。
日本の歴史を振り返ってみるならば、僧侶のなかにもいわゆる出世競争がありました。たとえば比叡山は中世かなりの権力を持っており、公家や武家にならんで、寺家のトップに立つことは大きな意味を持ちます。比叡山での出世競争は苛烈なものがあったことでしょう。しかし、同時にそもそも比叡山は日本宗教界のトップでもあることから、比叡山のトップ、つまり天台座主であることは仏の境地に最も近い立場にあると目され、通俗的な「出世」を比叡山で果たすことは、まさに「出世間」をも果たしたことを意味したことでしょう。こうした事情から、出世競争の場面だけが切り取られ、通俗的な「出世」という言葉が生まれたとも考えられそうです。
世間とは欲界・色界・無色界の「三界」を指しており、すべていまだ迷いのなかにある状態のことです。六道と対比しますと、無色界と色界と欲界の一部は天上道、残りの欲界が人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道となります。「輪転」(=輪廻転生)は三界をへめぐることであり、こうした世間から脱出することこそ仏教の目指すところなのです。「往生」するということは、浄土へ往き生まれることであり、浄土とは仏の世界を指しています。言い換えるならば、世間的な煩わしさから抜け出ることだと言っても良いでしょう。他者と比べて胸がざわつくような事態、そんな自分におさらばするのが出世なわけです。
ただ、そうは言っても簡単なことではありません。周囲も一緒の思いなら何とかなりそうですが、世間一般の環境ではあまりうまくいきそうにありません。だから僧侶は出家して皆で修行に励んだわけです。では、出家できないようなことであればどうするのか。日本では出家仏教はあまり根づかず、在家のなかでの仏教実践ということに注目が集まりました。大乗仏教は出家在家に拘らない側面が強いので、日本人に適した教えが多かったことも幸いでした。普段の生活のなかで、たとえばお念仏を称えたり、お題目を唱えたり、ご真言を唱えたり、または少しの間坐禅をしたりということも奨励され、少しでも自分を見つめる機会が持たれました。
たとえ十度のお念仏(=「十念」)であっても、仏の慈悲によりまして、私たちは救われていきます。こんな出家もままならないような自分であっても、仏は見捨てることなく、むしろ私たちをお目当てとして下さっているのです。在家仏教においては、仏のはたらきを信じると同時に、自分自身のいたらなさ、自分勝手に生きている様を知ることこそ大事であると言えます。胸がざわつくのは他者のせいではなく、むしろ自分自身の心に、他者を打ち負かしたいという歪んだ欲求があることの証でしょう。なかなか消えるものではありませんが、そんな自分なんだと知っておくほうが、多少は楽になるかもしれません。原因が判明するということは、なにかと良い道を示してくれるものだからです。
善福寺 住職 伊東 昌彦

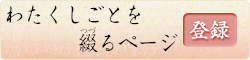
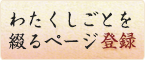



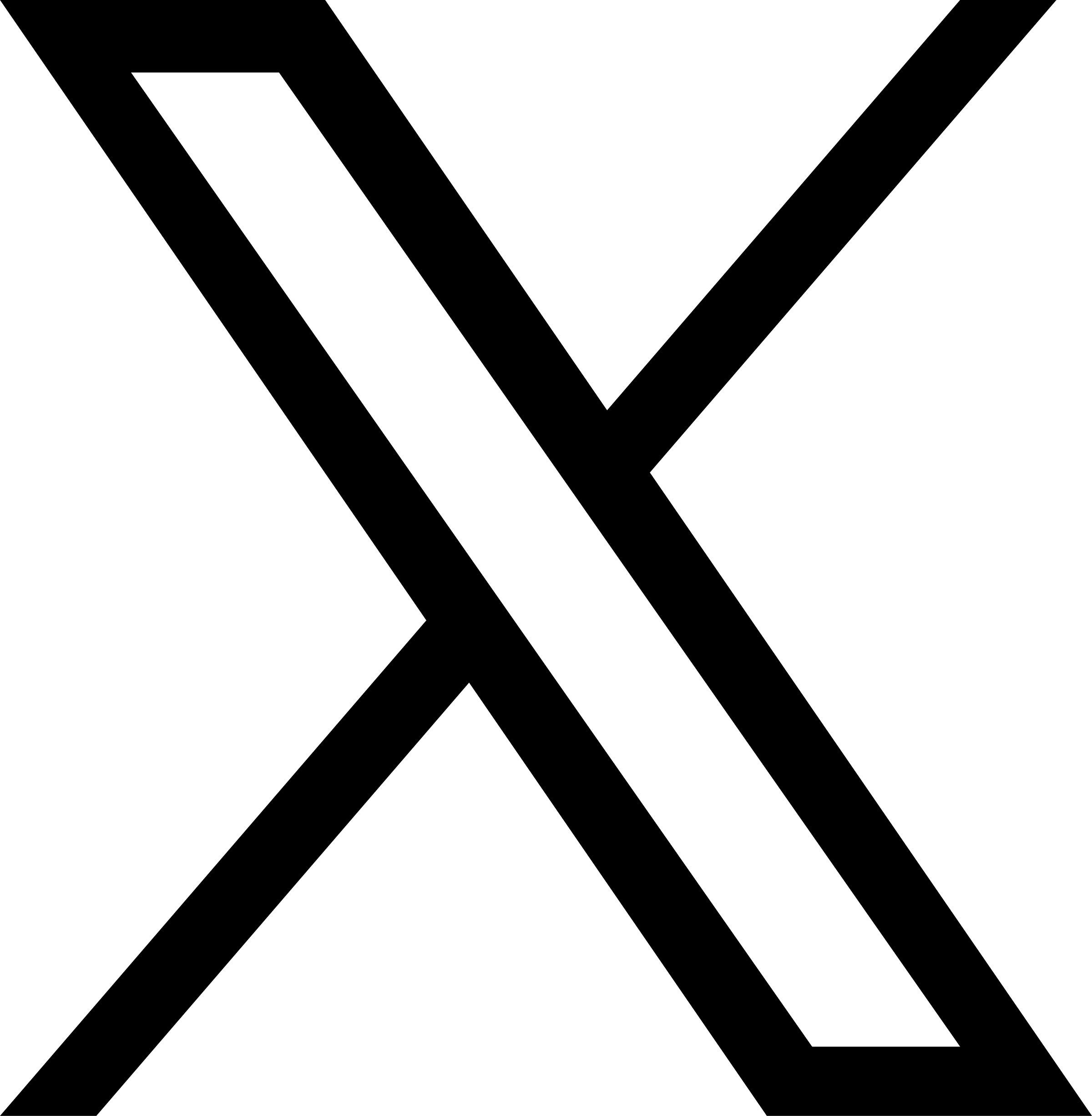
 Facebook
Facebook