今まで極楽浄土の話をしてきましたが、こうしたいわゆる「あの世」という概念を、日々の生活において捉えるならば、どういう意味が出て来るのでしょう。そもそも、なぜ極楽浄土が仏教で説かれるかと言えば、より充実した「今」を生きるためです。極楽浄土が善い国土だから早く行ったほうがいい、つまり早く死ねと言っているわけではありません。むしろ、行く準備をしとけということで、それが「今」の充実につながるということになります。
極楽浄土のような「あの世」がないとしたら、どう思われます?元気で健康のときは死なんてほぼ考えませんので、もとより「あの世」なんてないと一蹴される方も多いでしょう。しかしどうでしょう、自分は元気であっても、自分にとって大切な方が先に亡くなったとしたら、同じように考えられるでしょうか。「あの世」がないということは、亡くなれば無に帰すということです。何もかも無くなる。まさに無です。
もちろん、それでも問題ないと答える方はいらっしゃると思います。それはそれで大いに結構なことです。ただ、少なくとも私にはそう思えません。大切な方であれば再会したいですし、見守っていてもらいたい。そして、いざ自分が死ぬとなれば、やはり無に帰すということを想像するだけで怖い。無というのは文字通り何も無しです。空間すら無い。当然意識は無いですし、存在しません。無を感じることもない。
宇宙の果てがどうなっているのか想像するより恐怖感があり、寝る前に布団で考えてはいけません。翌日、目が覚めればすっかり忘れているものですが、忘れているだけで解決にはなっていません。生きているということが、実は常に無と隣り合わせなのだとしたら、私はとても不安です。仏教の説かんとするところは、「今」をより良く生きましょうということなのですが、死の問題はそこに首をもたげてくるものです。ああ、恐ろしい。
死がどのようなものであれ、死を受け入れることは難しいことです。生命なのでいずれ死ぬとは理解していても、心情としてはなかなかついていけません。だからこそ「あの世」が必要なのです。死は無ではなく、生活の続きなんだと思えることは安堵になります。たとえそれが証明できないものであったとしても、「あの世」があって続いていくと思えることこそ重要です。極楽浄土は「今」を生きるため、死の恐怖を少しでも軽くし、しっかりとした死への準備を促してくれます。
はっきり言いますと、極楽浄土があるのかないのかなんて分かりません。おそらく、経典に説かれているような具体的な環境ではないでしょう。高度な瞑想によって極楽浄土の知見を得た高僧方は、当時の表現法にしたがって経典に様子をまとめたのです。死んで見て来たわけではないので、客観的に証明できるものがあるわけではありませんが、私も何かはあると思います。私たちはこの宇宙の一員です。1つの命として、宇宙の何かに帰っていくということが極楽浄土へ往くこと、すなわち浄土往生なのだと考えています。
浄土往生は「この世」と「あの世」の橋渡しです。ここからは本当に宗教的な言い方になりますが、橋があると信じていれば、必ずあります。私はそう思って臨終を迎えたい。その時はもう分からなくなっているかもしれませんが、普段からそう思っていれば大丈夫でしょう。亡くなった両親にも再会したいのですし、何も無いよりよほど嬉しい死後の世界かな。いつ死ぬか知りませんが、浄土往生という橋渡しによって死の準備をしつつ、安堵した生活を送っていきたいものです。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦

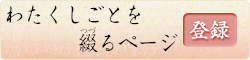
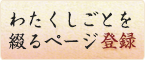



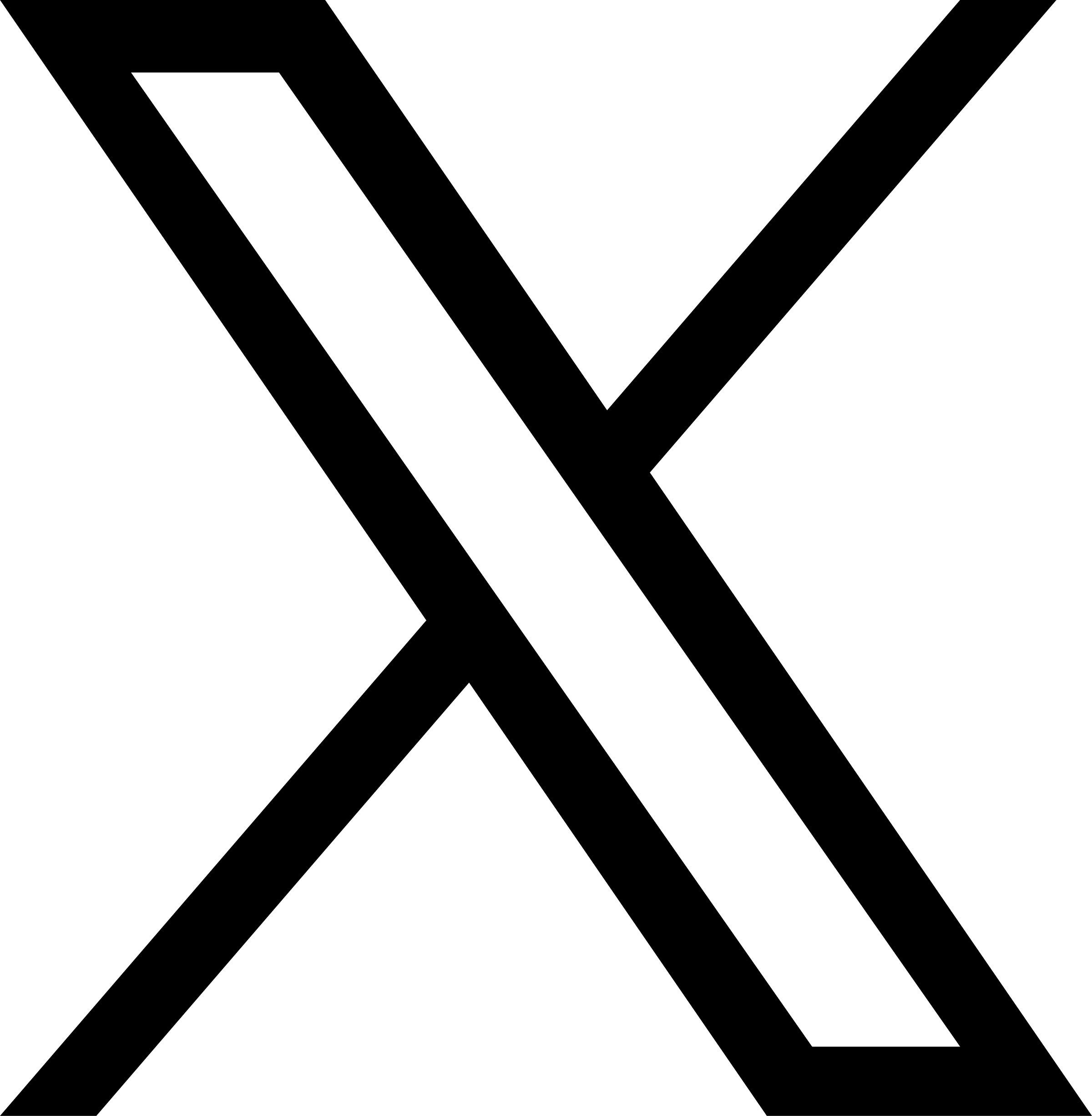
 Facebook
Facebook