浄土系の寺院で読誦することの多い『阿弥陀経』という経典に、「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」(しょうしきしょうこう おうしきおうこう しゃくしきしゃっこう びゃくしきびゃっこう)という一節がございます。これは阿弥陀如来の国土である極楽浄土においては、それぞれの色がそれぞれ自分自身の色をしっかりと映し出している、という様子を説いています。単純に4色しかないということではなく、無数の色があっても、互いに妨害しして個性を打ち消し合うことがないことを示唆しています。
これは人の個性です。人は千差万別、同じ思考の人はいません。一卵性の双子であっても、毎日同じ服を選ぶということはないでしょう。身体的に同じ存在とはいえ、別人格だからです。もし同じであるならば、何か外的な強制的要因が働いているはずです。別々で良いのです。経験も異なりますし、そもそも心はそれぞれ異なります。
しかし、個性と個性がぶつかり合いますと、時には問題も発生します。色合いで言うならば、ぶつかり合ってゴチャゴチャになれば、美しいとは言い難い風合いになってしまいます。
『阿弥陀経』では上記の経文の直後に、「微妙香潔」(みみょうこうけつ)と説かれます。これは、それぞれの色が「きわめて見事であり清らかな香りがする」という意味です。もう少し具体的に尋ねてみますと、『阿弥陀経』のサンスクリット語原典(『阿弥陀経』は漢訳であり、元々はインドのサンスクリット語で書かれていました)の同じ箇所では、「さまざまな色の蓮花はさまざまな色でさまざまな輝きがあり、さまざまな色に見えている。」(岩波文庫『浄土三部経(下)』、紀野一義訳)と説かれています。4つの色があっても、それぞれがぶつからず、それぞれが個性を発揮しているということでしょう。だからこそ、「きわめて見事」なのです。
昨今、多様性ということが声高に叫ばれていますが、互いに尊重しなければ成り立たない概念でもあります。自分が輝くためには、他者も輝いていなければなりません。私がいて、あなたがいる。あなたがいて、私がいるのですから。
『宗の教え~生き抜くために~』
宗教という言葉は英語のreligionの訳語として定着していますが、言葉では表し切れない真理である「宗」を伝える「教え」という意味で、もとは仏教に由来しています。言葉は事柄を伝えるために便利ではありますが、あくまでも概念なのでその事柄をすべて伝え切ることは出来ません。自分の気持ちを相手に伝えるときも、言葉だけではなく身振り手振りを交えるのはそのためでしょう。それでもちゃんと伝わっているのか、やはり心もとないところもあります。ましてやこの世の真理となりますと、多くの先師たちが表現に苦労をしてきました。仏教では経論は言うまでもなく大事なのですが、経論であっても言葉で表現されています。その字義だけを受け取ってみましても、それで真理をすべて会得したことにはなりません。とは言いましても、言葉が真理の入口になっていることは確かです。言葉によって導かれていくと言っても良いでしょう。本コラムにおきましては、仏教を中心に様々な宗教の言葉にいざなわれ、この世を生き抜くためのヒントを得ていきたいと思います。
善福寺 住職 伊東 昌彦

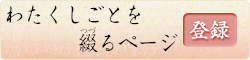
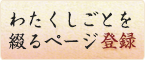



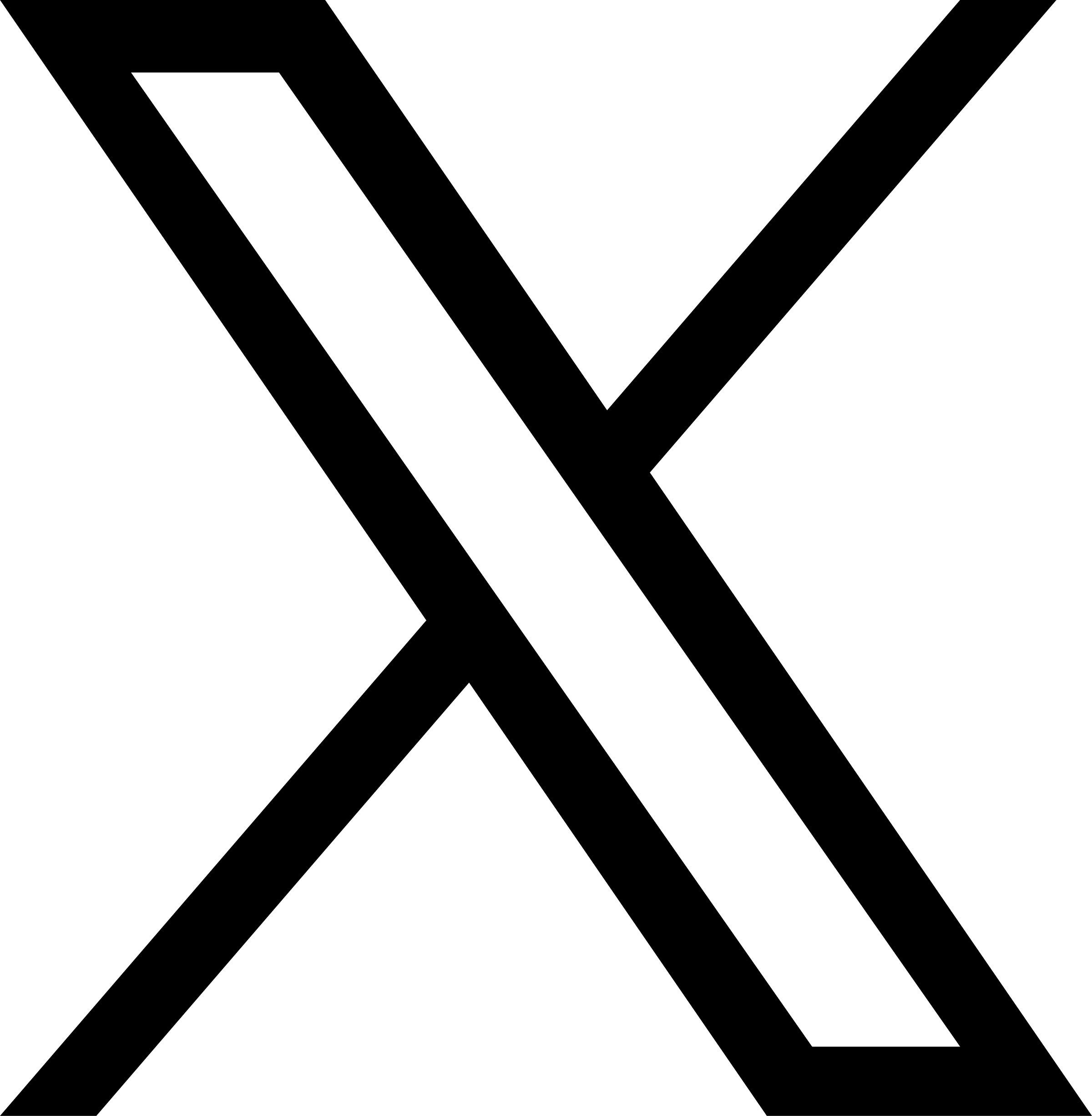
 Facebook
Facebook